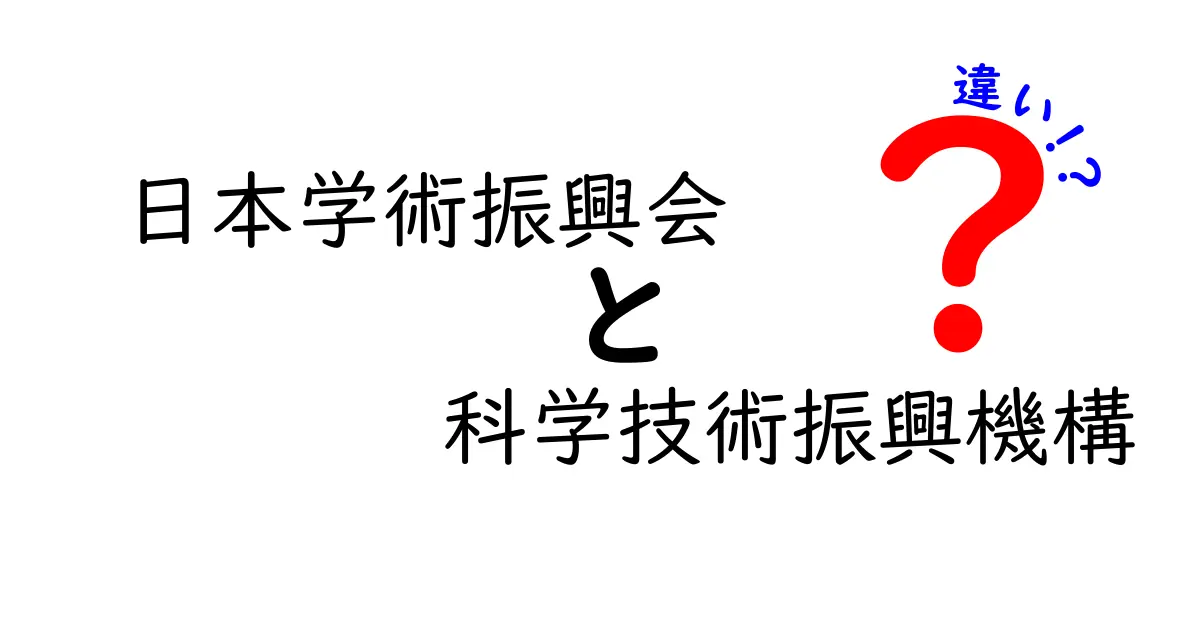

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
日本学術振興会と科学技術振興機構の違いを理解するための基礎知識
日本には研究を支える大きな組織がいくつかあります。とくに「日本学術振興会(JSPS)」と「科学技術振興機構(JST)」という名前は、研究者や学生、教育関係者の間でよく耳にします。名称が似ているのは混乱のもとですが、役割や仕組みが異なります。この記事では、初心者にも分かる言葉で、両者の違いをやさしく解説します。まず前提として、どちらも国が関わる機関であることは共通しています。
ただ、JSPSは「学術の自由と新しい発見」を支える基礎研究の支援に強みを持ち、JSTは「技術の応用と産業との橋渡し」を重視する取り組みを展開しています。
そのほかにも、予算の配分方法、研究者の選抜方法、助成の対象となる研究の種類など、細かな点で違いがあります。以下で詳しく見ていきましょう。
日本学術振興会(JSPS)とは
日本学術振興会、英語名は Japan Society for the Promotion of Science。長い歴史のある組織で、研究者の“基礎研究”を育てることを主な目的としてきました。基礎研究は新しい発見や理論の創出につながる土台であり、社会の直接的な利益がすぐには見えにくい性質を持つとされることが多く、これを支えるのがJSPSの役割です。JSPSは研究者が国内外で自由に学び、研究を進められるように、旅費・滞在費・研究活動費などの助成を提供します。代表的な制度として「若手研究者の支援」「若手研究者の海外派遣」「研究者交流のための奨励金」などがあります。制度は独立行政法人としての枠組みの中で運用され、審査は公正さを保つため透明性を重視します。審査の基準には、研究の独創性、社会的意義、研究計画の具体性、研究者の過去の実績などが含まれます。JSPSの助成を受けると、研究費の支給だけでなく、学会や研究者同士のネットワークづくりの機会も広がります。これにより、若い研究者が世界の研究コミュニティに参画しやすくなるのです。
科学技術振興機構(JST)とは
一方、科学技術振興機構、英語名は Japan Science and Technology Agency。JSTは「技術の発展と社会実装」を重視する組織として、研究の成果を産業や社会に結びつける役割を担います。JSTは長期的な研究プログラムや大規模研究プロジェクトを運用し、研究成果の実用化や技術開発の加速を目指します。結果として、企業と大学が協力する場が増え、論文だけでなく新しい技術や製品が市場に出やすくなるのです。
JSTはCRESTやPRESTOといった戦略的な研究プログラムを実施しており、分野横断のプロジェクトや、若手研究者のリーダーシップ育成にも力を入れています。
また、産業界との連携を促進するための仕組み、研究成果の知的財産化、起業支援、研究開発の評価指標の整備など、多角的な取り組みを展開しています。これらの活動は、日本の技術力を世界と競えるレベルに引き上げることを目標としています。
違いと用途:どちらを使うべきか
ここまでを踏まえると、両者の違いは「狙い」と「運用の仕方」に集約されます。JSPSは基礎研究の育成と研究者の人材育成を主要任務としているため、新しい発見や理論の深化を支える支援が中心です。それに対してJSTは「技術の社会実装」と「産業との連携」を重視します。研究成果を社会に速く届けるためのプログラム設計、企業との協働、技術開発の資金投入などが重要な役割です。
その結果として、研究の段階での支援の形が異なります。JSPSの助成は個々の研究者を中心に進むことが多く、応募も研究室単位で行われるケースが一般的です。一方JSTは大規模プロジェクトや研究グループを対象にした公募が増え、研究の組織的な推進が重視されます。
どちらを選ぶかは、あなたの研究の性質と目標次第です。もし「新しい発見を作ること」が第一の目標ならJSPSの奨励や若手支援が適しているでしょう。研究の成果を製品化したい、社会実装を早めたいと考えるならJSTの戦略的プログラムや産学連携の機会を狙うべきです。
ある日、友だちと部活の話をしていたとき、JSPSとJSTの話題が出ました。友達は「基礎研究にはJSPS、実用化にはJST」と覚えるといいと言い、私は「それだけじゃないよ」と返しました。JSPSが若手の研究者を世界に送り出す仕組みを持っていること、JSTが大規模プロジェクトを通じて技術を社会に届ける仕掛けを作っていることを、雑誌の記事と自分の授業ノートを照らし合わせて理解していきます。結局、研究者としては二つの道が並走しているイメージです。基礎の土台を固めるJSPSと、技術を形にするJST。この二つを使い分けることが、日本の科学技術の発展を後押しします。
私たちは日常の学校生活の中でも、研究者の話を聞く機会を大切にするべきだと感じました。なぜなら、学術の世界は一人ひとりの努力と組織の連携で成り立っているからです。
次の記事: 参謀と指揮官の違いを徹底解説!意味・役割・事例をわかりやすく »





















