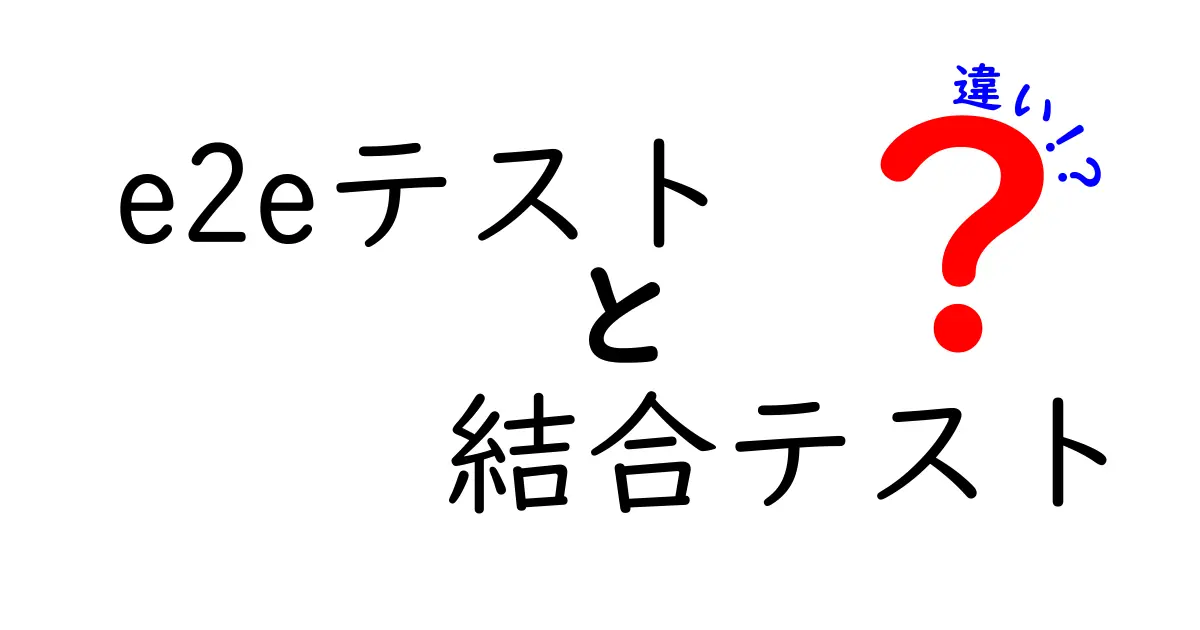

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
e2eテストと結合テストの違いをわかりやすく整理する
まずは基本の定義から。e2eテストとは、エンドツーエンドでアプリケーション全体の機能が動くかを検証するテストのことです。実際のユーザーが行う操作を想定して、画面遷移やデータの流れ、外部サービスとのやり取りまでを含めて検証します。一方、結合テストは、複数の部品やモジュールが正しく接続して動作するかを検証するテストです。ここでは主に内部の結合部分、APIやデータベースの連携、モジュール間のデータ受け渡しに焦点を当てます。
この二つのテストは目的が違います。e2eテストは「最終的な動作を保証する」ための検証であり、実際の操作を模倣します。結合テストは「小さな単位の品質を確保する」ための検証であり、開発初期の段階で問題を早く見つけやすくします。テストの順序としては、まず結合テストを行い、単体テストで部品の細かい欠陥を潰してから、最後にe2eテストで全体の動作をチェックするのが一般的です。
以下の表は比較の要点を整理したものです。
読み方のヒントとして、範囲・目的・実施コスト・対象技術を軸に整理します。
結合テストの例としては、API間の連携をチェックするテストや、データベースへの書き込みと読み出しの整合性を確かめるテストがあります。
また、モックやスタブを使って外部依存を取り除くことも一般的です。
最近、友達とテストの話をしていて、結合テストの話題になりました。結合テストは小さな部品同士の約束事を確かめる作業ですが、この“約束事”は私たちが普段使っているアプリの便利さと直結しています。例えば、あるアプリがログイン画面からダッシュボードへ移動する時、バックエンドのデータが正しく返ってくるか、あるいはデータベースの更新が正しく反映されるか。これらを1つずつ、手を動かさず自動で検証してくれるのが結合テストの大切な役割です。日常の体験から言えば、結合テストは“仕組みの見えないところを守る守護神”みたいな存在で、開発者が気づきにくい境界の不整合を教えてくれます。私が感じたのは、結合テストをしっかり設計すると、後のe2eテストがスムーズに走るということ。結局は、細かい部品の品質を固めることが全体の品質を押し上げるのだなと、友人と話しながら納得しました。





















