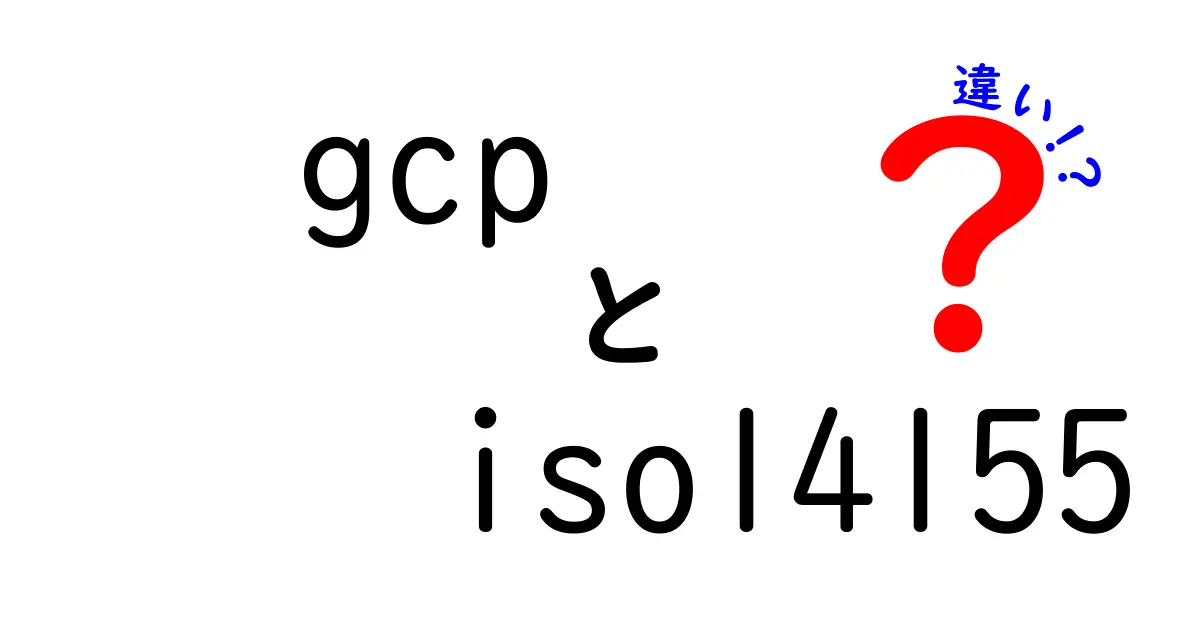

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
GCPとISO14155の違いを徹底解説 — 医療機器の臨床試験基準と薬事規制の差をわかりやすく
このテーマでは、GCPとISO14155の違いを単純に「薬の臨床試験」と「医療機器の臨床研究」の違いだとだけ説明して終わるのではなく、実務でどう扱われるか、現場のチェックリスト、倫理審査の順序、データの取り扱い、リスク評価、規制当局への報告の流れ、研究計画の作成時に何を用意すべきか、契約や監査の考え方の違いなど、具体的な観点を混ぜて解説します。
GCPはICHが策定した国際的な薬物臨床試験のガイドラインで、研究の倫理性とデータの信頼性を重視します。一方ISO14155は医療機器の臨床調査に適用される国際標準で、機器の適合性、リスクマネジメント、デバイスの性能評価の枠組みを中心とします。ですので、同じ「臨床試験」という言葉を使う場面でも、対象が薬物かデバイスかで要求される文書の種類、監査の焦点、保険の適用範囲が大きく異なるのです。このような背景を前提に、実務でよく遭遇する違いの要点を、初心者にも伝わるよう丁寧に整理します。ここではまず定義の差と適用範囲の違いを押さえ、次に実務上の影響、さらに研究計画を作るときの具体的なチェックリストを提示します。
GCPとISO14155の根本的な違い
GCPは薬物臨床試験のための国際的な指針で、倫理審査、被験者の同意、データの信頼性、監査の準備などを中心に規定します。
ISO14155は医療機器の臨床調査に適用される国際標準で、機器のリスクマネジメント、設計検証、適合性評価、使用環境における性能評価などを重視します。
対象が薬物かデバイスかで、必要な文書の種類や監査の焦点が異なり、同じ「医療研究」というくくりでも求められる品質マネジメントの体系が異なる点が大きな違いです。
実務では、契約の条項、監査の頻度、データ記録の運用、研究計画の作成方法にも差が出てきます。ここでは、要点を整理して、初心者にも理解しやすい言葉で具体的な違いを示します。
なお、GCPはICHのガイドラインとして世界中で共通の原則を示しますが、ISO14155は特定のデバイスカテゴリに適用されることが多く、地域の法規制と組み合わせて運用されます。最後に、現場で使えるポイントをまとめます。
現場での具体的な適用例と注意点
医療機器の臨床調査を進めるとき、GCPの原則をベースにISO14155のデバイス特有の要件を組み合わせる場面が現れます。
例えば、研究計画を作る際には、適切なリスク評価をデバイス特性に合わせて行い、患者同意の取得プロセスをデバイスの使い方に合わせて分かりやすく設計します。
データの記録では、データの信頼性と追跡性を確保するための文書化、監査証跡の管理、保管期間の設定などが重要です。
現場では、倫理審査の提出書類が薬物試験と共通点も多い一方で、デバイスの使用環境(病院、外来、製造現場など)に応じて追加のリスク管理が必要になります。こうした点を意識して計画を練ると、報告時の整合性が高まり、監査で指摘を受けにくくなります。
実務経験が浅い人には、まず「適用対象の差」「求められるデータの質」「記録の保全方法」を押さえることが近道です。
ISO14155は医療機器の臨床調査を対象とする国際標準で、デバイスの安全性と有効性を検証する枠組みを重視します。これに対しGCPは薬物臨床試験の倫理とデータ信頼性を守る原則で、現場ではデバイスと薬剤の扱い方が異なる点に注意が必要です。二つを同時に守るには、対象物の特性を理解し適切な記録・監査・リスク管理を組み合わせることが鍵です。





















