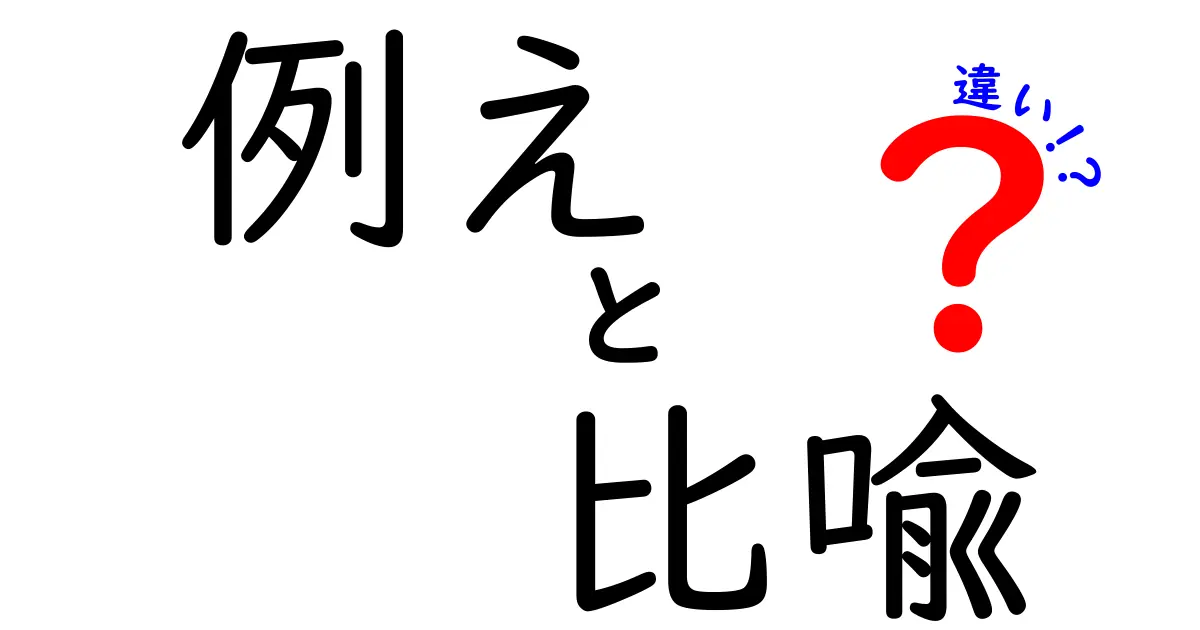

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
例えと比喩の違いを理解する基本の考え方
このセクションでは、まず「例え」「比喩」「違い」という三つの語がどう使われるかを整理します。
日本語では比喩は言葉の技法の総称であり、文章の情景や感情を豊かに伝えるための道具箱のようなものです。
この道具箱には直喩と暗喩という二つの基本形が含まれ、前者は「〜のようだ」「〜みたいだ」といった直截な比較語を使って、二つの事柄をはっきりと結びつけます。後者は比較の語を省略して、別のものへと置換することで読者に強い印象を与えるのが特徴です。
文章の目的や文脈に応じて、これらの技法は適切に使い分けることが大切です。
次に「例え」について考えます。例えは比喩の一形態ではありますが、読者の理解を深めるための具体的な説明の枠組みとして機能します。授業の解説で使われる例え話は、難しい概念を身近な出来事や比喩的な情景に結びつけることで、抽象的な内容を分かりやすくします。つまり例えは「説明の道具」であり、比喩そのものが目的となる場面では、過剰な比喩を避けて要点を伝える工夫が必要です。
この違いを理解すると、日常の会話や教科書の読み方が変わってきます。例えば科目の難問を説明するとき、直喩を多用してイメージを鋭く示すと、読み手は頭の中でその光景を描きやすくなります。一方で抽象的な理論を説明する場面では、暗喩を使うことで新しい視点を提示できることがあります。このような使い分けを意識するだけで、言葉の力をより効果的に活かせるのです。
例えと比喩の使い分けの実践ガイド
ここでは、実際の文章でどう使い分けるかを具体的に説明します。まずは伝えたい意味を決め、その後にどの程度の比喩を盛り込むかを決めます。文の目的が「説明」なら、直喩や暗喩の適切な組み合わせを考え、適度な比喩量を保つことが大切です。使いすぎると読み手が飽きてしまいます。逆に少なすぎると印象が薄くなるので、場面に応じた緩急を意識します。
また、例え話を用いる場合には、雑談のような親しみやすさと、事実の正確さのバランスを取ることが重要です。物語の中に現実の情報を織り交ぜると、読者は思考を止めずに理解を進められます。
以下の表は、使い分けのヒントを整理したものです。
日常の会話と作文の両方で使えるコツを条件別に並べています。
最後に、読者を意図した言葉選びが文章の説得力を決めます。語彙の選択、文の長さ、リズムを整えることで、例えと比喩の力を最大に引き出せます。適切な場面で適切な技法を選ぶことが、読者の理解と興味を同時に高めるコツです。
今日は直喩について友だちと雑談をしました。直喩は『〜のようだ』『〜みたいだ』と明確な比較語を使って、二つの事柄をわかりやすく結びつけます。私は、直喩を多用しすぎると文章が陳腐になることもあると話しました。そこで大事なのは、場面とリズムです。たとえば説明文の中で強く印象づけたいときには直喩を選択し、説明がすでにクリアな時には控えめにする、そんなバランス感覚が大切だと結論づけました。
次の記事: 修辞と修飾の違いを徹底解説!中学生にも分かる言葉の力と使い方 »





















