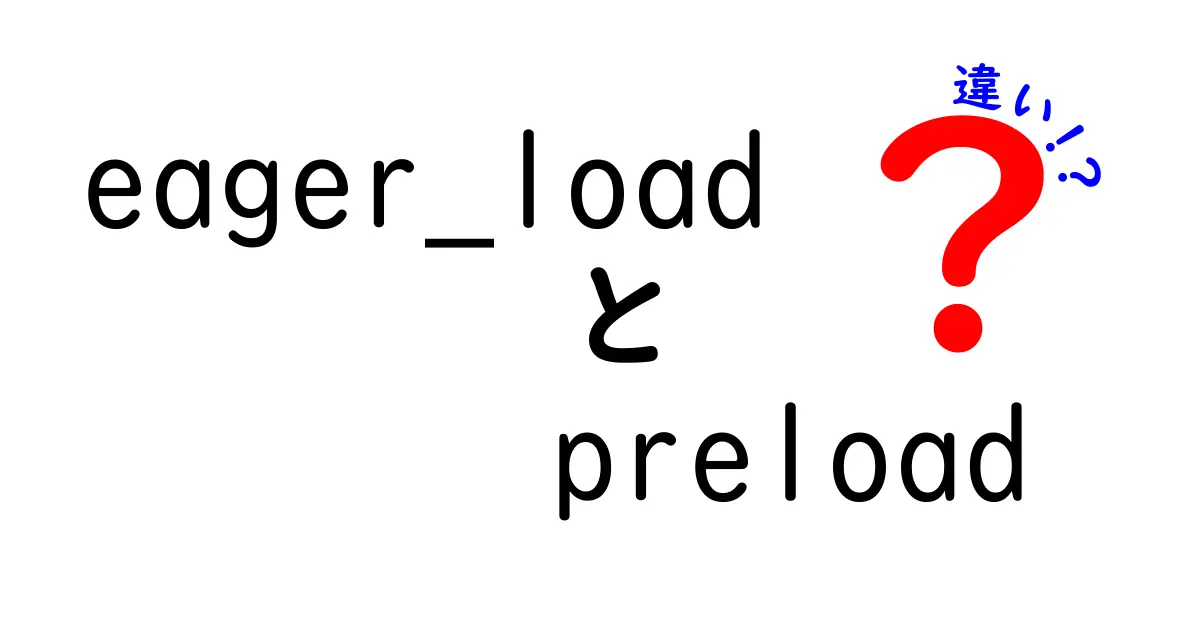

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
eager_loadとpreloadの違いを理解するためのガイド
このガイドでは Rails のデータ取得における eager_load と preload の違いを、初心者にもわかる言葉で解説します。まず最初に大事なのは N+1 問題の理解です。データベースに対して同じテーブルを何度も読みにいくと、処理が遅くなる現象を N+1 と呼びます。例えば投稿とコメントの組み合わせを表示する画面を想定します。投稿を一覧で取り出した後、各投稿に対してコメントを取りに行くと、投稿の数が多いほど実行される SQL の数は増え、結果的に待ち時間が長くなります。これが N+1 の基本的なしくみです。実務ではページネーションやフィルタリングが混ざると、N+1 の影響はさらに大きくなります。
この現象を解決するために Rails には eager_load や preload がありますが、それぞれ挙動が異なります。以下の節で、それぞれの特徴と実務での使い分けのヒントを詳しく見ていきます。
まず覚えておきたいのは、どちらを使うべきかは「関連データをどのように参照するか」「どの程度のデータ量を扱うか」「検索条件をどこに適用したいか」という点で決まるということです。
単純に N+1 を避けたいだけなら preload、関連データを結合して一括で取りたい場合は eager_load が向いていることが多いです。しかし実際には両者の中間的な使い分けも存在し、場合によって includes の挙動と組み合わせることで最適化できる場面があります。
本記事では、初心者にも理解しやすい具体例を使いながら、それぞれの特徴と使い分けのポイントを詳しく解説します。
eager_loadの仕組みと使いどころ
eager_load は関連テーブルを結合(通常 LEFT OUTER JOIN など)して取得します。これにより、1つの SQL クエリで親テーブルと子テーブルのデータを同時に取り出せるため、後から別のクエリを発行する必要がなくなり、N+1 が発生しにくくなります。特に「関連テーブルのデータを表示するが、検索条件を関連テーブルにも適用したい場合」には結合条件を使って絞り込むことが可能です。例えば posts と comments を結合して、投稿ごとに最新のコメントを表示したい場合など、1回の結合で必要データを取得できます。
ただし結合の影響で取得するカラムが増え、結果として返ってくるデータ量が増えることがあります。不要なカラムまで取り込むとクエリの実行時間が長くなり、場合によっては preload より遅くなることもあります。
また、結合条件の組み方次第で「重複するデータの扱いが複雑になる」局面もあり、複数の関連を同時に結合する場合にはパフォーマンス計画をしっかり立てる必要があります。実務でのコツとしては、必要なカラムだけを選択するように select で絞り込み、不要な結合を避ける工夫をすること、そして表示用途と検索条件の適用位置を明確に分けることです。
preloadの仕組みと使いどころ
preload は関連データを別々のクエリで取りにいきます。親テーブルを読み取り、その後に関連テーブルごとに別の SELECT を実行してデータを取得するため、結合のオーバーヘッドが抑えられます。複雑な結合条件を避けたい場合や、関連データの量が多くても安定した読み出しを確保したい場合に向いています。preload の利点は、1つの大きな JOIN を作らずに済む点で、データの結合に伴う重複や冗長なデータを避けられることです。ところが「関連テーブルに対して条件を使って絞り込みたい場合」には、preload だけでは望む絞り込みが難しいこともあり、その場合には includes や joins との組み合わせを検討する必要があります。実務での注意点としては、表示用途のクエリを別々に実行するため、キャッシュの活用やページネーションとの組み合わせを工夫することで、読み込み時間を安定させる工夫が有効です。
また、関連データを取得するタイミングと、表示する順序をどう保つかという点にも気をつけましょう。
実務での違いの見極めと注意点
実務では、まずデータベースに発行される SQL の数と実行計画を観察します。Rails のログや実行計画をチェックして、どのクエリがどの順序で走っているかを把握しましょう。eager_load は結合を使うため、結合条件をうまく設計しないと不要なカラムまで結合してしまい、読み込み量が増えてしまいます。preload は複数のクエリになるため、通信回数は増えるものの結合によるオーバーヘッドを抑えることができます。特に、ページングや検索条件が複数の関連にまたがる場合、preload の方が安定することが多いです。使い分けの具体的な判断材料としては、表示に必要なデータの性質(読み取り量、結合の複雑さ、検索条件の適用範囲)、およびデータの更新頻度を挙げられます。
もし可能なら Includes と eager_load の違い、あるいは joins との組み合わせを試して、実行計画を比較するのが最も確実な方法です。実務ではしばしば「最初は preload、特定の条件で絞り込む必要がある場合は eager_load を検討する」といった段階的なアプローチが有効です。
最後に、これらのテクニックは万能ではなく、データの性質によって最適解が変わります。常にパフォーマンスと機能性のトレードオフを意識し、必要なデータだけを適切に取得できるような設計を心がけましょう。
まとめとよくある誤解
本記事の要点を簡潔に整理します。
1) eager_load は関連データを結合して1回のクエリで取得するが、結合条件の影響で不要なカラムまで含む場合がある。
2) preload は関連データを別々のクエリで取得するため、結合のオーバーヘッドは低いがクエリ数が増える。
3) 実務では「N+1 を避けたい場面」「結合条件を活かした絞り込みが必要な場面」「データ量と表示パターン」を考慮して使い分ける。
4) includes は状況に応じて自動的に eager_load 又は preload に振ることがあるため、使い分けの癖を身につけることが重要。
5) 最適解はケースバイケース。性能と機能性の両立を目的に、実際のデータ量で性能試験を行い、ログと実行計画を基に判断しましょう。
状況に応じた使い分けを習慣化することが、開発者としての成長にもつながります。
友だちとカフェで Rails の話をしているときの雑談風小ネタです。Aさんは「eager_load と preload、どっちが速いの?」と尋ね、Bさんは「速さはケースバイケースだよ」と答えます。Aさんが「関連データを結合して1回で取るのが楽だよね」と言うと、Bさんは「確かにその場面は早い。ただし結合が複雑になりすぎると、余計なデータを拾ってしまって遅くなることもある」と返します。さらにBさんは「preload は別クエリだから、データ量が多いときは安定することが多い。でも絞り込みが難しくなる場面もある」と続けます。二人は自分たちのアプリケーションを思い浮かべ、実際にクエリ数と実行計画を見ながら、どの場面でどちらを選ぶべきかを具体的に議論します。会話の中で、最適解は常に状況次第だという結論に至り、データの量・表示箇所・検索条件を総合的に判断する姿勢が大切だと再確認します。





















