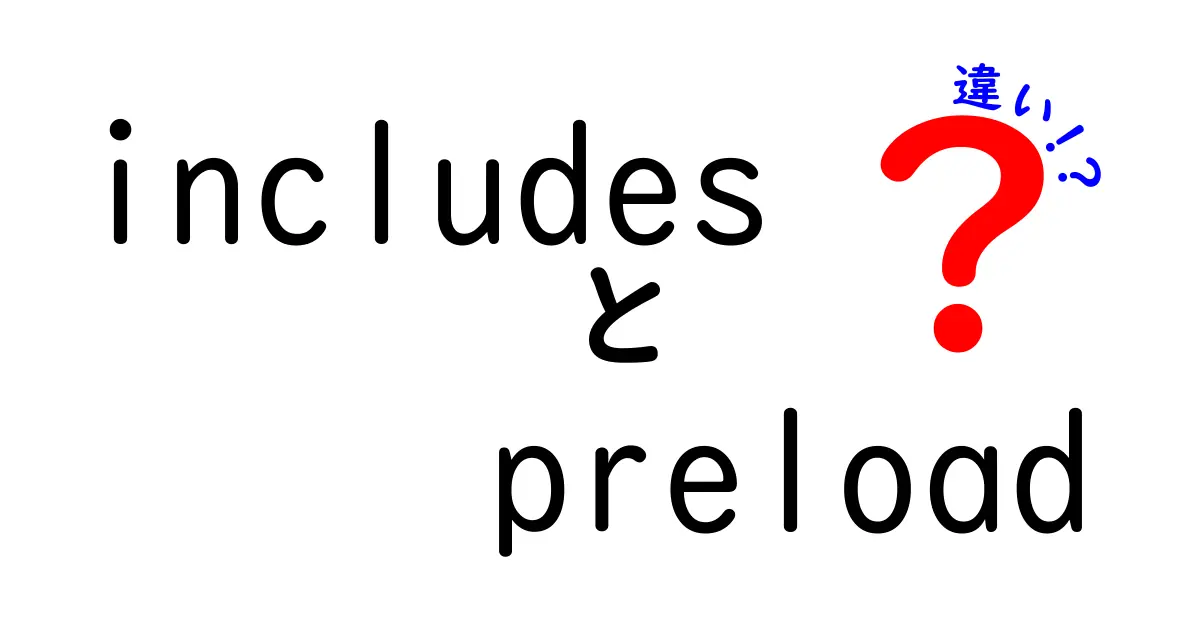

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
includes preload 違いを徹底解説!初心者でも分かるウェブ最適化のコツ
ウェブページを速く表示するためには、リソースをどう扱うかがとても重要です includes は資源をページに「含める」作業全般を指す広い概念です。サーバーサイドの include 指令、テンプレートのインクルード、HTML でのリンクやスクリプトの挿入などがこれに該当します。これらはページの構成を再利用可能にし、開発の効率を高めますが、同時に読み込み順序やレンダリングの影響をしっかり管理しないと、表示遅延を招く原因にもなります。
一方 preload はブラウザに対して「この資源を今すぐ取得してほしい」という強い指示を出す機構です。リソースヒントとも呼ばれ、特定の資源を初期表示に間に合わせるために使われます。適切に使えば初期表示のタイムを短縮でき、ユーザー体験を改善できますが、過剰に使うとネットワーク帯域を無駄に使うリスクもあります。
この二つの機能は目的と使い方が異なるため、状況に応じて正しく組み合わせて使うことが大切です。以下では基本の考え方、使い分けのコツ、実際の運用例を分かりやすく整理します。
まず覚えておきたいのは 「クリティカルな資源をどう扱うか」 という点です。例えば上部の CSS やフォント、最初に表示される画像などはユーザーの体感に直結します。これらを includes でまとめて読み込むだけではなく、preload を適切に使って先読みすることで、表示の遅延を減らせる可能性があります。ただし 過度な preload は無駄な帯域を消費する ため、CPU負荷やネットワークの帯域を監視しながら使うべきです。
また includes が意味するのは「含める」という行為そのものなので、構成を整理し再利用性を高めることが目的です。対して preload は指示の性質が強く、資源がいつ使われるかを予測して先に取得 するのが目的です。
基本の仕組みと用語の整理
ここで includes の幅と preload の特性を整理します。 includes はサーバーサイドの処理やテンプレートの組み込み、あるいはフロントエンドのリンク・スクリプトの挿入など、資源をページに「組み込む」ための手段の総称です。これにより複数の資源を適切に管理でき、機能の再利用性も高まります。
この意味で includes は一般的に複数の資源を同時に管理する際の土台となります。対して preload はブラウザに対して「この資源を優先的に読み込ませたい」と伝える手段です。as 属性で資源の種類を伝えることにより、ブラウザは最適な読み込み戦略を選択します。結果として、初期表示のスムーズさを高められる場合がありますが、正しく使わないと逆効果になることも覚えておきましょう。
使い分けの実践ガイドと注意点
実務での使い分けのコツは次の三点です。第一に クリティカル資源を優先することで、ページの第一印象を良くします。CSS の最初の部分、重要なフォント、すぐに描画を開始する画像などは preload の候補となります。第二に 読み込みのブロックを避けるため、不要な資源の preload は避け、通常の includes で読み込む資源と組み合わせます。第三に 効果を検証することです。実際のパフォーマンス改善はサイトごとに異なるため、Lighthouse や Core Web Vitals の指標を確認し、必要なケースだけ preload を追加します。以下の表は代表的なポイントを比較したもの。
この表を見れば、includes と preload の違いが頭の中で結びつきやすくなります。最後に実務でのポイントを短くまとめます。
・重要な資源は preload で先回しの可能性を探る
・過剰な preload は避ける
・ページの構成を見直して includes の再利用性を高める
昨日、友達とカフェでウェブの話をしていて preload の話題になった。友達は『 preload があると資源が必ず早く読み込まれるのでは?』と期待していたが、実際には先読みを指示するだけで、使い方次第では効果が薄いことを僕は説明した。結論はシンプルで、どの資源が本当に初期表示に影響するかを見極め、必要な場合だけ preload を使うこと。読み込みの順序をコントロールすることで、UXは大きく変わる。設計と検証の回転数を増やすことが、ウェブのパフォーマンス改善には欠かせない。





















