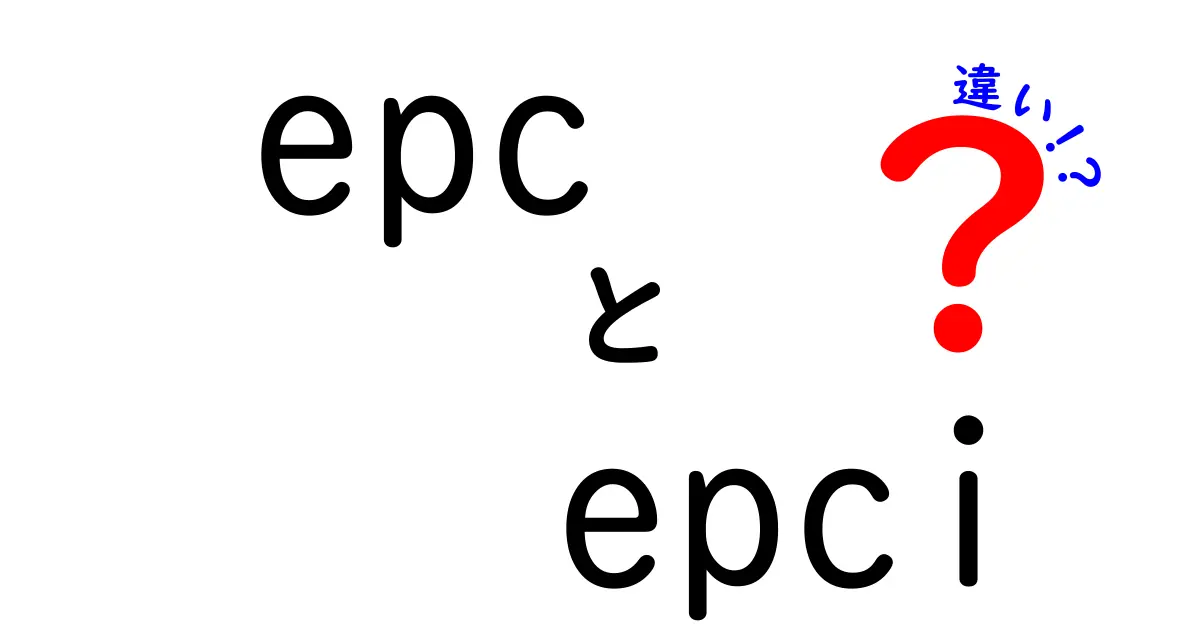

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
EPCとEPCIの基本を押さえよう
EPCとEPCIは巨大な産業プロジェクトで使われる契約の呼び名です。ここでは、まず両者の意味を分かりやすく整理します。EPCは Engineering, Procurement, Construction の頭文字を取った略語で、設計・資材調達・建設の三つの工程を一括して請け負う契約形態です。EPCを選ぶと、発注者は設計と購買・工事の責任を一つの契約者に集約させることができ、現場での連携を一本化して納期と品質を管理しやすくなります。これに対してEPCIは Engineering, Procurement, Construction, Installation の略で、設計・購買・建設に加えて現場での設置・据付までを請け負います。
EPCとEPCIの大きな違いは「現場の設置作業が含まれるかどうか」です。現場設置が含まれるEPCIでは、契約者が設置作業の計画・実行・試運転までを責任をもって進めることが多く、発注者は現場での接口管理の手間を軽減できます。逆にEPCでは、設計と購買・建設の責任は契約者に集中しますが、現場の設置は必ずしも契約の範囲外であったり、分離して別のベンダーが担当するケースもあります。
EPCって何?どんな工程が含まれるのか
EPCの三つの柱を詳しく見ていきましょう。
Engineering(設計)は、機器の仕様決定、配管・電気・構造の図面作成、計算、検証などを含みます。ここでの責任は、機能要件に対する技術的解決と、後の購買・施工の前提条件づくりです。
Procurement(購買)は、設備・部材・資材を世界のサプライヤーから調達する活動です。コスト管理・納期管理・品質保証の観点から、設計と現場の間にある潜在的なズレを拾い出し、適切な代替案を提案します。
Construction(建設)は、現場での組み立て・設置・結線・試運転・最終受け渡しまでを含みます。建設フェーズは多くの場合、長い時間がかかり、現場の環境・天候・交通事情などの影響を強く受けます。
このようにEPCは「設計・購買・建設を1社で完結させること」を最大の特徴としますが、実務では設計と購買の連携、そして建設のスケジューリングを厳密に管理する能力が求められます。現場で発生するインターフェースの問題を最小化する工夫が、納期とコストの安定化につながります。
EPCIに「Install」が加わる意味と利点・注意点
EPCIは「Installation」を含むことで、現場での設置・据付・試運転・場合によっては現場での切替・接続までを契約者の責任として引き受けます。海上プラットフォームや油田の設備など、現場での大規模な作業が必要なプロジェクトでは、設置作業を含めた一括契約のメリットが非常に大きいです。
利点としては「単一の窓口による調整の簡略化」「interface の減少」「納期の短縮・予測性の向上」が挙げられます。契約期間中の変更対応も、同一ベンダーが設置まで責任を持つため、手戻りが減る傾向にあります。
一方で注意点もあります。Install を含む分だけ、契約者側のリスクが増え、現場での不可抗力、特殊な資材の納期遅延、現地調達の難易度が納期とコストに直結することがあります。さらに、現場の安全管理・環境規制・周辺ステークホルダーとの調整を契約者が強く受け持つため、プロジェクト管理能力がより重要になります。
契約の実務ポイントと判断基準
実務で EPC と EPCI を適切に使い分けるためには、プロジェクトの特性とリスク許容度を前提に判断します。大きな判断軸は「現場の設置が必要かどうか」「納期の厳しさ」「顧客が現場での Interfaces にどれだけ関与したいか」です。現場の設置を含めると、EPCI の方がシームレスなスケジュール管理が可能ですが、契約の複雑さと単価の上昇という現実的なコスト要因も無視できません。
ベンダー選定では、過去の実績・現場での安全記録・協力企業との連携力を重視します。支払い条件はマイルストーンと成果物ベースを組み合わせ、遅延が生じた場合のペナルティやボーナスの設定も重要です。
結論として、発注者は「現場設置を任せるべきか」「設置を自前で管理するのか」を、プロジェクトのリスク分布とコスト効果の観点から総合的に判断すると良いでしょう。理解を深めるために、下の表で差をもう一度整理します。
このように、EPCとEPCI は「設計・購買・建設」に加えて「設置」という現場作業の有無で大きく分かれます。契約を検討する際には、技術的要件だけでなく、現場の運用・安全・法規制の観点も含めて総合的に判断することが重要です。
読者のみなさんがプロジェクトを前に進めるとき、どちらの契約形態が自分たちの目的に最も適しているのかを、具体的な案件の条件に合わせて整理できるようになると良いですね。
友人と学校の課題を話していたとき、EPCとEPCIの違いをどう説明すれば伝わりやすいか考えました。EPCは設計・購買・建設を一括で担う契約で、設計の要件を決める責任とコスト管理を1社に集中させるイメージです。一方、EPCIはこれに加えて現場での設置まで含むため、現場の作業計画と実行までを同じベンダーが担います。 Install という語は現場での大掛かりな作業を連想させ、納期管理や安全管理の難易度を高めます。現場設置を含むかどうかで、リスクの配分が大きく変わる点がポイントです。授業のグループワークでも、現場設置を含む契約は一括窓口の利便性と同時にコスト増の要因になることを体感しました。





















