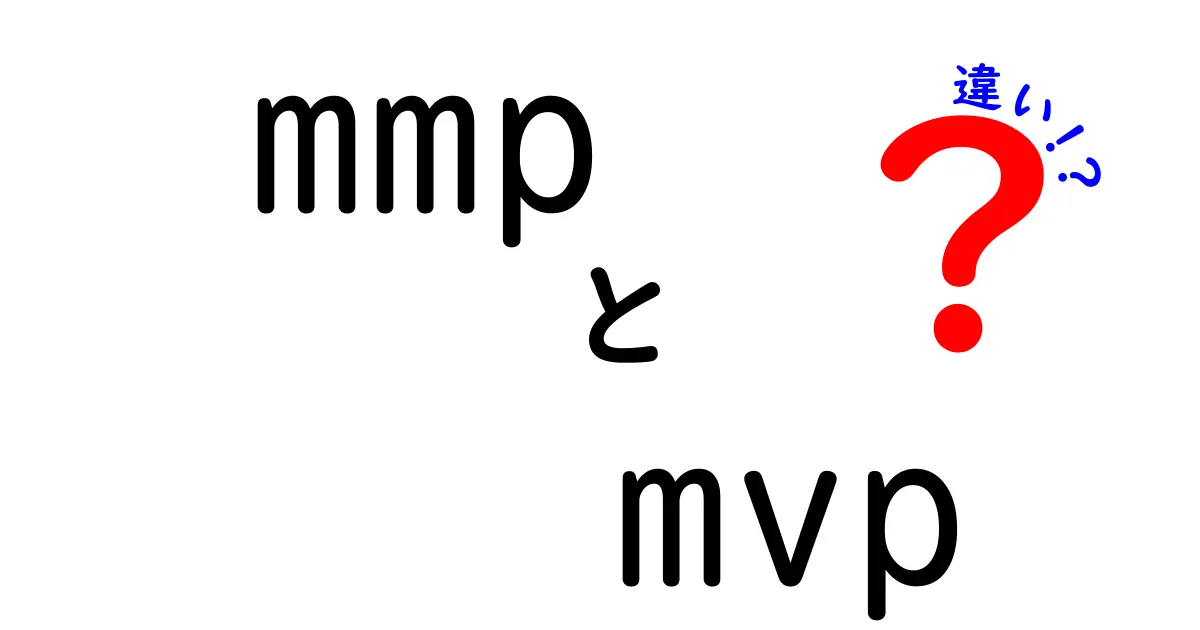

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに
近ごろよく耳にする用語の一つに、MVPとMMPがあります。これらは似ているようで目的が異なるため、どちらを選ぶかで開発の方向性が大きく変わります。
MVPは「最低限の機能で顧客の反応を知る」ことを目的とした学習型の製品であり、試作を繰り返しながら仮説を検証します。
一方のMMPは「市場に対して最低限の価値を提供できる製品」を意味し、機能を最小化したうえで市場性や販売価値を重視します。
この違いを正しく理解して使い分けることが、時間とコストの節約につながります。
本記事では中学生にもわかる言葉で、MVPとMMPの違いを詳しく解説します。
まずは基本の考え方を押さえたうえで、実務での使い分け方、そして具体的なステップまで順を追って説明します。
最後には実務に即した判断基準を整理しますので、開発方針を決める際の参考にしてみてください。
MVPとMMPの基本となる考え方
MVPは、まだ完成させきれていない段階でも、顧客が実際に使える最低限の機能を備えた製品です。目的は「仮説が正しいのかを早く知ること」であり、学習のサイクルを回すことに重きが置かれます。市場全体の理解を深めるための実験道具として役立ち、データや顧客の反応を基に改善を重ねていきます。
この過程では、機能を増やしすぎず、ユーザーが何を求めているのか、どの機能が価値を生むのかを見極めることが重要です。
MVPの成功は「学習結果を次の投資判断に繋げられるかどうか」に左右されます。
MMPは、製品を市場に出す際の最低限の販売価値を満たすことを狙います。すなわち、機能は最小限に抑えつつ、価格設定、ブランドメッセージ、サポート体制、品質安定性といった市場投入に必要な要素を整え、実際に売れる状態を目指します。MMPは「市場に出して売れる価値を確保する」という観点が強く、完成度を高めつつもリリース後の運用まで見据えた設計になります。
この二つの考え方を混同すると、開発の方向性がブレたり、リソース配分を誤ったりします。例えば、学習に重きを置くMVPを市場リリース直前の収益化のために使ってしまうと、顧客が本当に求めている価値を把握できず、長期的な市場適合性を失う可能性があります。逆に、MMPを追求しすぎて市場投入のために過剰な機能を揃えると、準備が遅れ、競合に遅れを取ってしまいます。ここからは、両者の違いを具体的な視点で整理していきます。
実務での違いを理解する表
以下の表は、MVPとMMPの違いを要点ごとに整理したものです。実務での判断材料として活用してください。
重要ポイントとして、MVPは「知るための実験道具」であり、MMPは「市場で売る価値を最小限に揃える製品」です。両者の目的を混ぜてしまうと、判断軸がぼやけてしまいます。現場では、最初のリソース割り当てをMVPの検証フェーズに置き、仮説が十分に検証できた段階でMMPの準備へ移行するのが理想的です。
具体的な使い分けのステップ
実務での適用例として、以下のステップを参考にしてください。
1) 問題設定と仮説の明確化: 顧客が抱える本質的な課題と、それに対する解決策の仮説を紙に書き出します。
2) MVPの設計: 学習を最大化できる最小限の機能セットを決定します。ここでは「この機能がなければ検証できない」という必須機能だけを残します。
3) 学習指標の設定: どのデータを見て仮説を評価するか、具体的な指標を決めます。例として、使い方の頻度、リテンション、課金意欲の有無などがあります。
4) MVPのリリースと検証: 実際に市場に出してデータを回収します。顧客の声を丁寧に記録し、仮説を検証します。
5) 解析と意思決定: 学習結果を基に、仮説が正しいか、次にどの機能を追加するべきかを判断します。
6) MMPへの移行準備: 学習で得た価値観を基に、実際に市場で売れる価値を整理します。価格設定・マーケティング・サポート体制を整え、最低限の販売可能性を確保します。
7) MMPのローンチ準備: 最低限の機能だけを残しつつ、品質と信頼性を高め、顧客に適切な価値を伝える準備を整えます。
8) 市場投入と運用: 発売後は顧客の反応を継続的に追跡し、必要に応じて改善を回します。
まとめと実践ポイント
要点をまとめると、MVPは学習のための最小限の製品であり、MMPは市場に出す価値を最小限の機能で実現する製品という違いがあります。
現場の実践では、はじめに仮説を検証するためのMVPを選択し、仮説が十分に検証できた段階でMMPへと移行するのが最も効率的です。
この考え方を身につければ、無駄な機能追加を避けつつ、市場のニーズに合致した製品づくりを進められます。
最後に、数字と人の声の両方を重視して判断するクセをつけてください。
そうすることで、冗長な作業を減らし、価値ある製品をより早く届けることができます。
MMPという考え方は、ただ機能を揃えるだけでなく、実際に市場で saleable value を持つことが大事だという発想につながります。つまり、最低限の機能だけでなく、顧客が『これを買う理由がある』と感じられる価値をどう工夫して提供するかが鍵です。私たちは友達と雑談するように話を広げながら、MVPとMMPの違いを日常の例に置き換えて理解を深めるといいでしょう。例えば、新しいアプリを作るとき、最初の版で使い勝手を検証してから、実際にお金を払ってもらえる価値へと調整していくイメージです。





















