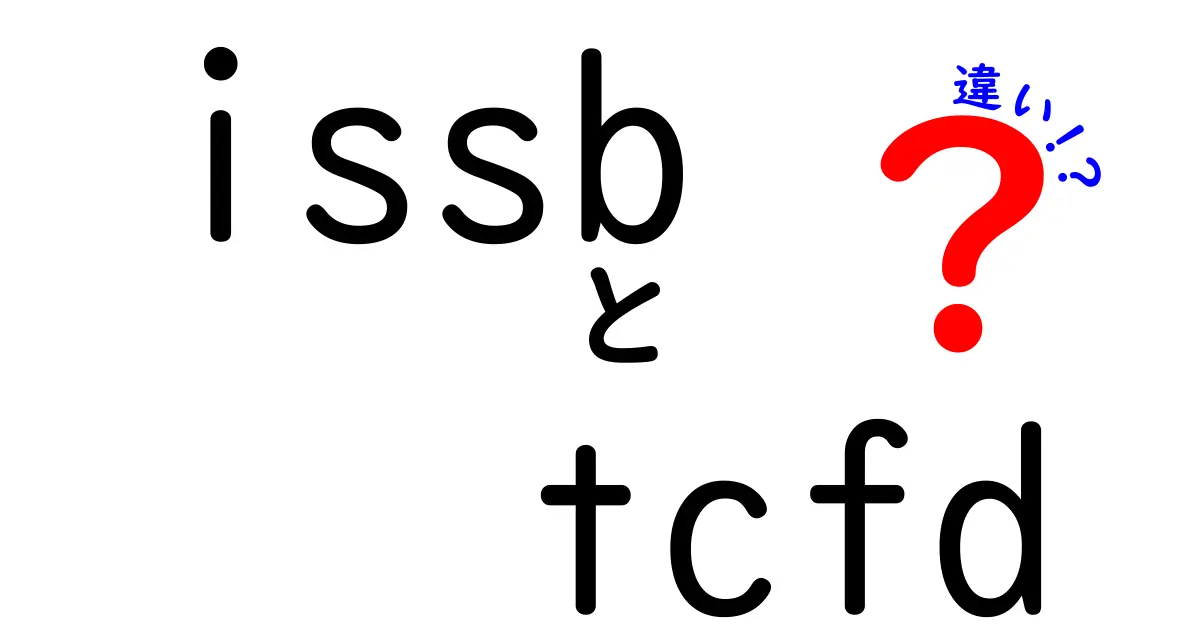

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ISSBとTCFDの違いを理解する
現在、企業が開示する環境・社会・ガバナンス情報のルールは世界で複数存在し、時には混乱を招くこともあります。そんな中、ISSBとTCFDはとても重要な役割を果たす枠組みです。ISSBはIFRS財団が作る『国際的な持続可能性情報の開示基準』であり、主に企業の財務的価値に直結する情報を標準化します。TCFDは2015年に設立された気候関連財務情報開示タスクフォースで、気候リスクと機会についての開示を推奨します。これらは同じ目的を持ちながら、焦点の置き方と実務の手触りが少し異なります。ISSBはグローバルな基準を作り、重視するのは「投資家が企業の将来性を判断する材料」としての情報です。TCFDは気候変動による財務リスクの理解を深めることを最初に置き、企業の戦略・ガバナンス・リスク管理・指標と目標の4つの柱を軸にしています。これにより、企業は長期的な視点での適応や対応策を具体化しやすくなります。
この二つの枠組みの関係を理解する鍵は、情報の粒度と適用範囲の違いです。ISSBは「幅広いESG情報を統合して、投資判断に直接役立つ形で提供する」ことを目指します。その一方でTCFDは「気候という特定のリスクにフォーカスし、財務への影響を定量的・定性的に説明する」ことを重視します。つまりTCFDはISSBが作る土台の一部として機能することが多く、両者は補完関係に近いと考えるのが自然です。
この説明だけで完結ではなく、実務上の違いも押さえておくと良いでしょう。ISSBの基準はIFRS財団の長期的な統一性を背景に、国や企業の規模を問わず適用しやすい性格を持ちます。対してTCFDは既存の企業開示と組み合わせて使われることが多く、特に金融機関や規制機関が求める気候リスクの開示様式として強い影響力を持っています。総じて言えるのは、ISSBは「より広範な情報の統合的な開示基盤」、TCFDは「気候関連リスクの理解と伝達のための実務ガイドライン」という二つの役割を果たしている点です。
日常の実務での差: 企業と投資家の視点
企業と投資家の立場から見ると、ISSBとTCFDの差は実務の手順と情報の粒度に現れます。ISSBはグローバルな基準を提供することで、企業がどこに何を開示すべきかの全体像を簡潔に示してくれます。これにより、複数地域の法規制に対応する負担が軽減され、S1・S2のような具体的な開示項目が整理されやすくなります。TCFDは、気候リスクに特化した情報の質を高めるための実務指針を提供します。たとえばガバナンスの仕組み、戦略の方向性、リスク管理の方法、指標と目標の設定と追跡など、投資家が「どの程度の情報量と品質で判断材料を得られるか」を決める要素が詳しく示されています。
実務上の使い分けとしては、まずISSBの枠組みを土台に置き、TCFDの視点を用いて気候リスクの項目を厚くする、という順序が自然です。具体的には、S1・S2の開示項目を満たすためのデータを整備しつつ、TCFDの四つの柱から得られる質問項目を追加する形です。これにより、外部の投資家や金融機関が比較しやすく、理解しやすい報告になります。規制や市場の動向を踏まえて、どの地域で、どの時点で、どの程度の深度で開示を拡充するかを計画的に決めることが大切です。
また、効果的な報告のコツとしては、要点を絞り、図表や要約を活用して情報の可読性を高めることです。文章だけでは伝わりにくい数値や指標を、箇条書きと簡潔な説明で補足すると、読み手にとって理解しやすくなります。
放課後、友人と ISSB の話題をしていて、ISSBはグローバルな統一基準を作ろうとする点に注目していた。TCFDは気候リスクの実務ガイドラインだと理解していて、二つは補完関係にあると話し合った。私は、ISSBがベースを整え、TCFDがその上で具体的なリスクの深掘りをする形が、企業の現場には最も使いやすいと感じた。
次の記事: sasbとssbjの違いを徹底解説!どっちを使うべき?最新ガイド »





















