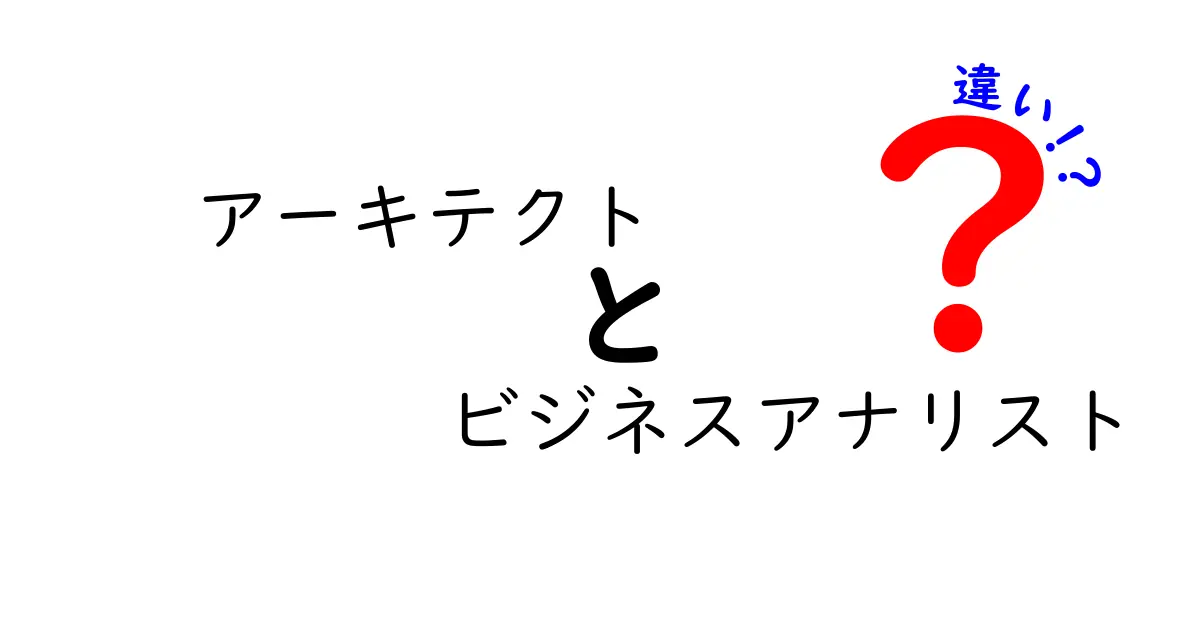

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
アーキテクトとは何か?
アーキテクトはシステムやサービスの骨格を設計する専門家です。彼らは全体の構造を俯瞰し、どの部品がどう連携するかを長期的な視点で決めます。目的は機能だけでなく性能・信頼性・拡張性・保守性といった非機能要件をも満たす「堅牢な設計」を作ることです。現場では要件を集めるだけでなく、将来の変化にも耐えられる設計を描くことが求められます。技術選択、データの流れ、APIの境界、クラウドの利用方針、セキュリティの考慮など、複数の要素を統合して大きな絵を完成させるのがアーキテクトの役割です。
また、アーキテクトは開発チームだけでなく運用・セキュリティ・経営といった他部門との対話も多く、意思決定のガイド役としての役割を果たします。現場の現実と技術の可能性を結びつける橋渡しとして、「何を作るか」と同様に「どう作るか」を明確にします。こうした視点は新規プロジェクトの立ち上げ時だけでなく、既存システムのリファクタリングや技術的負債の解消にも活きます。
総じて、アーキテクトはシステムの将来像を描く先を見据えた職種であり、現場の技術者の羅針盤となる存在です。
アーキテクトの主な役割と現場の動き
現場での具体的な動きは次のようになります。まず要件の上流で技術的な可能性を評価し、次に全体像の設計図を描く、そして実際の開発フェーズでは設計通りに実装されているかを監視します。これには以下のような活動が含まれます。
・技術選択と標準の決定
・データモデリングとデータ整合性の確保
・モジュール間の境界と責任の割り当て
・非機能要件の測定方法と監視設計
・リスクの事前洗い出しと対策の立案
・複数部門との意思決定の調整と合意形成
このような作業を通じて、技術的な実現性とビジネス上の価値の両方をバランスさせることが求められます。現場ではしばしば「作るべきものの品質をどのように保証するか」という問いに直面します。そこでアーキテクトは、標準化された設計パターン、再利用性の高い部品の定義、そして将来の変更を容易にするアーキテクチャの分解を重要視します。
このセクションのポイントは、技術的視点と戦略的視点の両方を持つことです。技術の最新動向を踏まえつつ、ビジネスの目的や制約を忘れずに設計の舵を取るのがアーキテクトの本質です。
ビジネスアナリストとは何か?
ビジネスアナリスト(BA)は組織のビジネス課題を理解し、解決のための要件を整理・具体化する役割を担います。彼らの主な任務は、関係者と話をして現状の課題や機会を洗い出し、それを実現可能な形に翻訳することです。BAは「何を達成したいのか」「どの業務プロセスをどう改善するのか」「どの機能が最も価値を生むのか」を見極め、要件定義書やユーザーストーリー、業務フロー図、価値検証のためのKPI設定などの成果物を作成します。現場では利害関係者の期待を調整し、予算・スケジュール・リスクを踏まえた現実的な解決策を提案します。
BAは技術者とビジネスの橋渡し役として、技術の専門用語を平易に説明し、現場の声を技術チームに伝える重要な窓口です。要件の優先順位を決める際には、価値とリスクを両方考慮し、短期の成果と長期の成長を両立させる判断を求められます。こうした作業を通じて、ビジネスの目的を明確にし、成果物を現実の開発計画に落とし込むことがBAの役割です。
ビジネスアナリストの強みとスキルセット
ビジネスアナリストはコミュニケーション能力と分析力が最も重要な武器です。関係者の意図を正確に読み取り、複雑なビジネスプロセスを分解してわかりやすい要件に変換します。さらに、業務プロセスの可視化、データの意味を読み解く力、利益と費用の比較、リスクの評価と対応策の提案といったスキルも求められます。現場ではアジャイルやウォーターフォールなど開発手法の違いを理解し、適切な要件管理の方法を選択する判断力が必要です。BAはしばしば新しいビジネスモデルの検討にも関与し、価値創出の観点での提案を行います。こうした幅広い視点が、組織の成長を支える大切な力になります。
アーキテクトとビジネスアナリストの違いと使い分け
両者の違いは使命の焦点と成果物に現れます。アーキテクトは技術の全体像を描き、将来の変化にも耐える設計を作るのが役割です。成果物は主にシステムアーキテクチャ図・技術選択の基準・非機能要件の設計方針など、技術寄りの文書や設計資料になります。対してビジネスアナリストは“ビジネスの価値”を前提に要件を整理し、現場の課題を解決するための機能要件や業務プロセスの改善案を作成します。成果物は要件定義書・ユーザーストーリー・業務フロー図・検証用のKPIなど、ビジネス寄りの文書が中心です。 この表から分かるように、両者は別々の視点を持ちながらも、最終的には同じ目標=「ビジネスの価値を最大化するシステムづくり」に向かっています。 最近、学校の課題で新しいアプリのアイデアを考えたとき、友達が“設計がいい人と要件を作る人で役割が分かれているのが分かりづらい”と言いました。確かに似ている部分も多いですが、深く掘ると全体像を作る人と価値を形にする人の違いが見えてきます。アーキテクトは“どう作るか”を、ビジネスアナリストは“何を作るか”を決める。二つの視点を同時に持つと、難しいプロジェクトでも迷わず進めそうです。
この二つは互いに補完関係にあり、実務では両者が協力してプロジェクトを成功へ導くことが多いです。例えば新しいシステムを導入する際にはBAがビジネス上の要件を固め、アーキテクトがその要件を技術的に実現する最適な設計を描く、という流れが一般的です。
下表は両者の役割を端的に比較したものです。項目 アーキテクト ビジネスアナリスト 焦点 技術的設計と全体構造 ビジネス価値と要件の明確化 成果物 システムアーキテクチャ図、技術選択基準、非機能要件設計 要件定義書、ユーザーストーリー、業務フロー図 主な関係者 開発チーム、運用、セキュリティ、経営 経営層、現場部門、開発チーム 成功指標 性能・拡張性・保守性の達成 業務改善の成果、ROI、満足度
現場では、両方の役割を理解し、適切に協力することがプロジェクトの成功に直結します。もしあなたが新しいプロジェクトを任されたら、まずビジネスの要件を固めるBAの視点と、技術的設計を描くアーキテクトの視点を同時に取り入れることを意識すると良いでしょう。
最後に、現場の実務では役割が組織の規模や文化、プロジェクトの性質によって若干変化します。中小企業では一人が両方の役割を担うことも珍しくありません。一方で大企業では専門性が高く、明確に分業されます。どちらのパターンでも大切なのは、ビジネス価値を最優先に、適切な技術設計と要件設計を結びつけることです。これを意識すれば、アーキテクトとビジネスアナリストの違いは自然と理解できるはずです。
ITの人気記事
新着記事
ITの関連記事





















