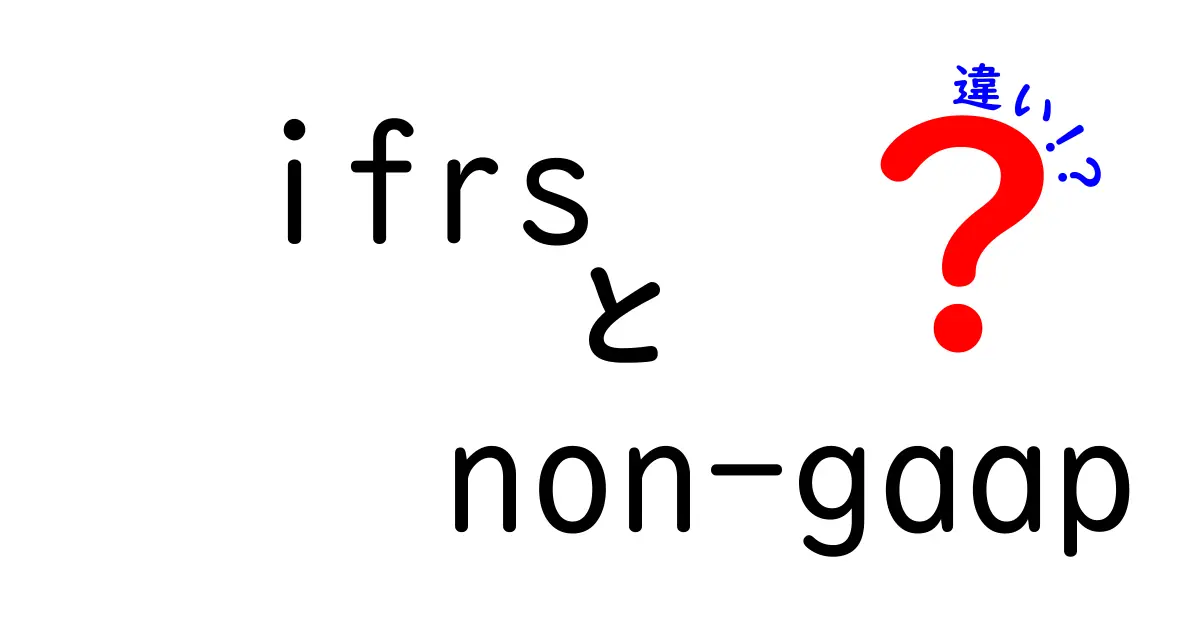

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
IFRSとNon-GAAPの違いを徹底解説!中学生にもわかる財務の基礎
はじめに、IFRSとNon-GAAPの基本を押さえよう。ここでは、会計の世界でよく出てくる IFRS と Non-GAAP という言葉が指す意味を、日常の例えを使ってやさしく説明します。まず、IFRSとは国際財務報告基準のことで、世界の多くの国がこの基準を採用していますが、ユニークな例外や解釈の違いがまだ残っています。これを理解するには、財務諸表の主要な目的を押さえることが大切です。財務諸表は「企業の経済活動の結果を外部の読者へ伝える道具」であり、投資家や銀行、従業員などがその企業は現状どうなのか、将来どのくらいの利益を出せるのかを判断する材料です。IFRSはこの伝えるための基準で、どの科目をどう分類し、どの金額をどの換算で表示するかを統一的に決めています。
しかし、Non-GAAPは企業が自分たちの業績を伝えるための数字の作り方です。例えば、ある企業が利益を高く見せたい時に、費用の一部を特別な項目として別枠に置くことがあります。このような処理はIFRSの厳格な基準には必ずしも従いません。
ですので、IFRSとNon-GAAPを混同すると、外部の人が本当の利益はどれくらいなのかを誤解してしまうことがあります。
IFRSとNon-GAAPの基本を学ぶポイント
IFRSとNon-GAAPの違いを正しく理解するためには、まず用語の意味をはっきりさせることが大切です。IFRSは「正式な会計ルールの集合体」であり、企業はこのルールに従って決算書を作成します。対してNon-GAAPは「公式なルールに従っていない指標」が含まれる場合が多く、企業が自分の経営状況を説明するための補足説明として提示されます。例えばEBITDAは、営業利益だけでなく減価償却などの非現金費用を除外する指標です。これが良い面も悪い面もあります。良い点は、投資家にとって経営の本質を見やすくすること。悪い点は、解釈次第で過大評価につながる可能性があることです。だから企業はNon-GAAPの開示を行うとき、必ず開示要件を守り、IFRSに基づく数字と併せて公表して、読者が正しく比較できるように配慮します。
ここまでをまとめると、IFRSは“統一された世界基準”、Non-GAAPは“表現の自由度が高い補足指標”と考えると、関係性がつかみやすくなります。中学生でも、実際の決算を読むときにはIFRSの数字を軸にしつつ、Non-GAAPの数値がどう作られているかを確認する癖をつけると良いでしょう。
表で分かる違いの要点
以下の表は、IFRSとNon-GAAPの違いを要点だけ整理したものです。表を見れば、何がどのように違うのかが一目で分かります。表の実務的な読み方のコツは、必ずIFRSの定義と非GAAPの開示の意図を分けて考えることです。この理解を基に、決算を読み解く力を少しずつ身につけていきましょう。
ここまでを読んでくれてありがとう。次に、実務での読み方のコツをさらに深掘りします。
実務での注意点と混乱回避のヒント
実務での注意点は多数あります。まず財務諸表の開示要件を守ること。開示の透明性を保つためには、IFRSに基づく元データとNon-GAAPの調整項目の両方を分かりやすく説明することが重要です。さらに、比較可能性を高めるためには、過去期のNon-GAAP数値も同じ基準で計算されているかを確認する必要があります。したがって、会社の財務担当者はIFRSの原則を理解した上で、Non-GAAP側の調整の理由と方法を明確に開示します。
加えて、情報の受け手である読者の視点も考慮します。投資家は数字の背景を知りたがるので、なぜこの項目をこのように設定したのかを簡潔に説明することが大切です。たとえばEBITDAのような指標は魅力的に見える一方、減価償却や一時的な費用を除くことで実態が薄れることもあります。そこで、IFRSの純利益とNon-GAAPの調整後利益の差異を一緒に並べて示すと、読者は実態をつかみやすくなります。これらの点を踏まえ、誤解を生まない表現を心がけましょう。
- 比較情報を同じ期間で提示する
- IFRSとNon-GAAPの定義を併記する
- 数値の出所と計算方法を明記する
最後に、実務で学んだことを日常のニュースで観察してみましょう。未知の専門用語が出てきた時には、まず基準の定義を確認し、どの数値がIFRSベースか、どの数値が非公認の補足かを区別する癖をつけると、財務ニュースの理解が格段に深まります。
Non-GAAPは会社が自分の業績をよりよく見せたいときに使う“見せ方の工夫”みたいなものだよ。でも、どんな時に使われるのか、どんな場面で真実が見えにくくなるのかを知ることが大切。例えばEBITDAを強調するとき、減価償却や一時費用を除くことで実際の現金の動きが薄れることがある。だから投資家は“この指標がどの部分を反映しているか”を必ず確認する必要がある。IFRSの数字とNon-GAAPの調整後数字をセットで見る癖をつければ、企業の本当の実力が見えてくる。
次の記事: 法定開示と適時開示の違いを徹底解説|初心者にもわかる実務ガイド »





















