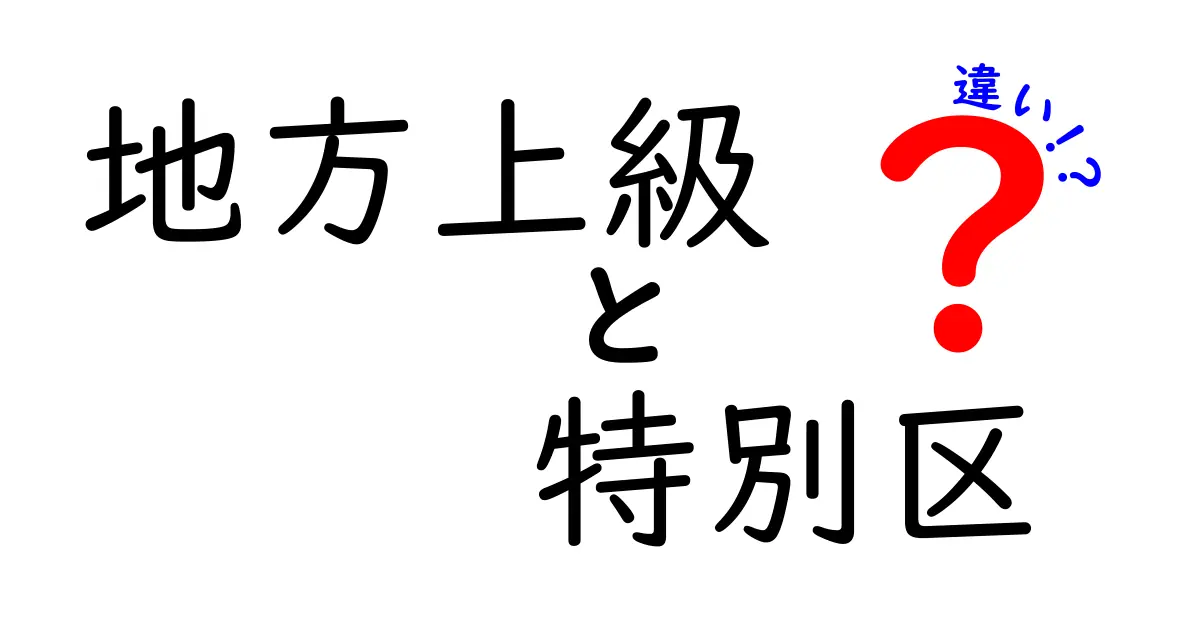

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
地方上級と特別区の違いとは?
<地方上級試験と特別区試験は、どちらも地方自治体の職員を目指す人にとって大切な国家公務員や地方公務員の試験です。
地方上級は都道府県や政令指定都市の幹部候補者を対象とした公務員試験であるのに対し、特別区は東京都23区の職員を採用するための地方公務員試験です。
この違いは、働く場所と仕事内容の違いに繋がっています。
今回は「地方上級と特別区の違い」についてわかりやすく解説していきましょう。
試験の特徴と求められる能力の違い
<まず試験内容を比較してみましょう。
地方上級試験では、一般的に教養試験や専門試験があり、幅広い知識や高度な専門知識を問われます。
特別区試験は地方上級よりはやや範囲が狭いことが多く、面接重視の傾向もあります。
どちらも公務員として必要な社会常識や法律、行政に関する知識は必須ですが、地方上級はマネジメント力や企画立案能力も求められます。
下の表に主な違いをまとめました。
| 項目 | <地方上級 | <特別区 | <
|---|---|---|
| 対象自治体 | <都道府県、政令指定都市 | <東京都23区 | <
| 試験内容 | <教養試験+専門試験(高度な内容も) | <教養試験中心+面接重視 | <
| 求められる能力 | <企画力、調整力、政策立案能力 | <実務遂行力、地域密着対応力 | <
| 仕事内容 | <幅広い政策立案や行政管理 | <区民サービスの提供、地域行政 | <





















