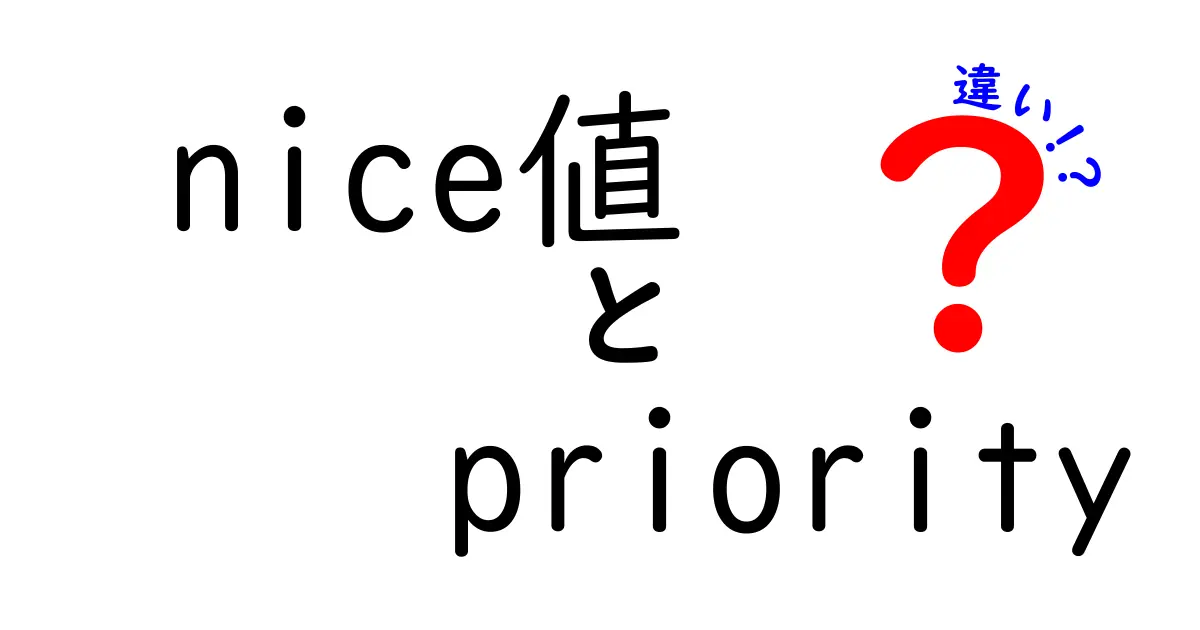

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
nice値とpriorityの違いをわかりやすく解説
近頃、わたしたちはパソコンがどのくらい速く動くかを決める設定をよく耳にします。その中でも「nice値」と「priority」は、CPUの使われ方を左右する重要な仕組みです。しかし、具体的にどう違うのか、どんな場面で使うのかは分かりにくいことが多いです。この記事では、中学生でも理解できるように、日常の例えを交えつつ、nice値とpriorityの基本的な考え方と、実務での使い方を丁寧に解説します。読み終わる頃には、どちらをどう使えば良いかが自然に見えてくるはずです。
まずは前提として、現代の多くのOSは同時に複数の作業を行います。CPUは限られているため、OSは「誰が次にCPUを使えるか」を決めるルールを用意しています。そのルールの中でも、nice値とpriorityは特に大切な指標です。nice値は人が決める値で、priorityはOSが内部的に管理する順位付けの仕組みです。これらがどう組み合わさって「どのプロセスがどのくらい優先されるか」を決めるのかを、具体的なコマンド例とともに見ていきましょう。
この章を読んだ後には、nice値とpriorityの基本的な違いが理解でき、日常のパソコン操作やサーバ運用の現場での活用イメージがつくようになります。次の章では、それぞれの仕組みの具体的な動きと、実際の使い方を詳しく見ていきます。
1) 仕組みを知ろう
この章では、背景となる仕組みを噛み砕いていきます。
OSは、同時に走る複数のプログラム(これを「プロセス」と呼びます)を管理します。CPUは限られているので、すべてのプロセスに一斉に同時に処理を与えることはできません。そこでOSは「次に誰にCPUを渡すか」を決めるルールを設けます。その中で、nice値とpriorityは「どのプロセスを優先して動かすか」を決める大事な指標です。
nice値は人が直接決める値で、通常 -20 から 19 の範囲をとります。値が小さいほど「このプロセスを優先して動かしてよい」という意味合いが強くなり、CPU時間の割り当てが多くなります。デフォルトは 0 で、特定のプログラムを優先したいときにはこの値を調整します。
priorityはOSの内部で使われる「優先順位」のことです。リアルタイム系のスケジューリング(SCHED_FIFO、SCHED_RR)では 1 から 99 までの固定値が割り当てられ、数値が高いほど優先度が高くなります。通常のタスク(SCHED_OTHER)では、priorityは内部的に動く数値で、実質的には niceness の影響を受けつつ、OSが動作の安定を保つように調整されます。
つまり、nice値は「人が設定する調整用の指針」であり、priorityは「OSが内部で使う実際の順位付けの仕組み」なのです。ここが二つの違いの本質です。これを押さえると、どう使い分ければ良いかが見えてきます。
2) どう使うのか
実務では、まず nice 値を使ってプログラムの動作を穏やかに変えるのが基本です。
新しくプログラムを起動するときには、nice コマンドの -n オプションで niceness を指定します。たとえば、下記のように実行すると、通常より少し遅く動作させることができます。
例: nice -n 5 ./my_program は、同じプログラムでも他のタスクより CPU の割り当てが少し控えめになります。バックグラウンドで動かす処理を穏やかにすることで、前景で動く人の作業を邪魔しにくくします。
すでに動いているプロセスのnicenessを変えたいときには renice を使います。例: renice -n -5 1234 は、PID 1234 のプロセスをより高い優先度で動かすようにします。-5 のように負の値を指定すると優先度が上がり、+5 なら下がります。
現在の割り当てを確認したいときには top や ps コマンドが役立ちます。たとえば、ps -eo pid,ni,pri,cmd --sort=-pri とすれば、niceness と priority の関係を同時に見ることができます。こうして状況に合わせて段階的に調整していくのが基本です。
注意点として、リアルタイムスケジューリング(SCHED_FIFO・SCHED_RR)はとても強力ですが、誤用すると他の作業を妨げる原因になります。日常的な用途では SCHED_OTHER を使い続け、nice 値でバランスを取るのが安全です。緊急時には一時的に調整する程度に留め、長期的には全体の挙動を観察してから適切な値に落ち着かせると良いでしょう。
3) 生活の中の例え
学校の昼休みの教室を想像すると分かりやすいです。教室には同時に多くの人が話したい状況があり、誰が先に話すかの順番が問題になります。nice値は「話していい順番を決めるルール表」のようなものです。値が小さいほど、前の人に近い順番で話す機会を得られます。一方、priorityは「今この話題を最優先で進める人」の役割です。リアルタイムのイベントでは、特定の話題をすぐ扱えるように、固定された優先順位を持つ人がいます。このような生活感覚の例えを使うと、難しい技術用語も身近なイメージとしてつかみやすくなります。
実際の現場では、nice値を用いて多数のタスクの競合を平準化し、必要な場面だけ priority の高いタスクを優先する、という使い分けが基本となります。これを頭の中に置いておくと、OSの挙動を観察するときにも、どこを調整すればよいかが見えやすくなります。
このように、nice値とpriorityは同じように「CPUの使われ方を決める仕組み」ですが、役割や適用シーンが異なります。使い分けの基本を押さえつつ、実際のコマンドで試してみると、OSの挙動がぐっと身近に感じられるようになります。
今日は友人と雑談する形で deep-dive します。nice値とpriority の違いを、学校の時間割とゲームの人気者の話題を混ぜながら分かりやすく解説します。nice値は“部屋の混雑度を決める温度計”のようなもので、数値が低いほどその人が前に出やすくなります。priorityは“その場の全体ルール”のように、リアルタイム領域では1〜99の固定値で強さが決まります。普段はnice値で調整しますが、特定の重要なタスクにはpriorityが直接力を発揮します。実務での使い方も、コマンド例を交えて雑談形式でゆるく掘り下げます。





















