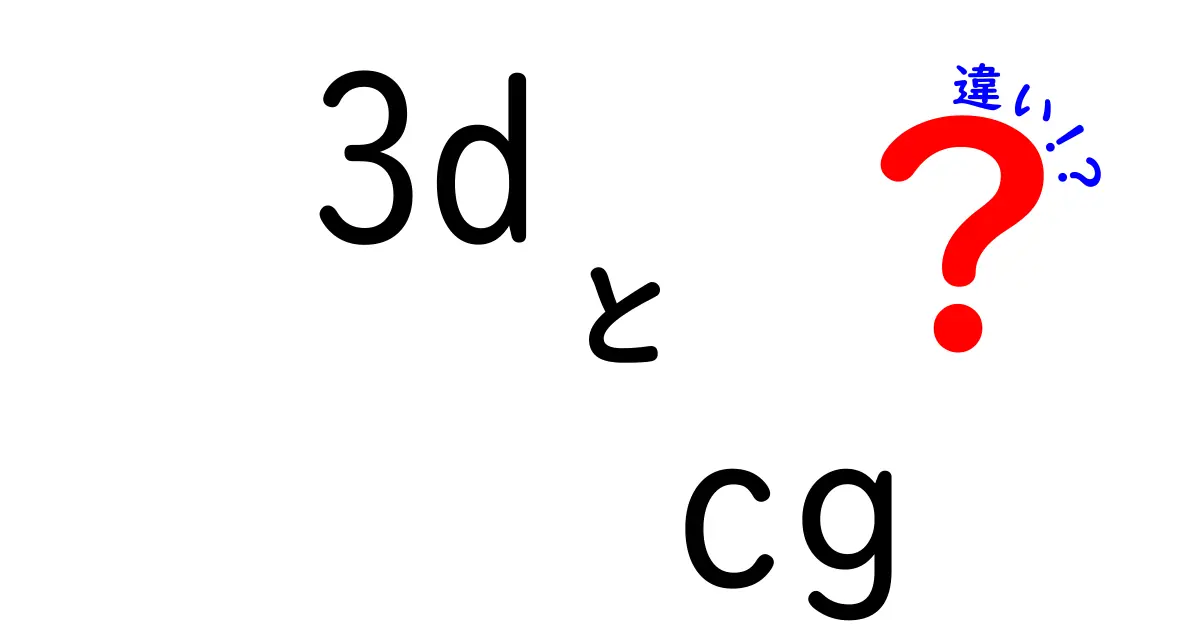

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:3DとCGの混同を解く第一歩
私たちは日常の中で 3D と CG という言葉をよく耳にしますが、二つの言葉が指す意味には微妙な違いがあることを知っていますか。ゲーム、映画、アニメ、広告、VRなど、映像を作る現場ではこの違いを正しく理解することが作品の品質を左右します。
本記事では、3Dと CG の本質的な違いを、初心者にもわかりやすく解説します。まずは基本の定義から確かめ、次に技術的な違い、そして実務での使い分けを順を追って見ていきます。
読み進めるうちに、作品づくりに携わる人はもちろん、これから学習を始めたい人も、どの分野を深掘りすべきかが見えてくるでしょう。
この記事を読めば、3Dと CG の違いが頭の中で整理され、実務や学習の計画が立てやすくなります。難しく感じる専門用語も、言い換えれば“何を作りたいか”という視点で整理できます。
それぞれの用語が指す範囲と、現場での具体的な役割を、身近な例とともに解説していきます。
定義の違いと基本イメージ
まずは、もっとも基本となる定義を押さえましょう。3Dは“三次元の空間”を扱う技術やデータの集合を指します。物体の形、位置、回転、奥行きといった要素を数式と座標で表現します。これに対してCGは“コンピューターで作られた画像全般”を指す広い概念です。
CGには2Dのグラフィックも含まれますし、3Dを使って作る画像も含まれます。要するに、3Dは物体そのものの空間情報を扱う一種の技術、CGはその技術の成果物としての画像や動画全体を指す横断的な言葉です。
この違いを理解しておくと、制作の段取りやツール選択がスムーズになります。
技術と表現の違い:実務の現場感
次に、現場で使われる技術と表現の違いを見ていきましょう。3Dの作業は大きく分けて「モデリング(形を作る)」「テクスチャリング(表面の質感を貼る)」「リギング(動かす準備)」「アニメーション」「ライティング(光を当てる)」「レンダリング(最終画像を作る)」の順で進みます。いずれも空間情報を前提にしており、奥行きや影の落ち方、反射の挙動などが現実に近づくほど難しくなります。一方でCGはこの3Dの成果物を“どう描くか”という観点を含みます。2Dでのポストエフェクト、合成、レンダリング後の編集など、手元のソフトウェアや目的に応じて様々な表現が可能です。
つまり、3Dは立体を生み出す技術領域、CGはその立体を使って作られた最終的な画像や動画の表現全般を指すと捉えるとわかりやすいです。現場ではよく「3Dを作ってからCGで仕上げる」という順序が採られます。
ポリゴン数、レンダリングエンジン、シャドウの質感など、細かなパラメータが作品の見た目を左右します。これらの用語を覚えるだけで、他の人と話すときにも意図が共有しやすくなります。
実務での使い分けと学習のコツ
実務の場面では、学習順序と作業の流れを意識することが大切です。まずは3Dの基礎となるモデリングと簡単なレンダリングを体験してみましょう。
その後、テクスチャやライティング、アニメーションといった“見た目を作る工程”に進むと、作品全体の質感がぐっと上がります。学習のコツとしては、実際の作品を模倣して作る“模写”から始め、徐々にオリジナル要素を追加する方法が効率的です。
また、ソフトウェアの使い分けも重要です。Blenderのように無料で始められるものから、Mayaや Houdiniのようにプロ向けツールへと段階的に触れると、理解が深まります。
実務では、データの互換性、レンダリング時間、制作スケジュールなど、現場の制約も学ぶ必要があります。これらを意識することで、より現実的な作品づくりができるようになります。
よくある誤解と注意点
よくある誤解の一つは、CGを作ることと 3D を作ることを同義と捉える点です。先ほども触れたように、CGは画像表現全般を含む広義の言葉であり、必ずしも3Dであるとは限りません。2DのCGや合成、デジタルペイントもCGの範囲に含まれます。もう一つの誤解は“すべての3Dはもちろんリアルに見えるべきだ”という考えです。現実的な見た目を追求する一方で、演出上の誇張やスタイルを用いることも大切です。
制作現場では、技術の最新動向を追う一方で、作品の目的とターゲットを忘れずに設計することが求められます。新しい機能やツールを追いかけすぎて、肝心の表現やストーリー性がおろそかにならないよう、バランス感覚を養いましょう。
まとめと次の一歩
ここまでで、3Dと CG の基本的な違いと現場での意味合いをつかむことができたはずです。
3Dは立体を作るための基礎技術であり、CGはその技術を活かして描く最終成果物を指す広義の概念です。作品づくりには、モデリング、テクスチャ、ライティング、アニメーション、レンダリングといった工程があり、それぞれの工程がどの役割を担っているかを理解することが大切です。
これから学ぶ人は、まず3Dの基礎を固め、次にCGの表現力を広げる学習計画を立てましょう。実務に近い課題を設定して、段階的に難易度を上げていくのが効果的です。
参考表:3DとCGの違い(簡易比較)
友だちと話している雰囲気で、レンダリングの話を深掘りしてみよう。友だちは"レンダリングって難しいイメージだけど、何をしてるの?"と尋ねる。私はこう答える。「レンダリングは、頭の中の3Dデータを“写真みたいな画像”に変える最後の仕上げ作業だよ。光の当たり方や影の落ち方、表面の質感がどう映るかを、現実の光の挙動をモデル化して再現する作業なんだ。たとえば太陽光が木の葉に作る影の模様や、金属の反射の強さは、レンダリング設定で大きく変わる。だからこそ、技術だけでなく“どのくらいリアルに見せたいか”という演出意図が大切になるんだ。学習初期は“正確さ”よりも“自分の意図を形にする力”を育てると良い。そんな気持ちで、日々の練習を少しずつ積み重ねていこう。





















