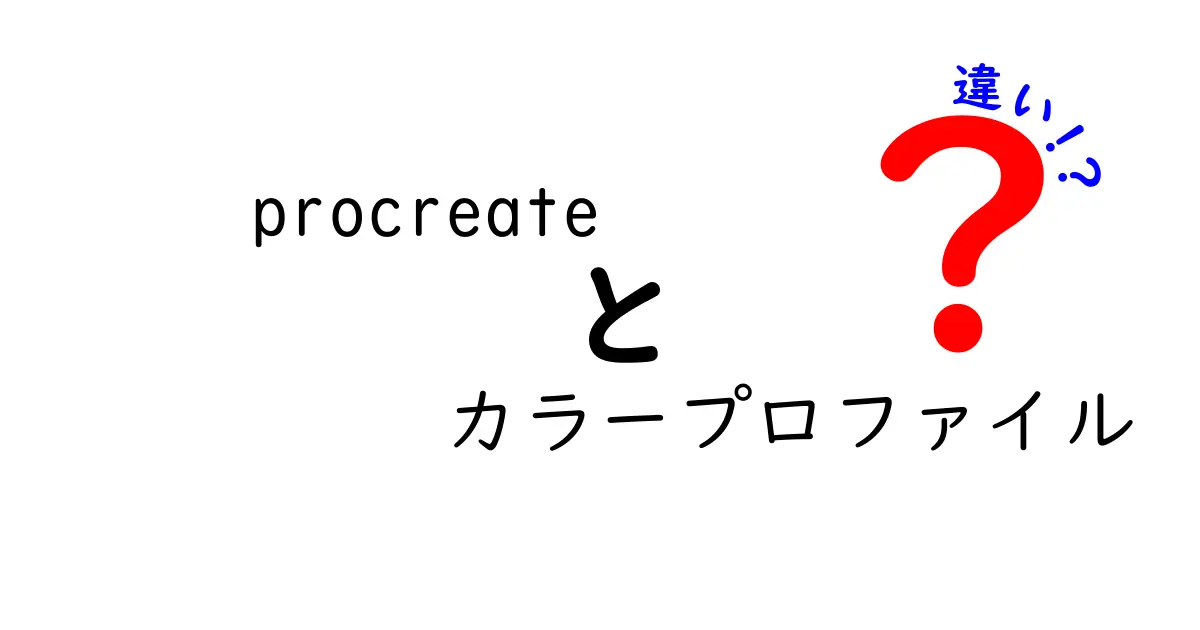

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
Procreateのカラープロファイルとは何か?基本の考え方
Procreateを使ってデジタル絵を描くとき、色の見え方はデバイスごとに微妙に変化します。これを安定させる仕組みがカラープロファイルです。カラープロファイルとは三原色の組み合わせをどのように数値として解釈するかを決めるルールのようなものであり、私たちが目にする色がどの機器でもなるべく同じように再現されるよう調整します。色のズレを減らすには作業開始時に適切なカラープロファイルを選ぶことが大切です。長い目で見れば、作品の最終的な見え方に直接影響します。
Procreateでは作業環境に適したカラースペースを選ぶことができます。代表的なものにはsRGB、Display P3、Adobe RGBなどがあります。それぞれ特徴が異なり、色域が広いほど多くの色を表現できますが、表示機器との相性を考える必要があります。
sRGBはウェブや一般的なモニターで安定して見える標準的な色域です。Display P3はAppleデバイスの広い色域を活かせ、写真や映像の再現性が高い反面古い機器では色が崩れることもあります。
印刷を視野に入れるときにはAdobe RGBのような広色域を選ぶとプリンタでの再現性が高まる場合があります。ただし出力先によって変わるため、最終的には出力先の色空間に合わせて変換する作業が必要です。
作品の行き先を想定してカラープロファイルを決めることが、色の再現性を保つコツです。
実践のガイド:用途別の選び方と注意点
日常の制作シーン別に、どのカラープロファイルを選ぶべきかを考えてみましょう。まずウェブやSNS投稿が主な場合はsRGBを基本にしておくのが安全です。表示機器がsRGBに対応していれば色の崩れが少なく、他の人に色味が近く伝わります。制作中はsRGBで作業しておき、最終出力の段階で別の空間へ変換しておくと便利です。
写真や映像寄りのデータを扱う場合は Display P3 の活用を検討します。広い色域のおかげで微妙なグレーや肌色の表現が豊かになります。ただし、受け手が古いデバイスやソフトを使っていると色味が正しく表示されないリスクもある点は覚えておきましょう。
データを共有するときは相手の環境を確認しつつ、可能なら共通の空間に変換して送るとトラブルを減らせます。
印刷を前提にしたプロジェクトでは Adobe RGB などの広色域を使い、プリンタの特性に合わせてカラー変換を行います。印刷時のカラー管理は専門家に任せる場合もありますが、デザイン段階で出力先を意識しておくと仕上がりが格段に安定します。
変換の際にはガマットのような色味のずれが生じることがあるため、モニターとプリンタの色校正を行い、最終的な検証を必ず行いましょう。
下記の表は三つの代表的なカラー空間の違いを簡単にまとめたものです。これを手掛かりに自分の制作ワークフローを組み立ててください。
実践的なワークフローのコツ
作品を作るときは、最初に使用するカラー空間を決め、各段階で適切に変換する癖をつけましょう。作業中は一貫した空間を保つことが色のズレを減らす鍵です。
完成後は出力先に合わせて最終的な色空間へ変換する作業を行います。変換後は必ずプレビューで確認し、必要に応じて微調整します。
また、友人やクライアントと共同作業をする場合は、使用するカラー空間を事前に共有しておくと、すれ違いが減ります。
ある日、友達とデザイン部の端末を並べてDisplay P3の話をしていた。私たちは同じデータを持っているはずなのに、彼女の画面では肌の色が少しピンク寄りに、私の画面では少しオレンジ寄りに見えた。そこで私が提案したのはこうだ。Display P3を選ぶ理由をひとつずつ説明するだけでなく、データを渡す相手に合わせて最初からsRGBへ変換しておくと、相手の端末で「これが正解の色」という解釈を揃えやすいということ。結局、私たちはウェブ用にはsRGB、印刷の打ち合わせにはAdobe RGBへ仮変換してスクリーンショットを見比べることで、色のズレを減らすことができた。つまり色は設定を共通にすることで大きく変わる。
この小さな工夫が、後の作品の完成度を左右するんだと実感した夕方だった。
前の記事: « gzip tar 違いを徹底解説!初心者にも分かる使い分けのコツ





















