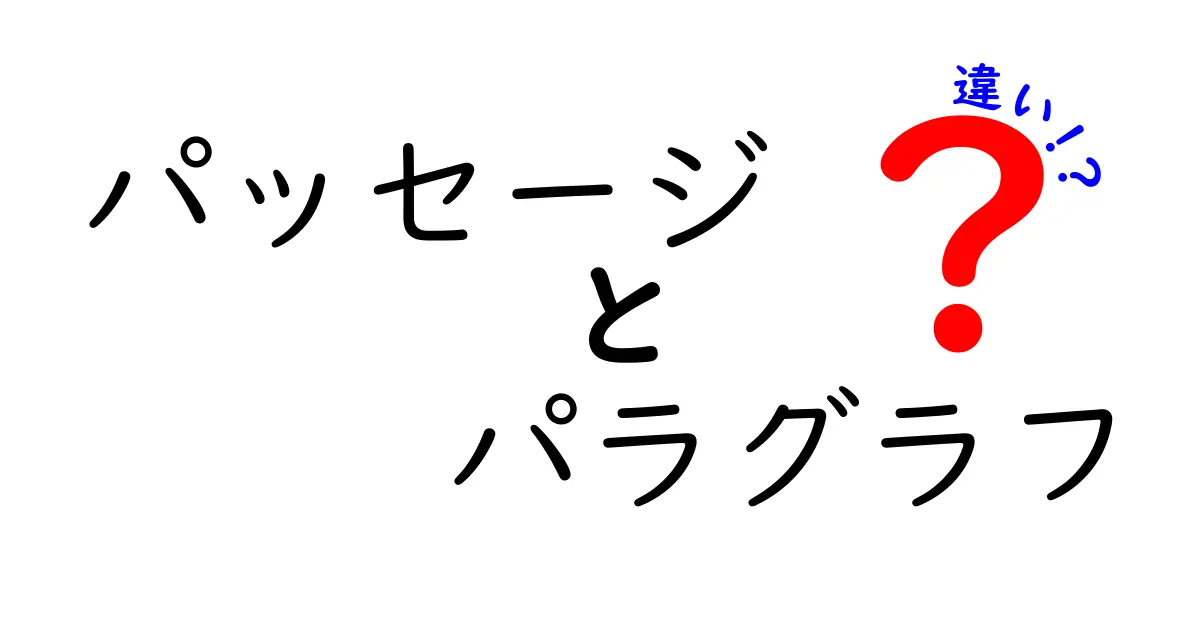

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
パッセージとパラグラフの違いを理解するための総論
「パッセージ」と「パラグラフ」は、似た響きの言葉ですが、日本語の文章の構造を理解するうえで重要な二つの考え方を指します。パッセージは文字通り「 текста の通りの経過」つまりテキストの一部を指す言葉として使われることが多く、長さや文のつながりを含む全体の意味を保ったまま抜き出した部分を指すことが多いです。また、外国語の学習では「読むべき文章の一部」を指す場合もあります。
一方、パラグラフは文章の構造を区切る基本的な単位、つまり段落そのものを指します。日本語教育の現場では、導入・展開・結論といった論旨の流れをコントロールするための「区切り」としての役割が強調されがちです。パラグラフは文の長さや句読点の使い方、文と文をどうつなぐかを通して、読み手に論理的な展開を伝える道具として機能します。
この二語は似た場面で使われますが、焦点が違います。パッセージは「抜粋された文章のかたまり」、パラグラフは「文章の構造をなす最小の区切り」という視点で区別すると混乱が減ります。さらに実務的には、教科書の長いパッセージを理解するために段落ごとに読解を進める、論文の各パラグラフの役割を把握して読み解くといった使い分けがよくあります。この理解を土台にして、実際の読み書きの場面で正確に用語を使い分けられるようにしていきましょう。
読書の現場では、パッセージは教科書の抜粋や長文の一部、文学作品の一節など「切り出された文本」を指すことが多いです。対して、パラグラフは文章の中の論点や話の展開を整理する最小単位で、複数のパラグラフが集まって一つの章や段落構成を作ります。例えば、解説文で「第一のパラグラフは導入、第二のパラグラフは理由、第三のパラグラフは例示」というように、段落ごとに役割が分かれます。
このような理解を深めると、読み方・書き方が格段に分かりやすくなります。今から紹介する定義・使い分け・実例を通して、パッセージとパラグラフの違いを体感してみましょう。
定義と語源の違い
パッセージはフランス語の passage から来ており、日本語では「ある文書の抜粋された部分」や「読み物の一部」を指すことが多いです。教科書や文学作品に出てくる長めの文塊を指すことが一般的で、朗読や読解問題でよく使われます。対するパラグラフは英語の paragraph が語源で、文章の中の「段落」という意味です。段落はひとつの中心的な話題や論点を展開する単位として使われ、導入・展開・結論といった役割を担います。
両者の語源の違いを知っておくと、英語や他言語の教材で見かける「パラグラフ」も理解しやすくなります。日本語の文章でも、段落を分けることで読みやすさや論理の明確さがぐんと上がります。結局のところ、パッセージとパラグラフの違いを意識することで、読むべき場所と、文章全体の構造を正しく捉える訓練になるのです。
日常での使い方と例
日常の読書や作文の場面を例にすると、パッセージはニュース記事の抜粋や教科書の長文の「この部分だけを読む」ときに使われます。たとえば、要約問題では「このパッセージの要点を説明せよ」といった指示が出ます。これに対して、パラグラフは作文の設計図のような役割を果たします。段落ごとに話の流れを分け、読み手に論点を伝えやすくするための“区切り”です。学校の宿題では、あるテーマについて3つのパラグラフを用意して、それぞれの段落で異なる視点を述べる練習をします。
具体的な例として、読解の課題を想定します。教科書の「現代社会の課題」というパッセージを読んだ後、最初のパラグラフで問題提起を説明し、次のパラグラフで解決策を紹介し、最後のパラグラフで自分の意見を述べるといった構成にします。こうすることで、文章の読解と作成が同時に鍛えられます。最後に、抜粋のパッセージを全体の文脈と結びつけて理解を深めることが大切です。
表で見るパッセージとパラグラフの比較
| 要素 | パッセージ | パラグラフ |
|---|---|---|
| 意味の焦点 | 本文の抜粋部分、文脈の一部 | 文章の最小構成単位、話の展開の区切り |
| 目的 | 理解するための抜粋、読解対象 | 論理展開の整理、伝達の補助 |
| 長さと構造 | 長さはさまざま、文脈依存 | 基本的に段落ごとに完結、統一された話題 |
この表は、用語としての整理を視覚的に補助します。言語を学ぶときには、こうした比較表を用いて“違いを言い換えられるか”を練習すると、書くときのミスが減ります。
友達Aと私は放課後、教科書の話題を雑談しながら整理していった。パッセージとパラグラフ、似ているけど違う点があると考えるうちに、Aは『パッセージは抜き出した本文のこと』、私は『パラグラフはその文章の中での話の区切りだ』と気づいた。私たちは実際の例として、ある社会の話題を扱うパッセージを読み、同じ段落ごとにポイントをノートに分解していく練習をした。段落ごとにテーマが変わること、導入・説明・結論の順に話が進むこと、それを意識すると読解が速くなる。結局、パッセージは“何を読んでいるか”を示し、パラグラフは“どう話を組み立てるか”の設計図になる、そんな結論に落ち着いた。





















