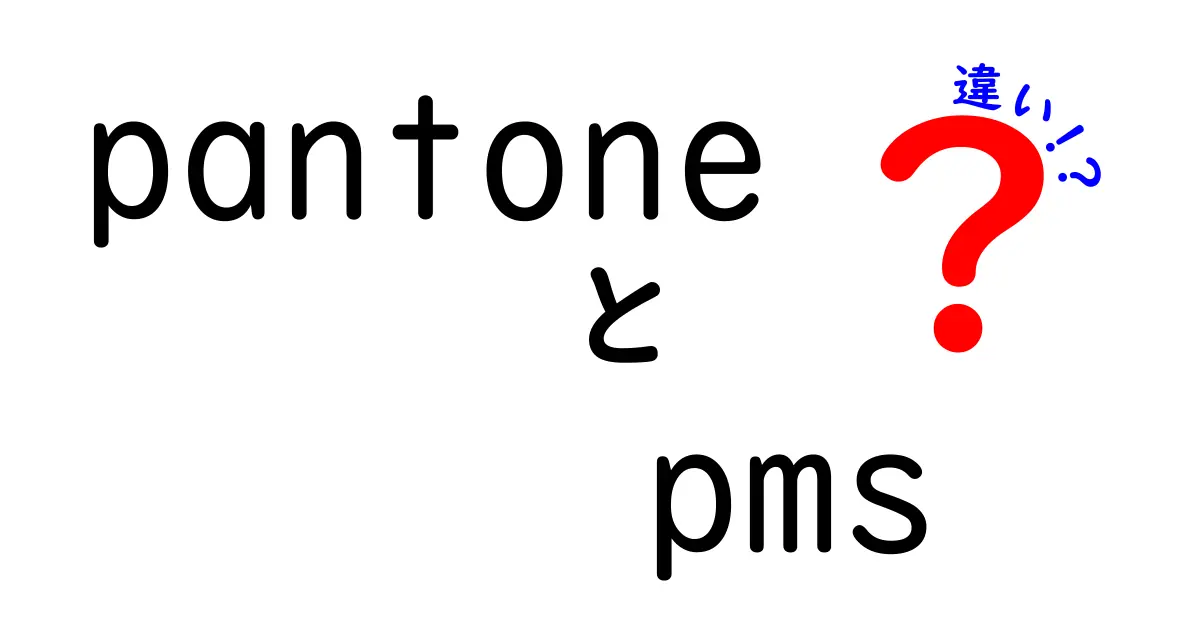

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
PantoneとPMSの違いを理解するための基本理解
Pantoneは色の標準化を目指す会社であり、世界中のデザイナーや印刷業者が共通の色指示を使えるように作られた色見本の体系です。デザインの制作過程では色の見え方が人によって微妙に異なることがありますが Pantoneのカラーは決まった標準値として提供されるため、同じ色を再現しやすくなります。ブランドカラーを一貫して表現することが目的のとき Pantoneは強力な味方です。PMSは実はこの Pantone の色体系を指す略称であり Pantone Matching System の頭文字を取ったものです。PMSのカラー番号を指示すると 印刷現場の担当者は同じ色を再現する信頼性が高くなり、紙の種類や印刷機の個体差があっても近い再現を狙えます。
ただしPantoneという言葉は文脈次第で意味が変わることがあります。場合によっては Pantone 自体のブランド名を指すこともあれば、特定の色見本の集まりを指すこともあります。現場での混乱を避けるためには文脈をよく読み、どの意味で使われているかを確認することが大切です。さらにデジタルデザインの分野では Pantone Connect というアプリやクラウドサービスを使って色を共有するケースも増えています。これらは紙の色見本とデジタル表示の橋渡しをする役割を果たします。慢性的な色のばらつきを抑えるには、事前の校正と適切な参照ファイルの準備が欠かせません。
この章は初学者向けの導入として設計しています。次のセクションで Pantone の特徴と PMS の意味をそれぞれ詳しく見ていくと、なぜ同じ数字が紙とデジタルで異なる印象を持つことがあるのか、そして現場でどう対処すべきかが見えてきます。色の世界は奥が深いですが、基本を押さえればデザインの品質とブランドの統一感を大きく向上させることができます。
Pantoneについて
Pantoneは世界で広く使われる色見本とその番号体系を提供するブランドです。色見本には主に固有の色番号が割り当てられており、設計者はこの番号を指定することで紙の種類や印刷条件が異なる場面でも同じ色を再現できます。Pantoneのカラーには複数のライブラリがあり、代表的なものにはコート紙向けのコートドカラーやマット紙向けのマットカラーなどがあります。実務ではPantone番号の後ろにつく C( coated)や U( uncoated)などの接尾語が印刷条件を示します。Cはコーティング紙、Uは非コーティング紙を指すことが多く、同じ番号でも紙の表面処理が違うと見え方が変わる点に注意が必要です。さらにPantoneは色のデジタル参照としても利用され、画像データやデザインファイルに埋め込まれる場合があります。デザイナーはこの Pantoneカラーをブランドの「公式な色」として管理することで、媒体を超えた一貫性を保てます。
Pantoneは現場での「正確さ」と「再現性」を重視した体系であり、スポットカラーとしての再現を前提としています。スポットカラー means 単一の色を直接印刷する方法であり、CMYKの混色ではなく 1 色だけで再現することが多いです。これにより、印刷機の設定を変えずに特定の色を安定して出すことが可能です。デザイン段階では Pantoneカラーを使ってブランドの核心色を決め、印刷指示書ではその番号とライブラリを併記しておくと、制作の過程での認識違いを減らせます。近年はデジタル印刷やハイブリッド印刷の現場も増え、Pantoneカラーはデモンストレーション用のサンプルとしても重宝されています。
このセクションの要点は次のとおりです。Pantoneはカラーの標準とブランドカラーの統一性を支える体系である。Pantoneの番号は色の「指示書」として機能し、PMSはその指示書を支える「番号体系の呼び名」である。これを理解しておくと、デザイン資料の伝達時に誤解が生じにくくなり、印刷現場でのトラブルを減らす助けになります。
PMSとは何か
PMSは Pantone Matching System の略で、特定の色を番号で表す体系のことを指します。印刷現場では PMS のカラー番号を使って色を指示し、スポットカラーとして固有値を再現します。PMSの特色は「番号で色を正確に伝える」点にあります。これにより、デザイナーはクライアントのブランドカラーをそのまま守ることができ、印刷会社は適切なインクを準備して色を再現できます。
PMSの色は紙の種類や表面加工の影響を受けます。通常はコート紙用の色見本と同様にコーティングの有無で見え方が異なるため、PMSの番号とともにライブラリの種類を表記します。例えば Pantone 185 C は赤系のスポットカラーであり、Cはコート紙を前提にした表現を示します。逆に 185 U のように U がつくと 非コート紙を指すケースが多く、同じ番号でも印刷結果が微妙に変わることがあります。デザイン段階ではこの違いを理解し、最終的な仕上がりを想定して選択することが大切です。
PMSは実務での色指定を簡略化する一方、現場によっては機材やインクの再現性の違いから色味が微妙にずくことがあります。そのため初校時の色校正を必須とし、できれば紙のサンプルとデジタルデータの両方で確認するプロセスを設けると安心です。Pantoneのブランド名と PMS の番号体系を混同せず、用途に応じて使い分けることが求められます。
実務での違いを見極めるポイント
実務では Pantone と PMS の役割を正しく理解することが色の再現性を高める第一歩です。まず印刷の目的がブランドカラーの厳密な再現なのか、それとも写真のような自然な色味の表現を重視するのかを見極めます。ブランドカラーを長期的に統一したい場合は Pantone番号を基準に管理するのが一般的です。一方、コストや納期を重視して CMYK で代用する場面では近似色の検証を行い、必要に応じて補正作業を加えます。特定の色をビジネス上の重要な要素として扱う場合にはスポットカラーの採用を検討し、印刷機の条件に応じてカラーを再現します。
この章では実務上の判断基準をいくつか挙げます。まず色の安定性を求める場合は Pantone のスポットカラーを使い続けると良いです。次に多色刷りや品質管理の観点からはPMS番号を複数の印刷機で共有することが有効です。紙質が変わる場合には事前に現物サンプルの検証を行い、色のばらつきを抑える努力をします。デジタルと紙の連携をスムーズにするには Pantone Connect などのツールを活用して、デザインデータと印刷現場の間でカラー情報を正確に伝えることが重要です。
昨日友達とカフェで色の話をしていたとき Pantone と PMS の違いについて盛り上がった。彼はどちらも同じ色を指してるのにどう違うのか混乱していた。僕はこう説明した。Pantone は色のブランド名とその色見本の総称であり、PMS は Pantone Matching System の略で特定の色を番号で表す体系だ。印刷現場では PMS の番号を指示して同じ色を再現しやすい。一方 Pantone という名前自体はブランド管理やデジタル参照にも使われ、デザイナーは公式のカラーとして管理する。要は PMS は色を伝える“番号”、Pantone はその番号を含む“体系とブランド”の両方を指すという理解で十分だ。これを覚えるだけで、資料の伝達時に色の認識ずれを減らせる気がする。
次の記事: ビビッドカラーと原色の違いを理解してデザイン力を上げよう »





















