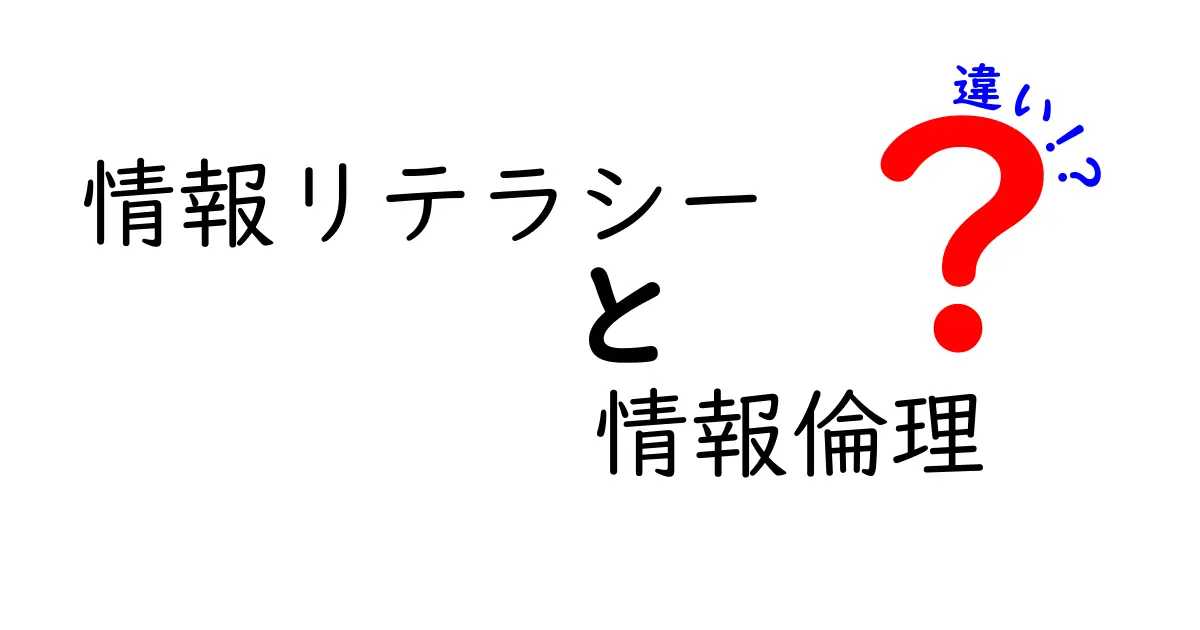

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
情報リテラシーと情報倫理の違いを正しく理解するための出発点
情報リテラシーと情報倫理は、現代のネット社会を生きる上での「基本の考え方」です。この二つは似ているようで、役割や意味するところが違います。まず、情報リテラシーは「情報を探し、見極め、適切に活用する力」を指します。学校の調べ学習や課題作成、友人との情報共有など、さまざまな場面で使われる力です。情報リテラシーを高めると、信頼できる情報とそうでない情報の違いを自分で判断できるようになり、根拠となるデータを探す力、出典を確認する力、複数の情報源を比べて結論を作る力が鍛えられます。
正しい情報の取り扱い方を身につけることは、学習の質を高めるだけでなく、社会で通用する「情報の使い手」になる第一歩です。
一方、情報倫理は「情報を扱うときの正しい判断と責任」を指します。人の権利を尊重し、偏見の拡散を防ぎ、誤情報を広めないよう配慮するなど、発信者・受け手・情報源の三方が公正に向き合うためのルールです。
たとえば、著作物を勝手に使わない、写真や文章の出典を明記する、個人情報をむやみに公開しない、他人を傷つける発言を避ける、などの行動が含まれます。
情報倫理は、私たち自身の信頼性を守り、社会全体の情報環境を健全に保つ力です。
情報リテラシーと情報倫理の比較表
倫理は情報の使い方における倫理的判断と責任の遵守。
他者への影響と法的・社会的規範。
プライバシー、著作権、虚偽情報の回避。
この二つは互いに補完的です。情報リテラシーだけが高くても、倫理的な配慮がなければ情報は社会的に有害になることがあります。反対に、倫理だけを重視して情報を盲信してしまえば、創造的で質の高い情報を生み出す機会を逃してしまいます。理想的には、情報を正しく扱う技術と、正しく扱う姿勢を両方育てることです。日常生活の中で見かけるニュースやSNSの投稿を例に、誰が、どんな情報を、どのような目的で伝えているのかを意識する癖をつけると良いでしょう。
情報リテラシーとは何か:情報を使いこなす力
情報リテラシーは単なる検索能力ではなく、情報を批判的に読み解く力を含みます。たとえば、ニュースを見たときに「誰が書いたのか」「どの情報源を根拠にしているのか」「統計データは信頼できるか」を順番に考える癖をつくることが大切です。
この力が身についていると、SNSの投稿や広告の裏側にある意図を読み取ることができ、間違った情報を受け取るリスクを減らせます。
また、複数の情報源を検討することで自分の結論に偏りが生まれにくくなり、論理的な思考の訓練にもなります。情報をただ受け取るのではなく、質問を立て、検証していく姿勢が求められます。
さらに、現代の学習や仕事ではデータの扱い方が問われます。信頼できるデータをどう拾い、どう整理し、どう伝えるかを意識することが、将来の進路選択にも影響を与えます。結局のところ、情報リテラシーとは「情報を正しく評価し、的確に活用する力を日常の行動に落とし込む能力」です。
情報倫理とは何か:正しい判断と責任
情報倫理は、情報を扱う人としての倫理観や責任感を育てる考え方です。個人のプライバシーを守ること、著作権を尊重すること、データを扱うときの公正さを保つこと、偏見や差別を助長する表現を避けることなど、さまざまなルールが含まれます。
現代のネット環境では、発言や投稿が瞬時に広がる特性上、誤情報の拡散を防ぐ責任が特に重くなります。自分が情報を発信するときには、発信の目的は何か、受け手にどんな影響があるかを考え、出典を明示する、必要であれば訂正する、という姿勢が求められます。
また、他人の創作物を無断で使わないこと、個人情報を軽率に扱わないこと、データの扱い方にガイドラインを設けて守ることが、社会全体の信頼を育む礎になります。情報倫理は人と情報の関係をより健全に保つ重要なルールであり、自分自身の発信が社会に与える影響を自覚する力を培います。
違いを日常でどう実践するか:実例と練習
日常生活での実践には、まず小さな時点から始めることが有効です。たとえば、ニュースサイトの記事を読むときには「著者名と出典が明記されているか」「データの出典はどの組織か」「同じ話題を扱う別の情報源と比較して矛盾がないか」を確認しましょう。次に、他人の作品を使うときは著作権表示を確認し、出典を正確に記す練習をします。SNSでは、情報を共有する前に「この情報は誰にとって有益か」「偽情報の可能性があるか」を一呼吸置いて判断し、必要なら事実関係を調べてから拡散します。
学校の課題では、引用のルールを守るだけでなく、情報源の複数性を意識して比較検討する習慣をつけましょう。さらに、プライバシーを守るための設定を見直したり、知らない人から来たリンクを安易に開かないといった基本行動も大切です。こうした実践を繰り返すことで、情報を自分の意志で選び、適切に利用する力と、他者へ影響を与える行動に対する責任感の両方が育っていきます。最終的には、情報を扱う自分の行動が周囲にどう響くかを自覚する習慣が身につくのです。
友達A: ねえ、最近SNSである投稿を見たんだけど、出典が書いてなくてちょっと怪しかったんだ。
友達B: そういうときはまず“誰が書いた情報か”を確かめるといいよ。出典があるか、別の信頼できる情報源はあるかを探すんだ。
友達A: なるほど。あと著作権のことも気になってきた。勝手に誰かの画像を使うのはダメだよね?
友達B: その通り。出典を明記するのはもちろん、オリジナル作品を尊重する気持ちが大切。情報倫理はここから始まるんだ。
友達A: じゃあ、私たちが日常でできることは何かな?
友達B: まず、情報を発信する前に一呼吸置く癖をつけること。嘘かもしれない情報を広めない。出典を確認してから拡散する。この小さな積み重ねが、社会全体の信頼につながるんだ。





















