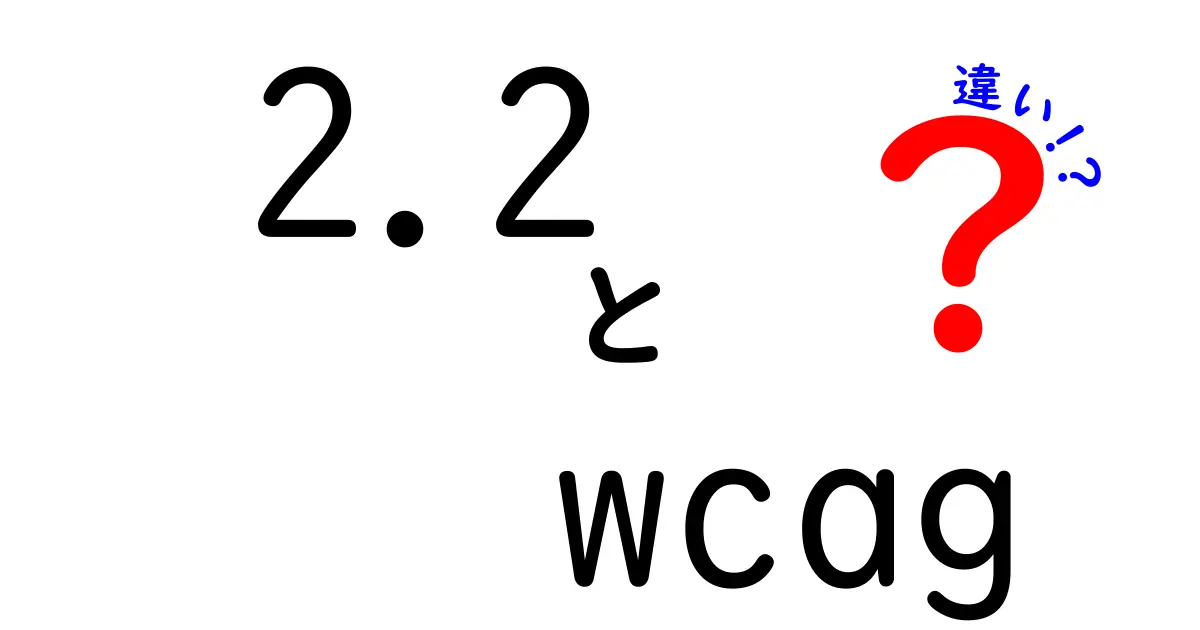

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
2.2とは何か
2.2とは、ウェブアクセシビリティの新しいバージョンで追加された要件のことです。WCAGとはWeb Content Accessibility Guidelinesの略で、障害のある人や高齢者、スマホ小画面の利用者など、さまざまな状況の人が情報にアクセスできるようにするための指針です。2.2は2.1を土台にして、現代のウェブの使われ方に合わせた追加要件を組み込んでいます。
この追加は「従来の基準を壊すもの」ではなく、「足りなかった部分を補う」性質を持ちます。つまり、2.2を満たすと、より多くの人が直感的にサイトを使えるようになるのが狙いです。
具体的には、キーボード操作を行うときのフォーカス表示の可視性の改善、ユーザーが長い手順を踏む場合の時間制限への対応、動的な情報の通知を十分に伝えるための適切な通知手段の提供などが挙げられます。これらは、画面読み上げソフトを使う人、視覚的な変化を過剰に感じる人、スマートフォンやタブレットの小さい画面を使う人、英語などの母語が異なる人にも役立つ具体的な改善です。
結局のところ、2.2は「誰にとっても使いやすい情報提供」を目指す考え方を、より具体的なルールとしてまとめたものです。
2.2と従来のWCAGの違い
従来のWCAGは、使いやすさを4つの原則(知覚可能・操作可能・理解可能・堅牢)でまとめ、その下に達成基準が階層的に並ぶ基本設計でした。2.2はこの土台を維持しつつ、新しい達成基準を追加する形で拡張しています。ここで重要なのは、2.2が「新しい技術」に対応するための柔軟性を持つ点です。たとえば、キーボード操作を行うときのフォーカス表示の可視性の改善、ユーザーが長い手順を踏む場合の時間制限への対応、動的な情報の通知を適切に伝えるための適切な通知手段の提供などが挙げられます。これらは、画面読み上げソフトを使う人、視覚的な変化を過剰に感じる人、タブレットやスマートフォンの小さい画面を使う人、英語などの母語が異なる人にも役立つ具体的な改善です。実務では、見出しや要約を追加して読みやすくする、動画には字幕と要点のテキストを併記する、フォームのエラー表示をより明確にする、などの具体的な対応を取り入れることが推奨されます。
新しい基準の例
以下は2.2でよく話題になるポイントの例です。フォーカス可視性の強化、動的コンテンツの状態変更の通知、時間制約の適切な扱い、難読症の人にも読みやすい文字サイズと行間の推奨など、実装時に気をつける点を挙げています。これらは、現場のウェブ開発者がすぐに取り組める具体的な改善案です。
この点は、日常のウェブ制作にも直結します。例えば、長いフォームの入力時には「現在地が見える」設計、動的に変わるメニューには適切な通知、動画には字幕と要点のテキストの併記などを考えると良いです。視覚以外の支援も忘れず、スクリーンリーダーを使う人の読み取り負担を減らす工夫を続けましょう。
友達と雑談風に深掘りする小ネタです。2.2の話題で私が気になったのは“フォーカス表示”の話。カギは“キーボードだけでサイトを使う人にも、今自分がどこを操作しているかを見えるようにすること”です。実は学校の授業でも、マウスが使えないときにウェブを動かす練習をします。そのときフォーカスが薄いと、どこをクリックしているか分からなくなって困ります。2.2はそんな場面を想定して、フォーカスを強く、はっきり見える設計を推奨します。現場では、デザインの美しさとアクセシビリティの両立を考え、色だけでなく形、サイズ、余白の工夫を組み合わせると効果的です。





















