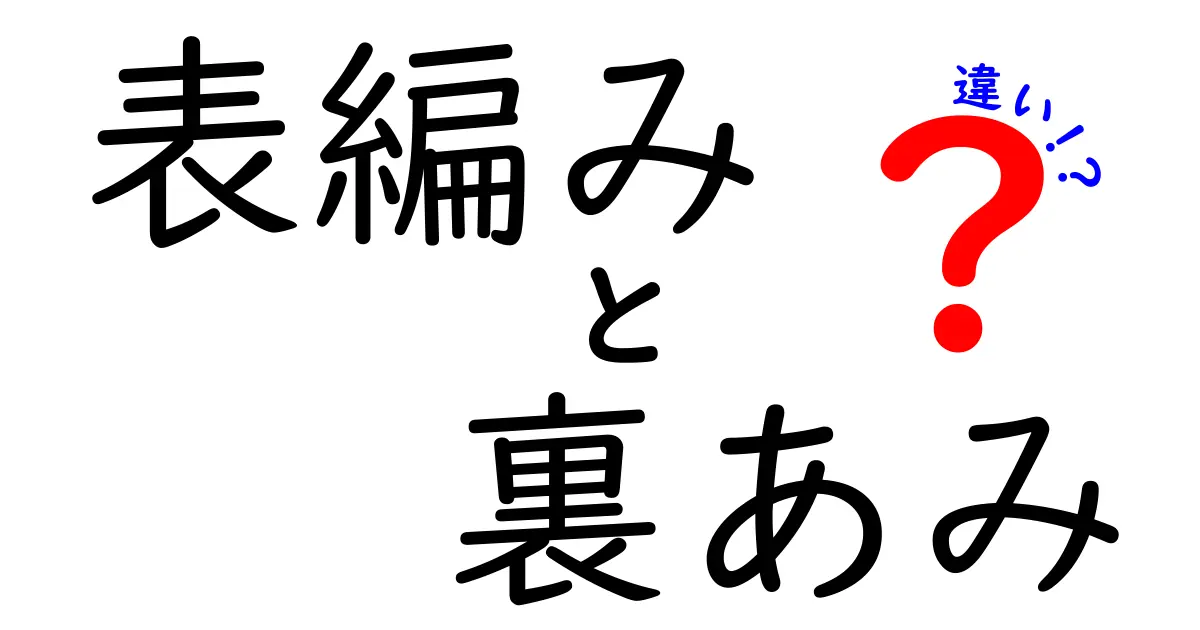

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
表編みと裏あみの違いを理解する基本
編み物を始めたばかりの人にとって、最初の大きな分岐点は 表編み と 裏あみ の違いをしっかり理解することです。 表編み は針で糸をひとくくりずつ拾って編んでいく作業の中で、右側の表面に現れる目が滑らかで均一な模様になるのが特徴です。これに対して 裏あみ は糸の表面を裏側から見る形の編み方で、裏側に現れる模様は凸凹が目立つのが普通です。これらは同じ糸と同じ道具を使っても、編み方を変えるだけで布の見た目と手触りがまるで別物になります。これから先、模様を作るときや縫い合わせをする時にも、この2つの違いを意識することがとても大切です。
このセクションでは、まずなぜこの2つが基本としてセットで学ばれるのか、その理由を日常生活の例と一緒に考えていきます。たとえば、セーターの前後身頃を編むときに、 表編み と 裏あみ の順序を変えれば生地の表情が変わってくる点や、裏地のある洋服で表面だけを美しく仕上げたいときの工夫など、具体的な場面を想定して説明します。
また、編み物は最初の数段で全体の印象が決まることが多いので、手元の糸跡が均等になるように糸の張り具合やテンポを整えるコツも紹介します。
本記事を読み進めると、 表編み と 裏あみ の基本的な違いだけでなく、実際の作品づくりでどう使い分けるかが見えてきます。特に初期段階の疑問点として「なぜ表側は滑らかで裏側は凸凹になるのか」「どうして編み目が揃うと作品の雰囲気が変わるのか」を、日常生活の感覚に例えてやさしく説明します。結論としては、布の表情は編み方の選び方でほぼ決まるという点です。
この理解を元に、次のセクションへ進んでいきましょう。
さらに、 表編み と 裏あみ の関係性を体感するための簡単な練習法も紹介します。まずは同じ糸と針で、同じ段数の作品を 表編み だけで1段、次に 裏あみ だけで1段編んでみてください。表面と裏面の差がどのくらい現れるか、どちらが柔らかく、どちらが堅い印象になるか、指先で感じることが大切です。
表編みの特徴
表編み の最大の特徴は、右側の見た目が滑らかで均一に見えることです。編み進めると表面にはつるんとした平面の模様が現れ、布地の厚みが均等に感じられやすいのが利点です。性質としては、弾力がありつつも、縦方向の伸びが主に出やすい傾向があります。衣類の表側や装飾的な模様を作るときに向いています。逆にデメリットとしては、縦方向の巻き癖が出やすく、端の処理や端のカーブを整えるコツが必要になる点です。初めのうちは表目と裏目を合わせて編む「表裏の交互編み」や、リブ編みで端の安定感を得る練習をすると良いでしょう。
このセクションを通じて、表編みの基本形を確実に覚えることが重要です。糸の引き加減を均一に保つ練習を重ね、段ごとの目の大きさがそろうよう心掛けてください。
また、実際の作品づくりでは 表編み の表情を活かすために、糸の太さや編み目の密度を調整する工夫が有効です。柔らかい素材の糸を使うと、表面の滑らかさがより際立ち、光の反射によって布に柔らかな輝きが生まれます。逆に硬めの糸を選ぶと、編み目の凹凸が強く出て、個性的なデザインを作りやすくなります。
裏あみの特徴
裏あみ は、表面から見ると凸凹が目立つのが特徴です。裏側は裏目の形状として見えることが多く、手触りは表編みとは異なる柔らかさや堅さを感じることがあります。裏あみの最大の利点は、布地の伸縮性が安定しやすく、全体の生地がしっかりとした印象になる点です。特に縁の処理やリブ編み、編地の模様を際立たせたい場面で強みを発揮します。デメリットとしては、表側の見た目がやや粗く感じる場合があり、作品全体の仕上がりが硬くなりがちで、初心者には練習が必要な場面もあります。
この特徴を踏まえ、裏あみを使う場面では「表を見せたい部分は別の編み方で補う」など、工夫を取り入れると良いです。
裏あみを活かすコツとしては、糸の張り具合を安定させること、針の持ち方を正しくすること、同じ段数を何度も練習して目の大きさを揃えることが挙げられます。裏あみだけの作品を作る場合は、全ての段を裏目で編む Garther 編みの練習をすると、布地が均等になりやすいです。こうした基本を押さえたうえで、表編みとの組み合わせを考えると、デザインの幅が大きく広がります。
実践で使えるコツと表裏の使い分け
日常の作品づくりでは、基本の 表編み と 裏あみ を上手に組み合わせることが肝心です。たとえば、セーターの前身ごろを 表編み、背中側を 裏あみ にすることで、正面の見た目を滑らかに保ちつつ、背面の伸縮性を確保できます。また、袖口や裾のリブ部分には 表編み と 裏あみ を交互に組み合わせるリブ編みを使うと、耐久性とデザイン性の両方を得られます。初心者の方には、まずは1つの部位を決めて、表編みだけ、裏あみだけで編む練習から始めると、混乱せずに技術を積み重ねられます。
最後に重要なポイントは、編み方を変えると生地の表情が変わるという事実を理解することです。作品全体の意図に合わせて、表面の見た目をどう演出したいかを考えながら、適切な編み方を選択していくことが、上達への近道です。
友だちと編み物の話をしているとき、私たちはよく表編みと裏あみの違いを“布の表と裏で感じる手触りの差”として表現します。例えば同じ糸と針でも、表編みで編んだ部分は光の当たり方で滑らかに見え、裏あみで編んだ部分は影の入り方で凹凸が強く見える、そんなズレを体感すると面白いです。私は部活の作品づくりで、表表地と裏地の組み合わせを試すことが多いのですが、それぞれの特性を理解しておくと、失敗が格段に減ります。階段を登るように少しずつ練習を重ね、表と裏の違いを体で覚えることが、上達のコツだと感じています。
前の記事: « ケーブル編みとリブ編みの違いを徹底解説!初心者にも伝わる具体例





















