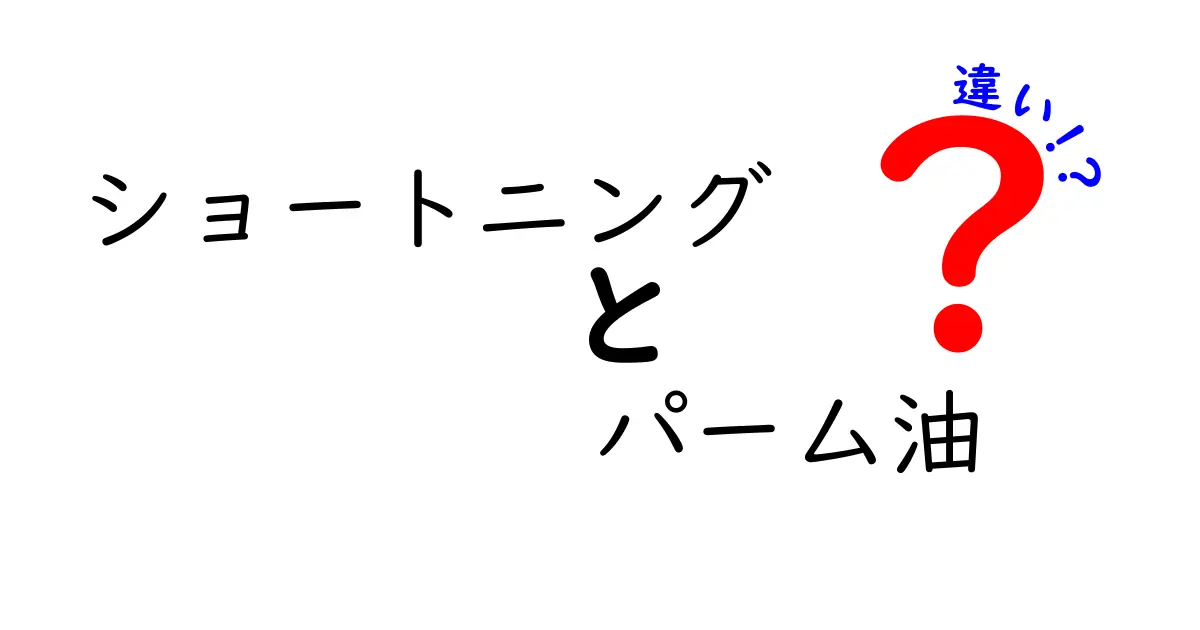

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ショートニングとパーム油の基本的な違いを理解しよう
ショートニングとパーム油は、どちらも料理で使われる油脂ですが、役割や作られ方、体に与える影響が異なります。ショートニングは主にパン作りなどで生地を固くする役割を持ち、空気を閉じ込めてサクサクした食感を作ります。一方、パーム油は熱に強く、炒め物や揚げ物にも使われ、色づきや深いコクを出すことが特徴です。製材については国やブランドで成分表示が多少異なるため、成分表示をよく確かめましょう。
読者のみなさんが日常で使う油には「何の油か」「どう加工されているか」が関係します。
ここでは、基本の違いを分かりやすく整理します。
油は「油脂の種類」と「加工の有無」で大きく分かれます。ショートニングはしばしば「部分水素添加された植物油脂」や「ブレンド油」で作られており、固体状を保つための加工が施されています。これに対して、パーム油はパームの果実から直接絞って作られ、自然に固さを保つ性質を持っています。具体的には、室温で半固体から固体の状態を取り、焼き菓子の食感を変える力があります。ここで大事な点は、どちらを選ぶかで仕上がりが大きく変わるということです。
料理の世界では、同じ材料でも油脂の違いで風味や口あたりが変わります。
次に、健康と環境の観点を見ていきましょう。ショートニングには一部の製品でトランス脂肪酸が含まれる場合があり、過剰摂取は心臓病のリスクと関係すると言われています。近年はトランス脂肪酸を抑えたショートニングも登場していますが、成分表示をよく読むことが大切です。パーム油は飽和脂肪酸が多く、過剰摂取は健康に影響を及ぼす可能性がありますが、適量を守れば料理のコクを引き出すのに有効です。また、パーム油の生産は熱帯林の伐採と結びつく問題が指摘されており、持続可能性を示す認証マークを持つ製品を選ぶなど、環境にも配慮した選択が求められています。
健康と環境の視点は、油脂を選ぶときの大切な判断軸です。
原料と製法の違いを見てみよう
以下の表は、ショートニングとパーム油の基本的な違いをまとめたものです。原料、加工方法、用途、特徴、健康・環境の観点を分かりやすく並べています。特に「用途」は、パン作り、焼き菓子、揚げ物などの具体的な例を挙げて理解を深めましょう。なお、同じ油脂でもブランドごとに成分表示が異なることが多く、購入時には成分表示を確認することが重要です。
このように、ショートニングとパーム油は「原料・加工・用途・健康・環境」で区別されます。用途に合わせて使い分けることが、料理の味と健康、そして環境保全の三つを同時に満たすコツです。実際の料理では、同じレシピでも油脂を変えるだけで食感や風味が変わることを体感してください。
今日はショートニングとパーム油の話を、友達と雑談風に深掘りしてみるね。ショートニングはパンの生地をサクサクにする魔法の油、パーム油は揚げ物にコクと色を添える名脇役。ところがそれぞれの健康影響や生産の環境問題もあって、どっちを選ぶか迷うことがある。結局は使い方次第。家では焼き菓子を作るときにはショートニングを使い、日常の炒め物にはパーム油を使うようにしている。もちろん、成分表示を確認してトランス脂肪酸や認証をチェックするのも大事だよ。友達とリサーチして、同じレシピでも油を変えると香りが変わることに気づいた。持続可能性の認証がついた製品を選ぶことは、地球の未来を守る小さな一歩だと感じる。





















