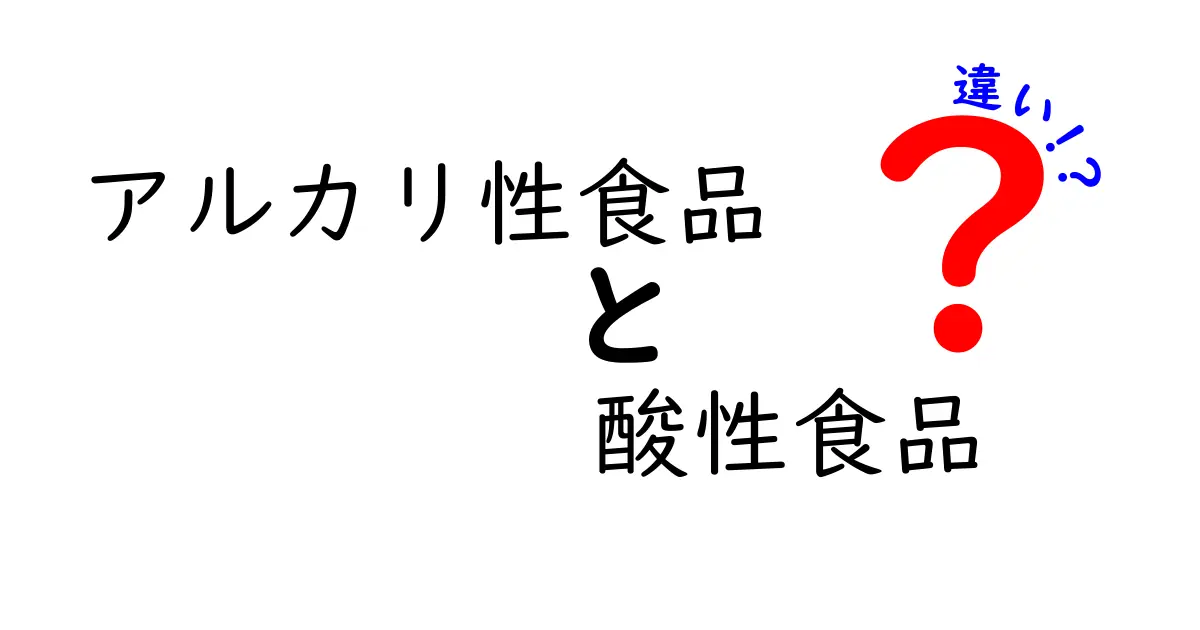

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
アルカリ性食品と酸性食品って何?基本をわかりやすく解説
<私たちの食生活においてよく耳にする「アルカリ性食品」と「酸性食品」。これらの言葉はいったい何を指しているのでしょうか?
アルカリ性食品は、体内で分解された後に体液のpHをアルカリ性に近づける食品のことを言います。一方、酸性食品は、体内で分解された後に体液のpHを酸性に近づける食品のことです。
例えば、野菜や果物は多くがアルカリ性食品に分類され、肉や魚、加工品は酸性食品が多いです。
この違いは体の健康やバランスを保つうえでとても重要で、食べるものによって体内の環境が変わることを意味しています。
では、次に具体的な食品の分類と、なぜこの分類が大切なのかをお話ししましょう。
アルカリ性食品と酸性食品の具体的な違いと健康への影響
<アルカリ性食品は主に野菜や果物、豆類、海藻類などが該当します。これらの食品は消化されると体の中の酸性度を下げ、よりアルカリ性に傾ける働きがあります。
たとえば、ほうれん草やバナナ、アボカドなどが挙げられ、健康を維持するために重要なミネラル(カリウムやカルシウム)を多く含んでいます。
一方、酸性食品は、肉類、魚介類、加工された食品、チーズ、卵などが該当します。これらは体内で代謝されると酸性度を高める傾向があり、過剰に摂取すると血液が酸性側に偏るおそれがあります。
酸性に偏ると疲れやすくなったり、骨の健康に悪影響があったりすると言われています。
健康のためには、アルカリ性食品と酸性食品のバランスを考えた食事を心がけることが大切なのです。
アルカリ性食品と酸性食品の代表例とバランスのとり方
<<
バランスをとるためには、肉や魚などの酸性食品を多く食べる場合は、必ず野菜や果物を多く摂取することがポイント。たとえば、ステーキを食べるときには付け合わせにサラダや温野菜を入れると良いでしょう。
また、飲み物も意外と影響が大きく、ジュースやコーヒー(関連記事:アマゾンの【コーヒー】のセール情報まとめ!【毎日更新中】)は酸性なので、ミネラルウォーターやアルカリイオン水を意識的に飲むのもおすすめです。
普段の食生活を少し意識するだけで、体の中のpHバランスを整えて健康維持につながります。
「アルカリ性食品」と聞くと体の中をアルカリにするとても良い食品というイメージが強いですよね。実はこの分類は体液のpHに影響を与える“後味”のようなもの。例えば、レモンは酸っぱいですが、代謝後はアルカリ性に傾ける作用があります。だから酸っぱいからといって必ず酸性食品ではないんです。このことからも、食品の“酸っぱさ”だけで判断せず、正しい知識を持つことが大切なんですよ。
前の記事: « 断捨離と身辺整理の違いとは?スッキリ生活を叶える秘訣を徹底解説!





















