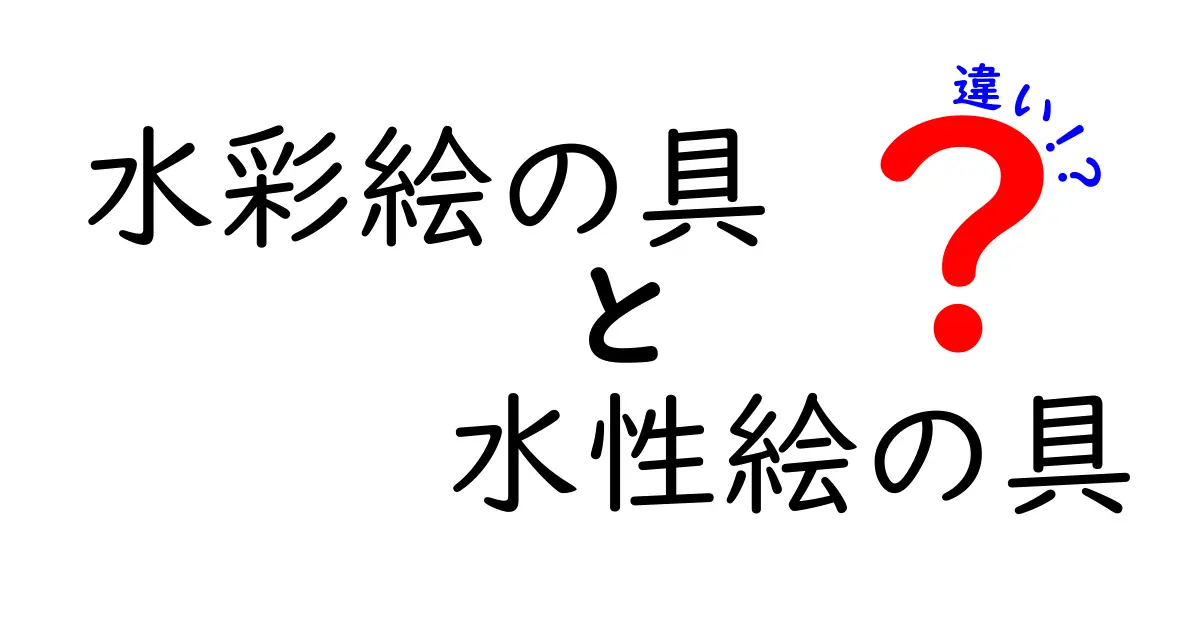

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
水彩絵の具と水性絵の具の基本的な違い
水彩絵の具と水性絵の具は、見た目は似ていても中身と仕上がり、使い方が大きく異なります。水彩絵の具は透明感を大切にする絵具で、主なバインダーは天然の樹脂であるアラビアゴムです。紙に水を含ませて薄い色を何度も重ねると、下地の白が透けて美しいグラデーションが生まれます。乾燥後も色を薄く重ねることができ、仕上がりは軽やかで柔らかな雰囲気になります。
一方、水性絵の具(日本でよく使われるガッシュ系)は不透明さを出せるのが特徴です。水を混ぜて薄くも塗れますが、白や明るい色を下地に置くと色が濃く出にくくなるよう調整されており、隠したい部分を覆い隠す力が強いです。これにより、はっきりした輪郭や面の塊を作りやすく、ポスター風の仕上がりにも向いています。
重要な違いのまとめとしては透明度の差と不透明度の差、そして色の重ね方の違いです。水彩は透過の美しさを活かすために薄い色を何度も塗り重ね、紙の質感を生かします。ガッシュは不透明度を活かして大きな面を一気に塗り、色同士の境界線をはっきりさせる表現に適しています。
また、道具選びも大切です。水彩には柔らかい紙と細い筆の組み合わせが向き、ガッシュには少し硬めの筆と若干厚手の紙が相性が良いことが多いです。
この違いを知っておくと、作品の雰囲気を意図的に変えることができ、初めて絵を描く人でも迷いにくくなります。次の段では、具体的な使い分けのコツと道具の選び方をもう少し詳しく見ていきます。
実用的な使い分けと道具選びのポイント
絵を描くときには紙と筆と絵具の組み合わせが作風を大きく左右します。まず紙の質感と厚さを選ぶことが、色の広がりを決める第一歩です。水彩絵の具を使う場合は180g以上の紙を選ぶと、湿らせたときに紙が波打ちにくく、色が広がりすぎず美しく広がります。反対に水性絵の具を使うと不透明度の調整がしやすく、やや薄手の紙でも描くことができますが、強い発色を求めるときには厚手の紙を選ぶと安定します。紙の下地の色も考慮して、白地が生きる場面と、地の色を活かす場面を使い分けましょう。
次に道具です。水彩には筆先の細さと毛量の組み合わせが重要です。細い筆は線描や繊細なグラデーションに、太い筆は大きな面を一気に塗るのに適しています。毛質は柔らかいものほど水を含みやすく、硬いものは色をコントロールしやすいという特徴があります。ガッシュを使う場合は、筆を少し硬めにした方が色の境界がはっきり出やすいです。
実際の描き方としては、水彩は薄い色を先に重ね、段階的に濃い色へ移行する“透明感を活かす順番”を意識します。水性絵の具は下地を覆うことができるため、不透明な色を活かした面を作り、後から細部を描き足すのが効果的です。
練習のコツとしては、まず水の量を揃えて同じ紙で練習し、色の濃淡の違いを体感することです。少量の絵具と多めの水で薄い色を作る感覚を覚えると、手が動きやすくなります。
最後に、初心者がよく迷うポイントをいくつか挙げておきます。水彩は“にじみを怖がらない”、ガッシュは“不透明度を活かして重ねる”という基本を忘れずに練習してください。
ここまでの内容を表にまとめると、違いが一目で分かりやすくなります。以下の表を確認して、次の作品づくりの準備を整えましょう。
表の下には、実際に描いた作品の写真を添付すると、技術の習得が早くなります。
水性絵の具を深掘りしてみると、実は絵具の粒子サイズと水の量のバランスで表現が大きく変わることに気付きます。僕が好きなのは、薄い色を何度も重ねて紙の白を生かす感覚です。水性絵の具は不透明部分を作りつつ、部分的に紙の地の色を出せるので、技術練習としては非常に適しています。友達と一緒に絵を描くとき、透明な水彩の上に不透明なガッシュを載せてコントラストを作ると楽しい雰囲気になります。





















