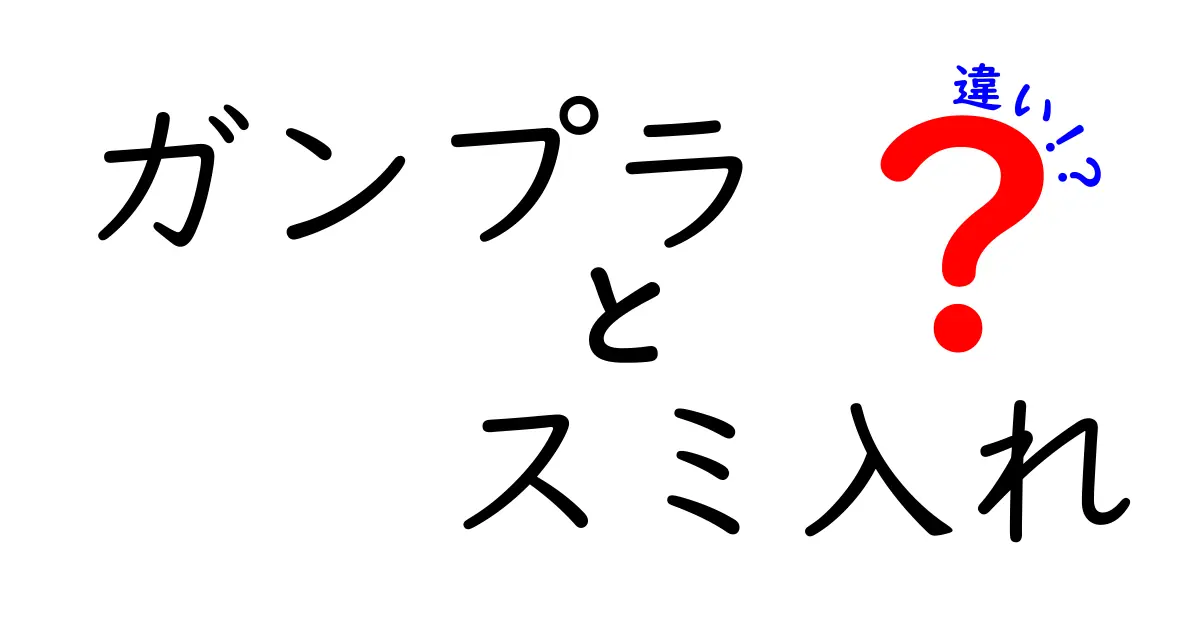

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ガンプラのスミ入れと“違い”を理解する基本
ガンプラの『スミ入れ』とは、部品の溝や陰影を強調して立体感を生む工程のことです。陰影があると光の当たり具合や形状が読み取りやすくなり、組み立てたパーツが平坦に見えるのを防げます。スミ入れの目的は、情報伝達としての陰影を自然に作ることで、塗装の美しさを保ちつつ、ディテールの存在感を引き立てます。陰影の濃さやラインの細さは作品ごとに異なり、パーツのサイズ・形状・塗装の仕上がりによって最適なバランスを探ることが重要です。
初心者は特に“濃くしすぎると写真映えはするが現実感が薄くなる”という点を注意すると良いでしょう。反対に薄すぎると陰影がぼやけて立体感が失われます。
この違いを理解しておくと、どの道具を選択するべきか、どの濃さで始めるべきかが見えやすくなります。
本稿では、エナメル系・水性系・ラッカー系の特徴と使い分け、仕上げの順序、練習のコツ、そしてよくある失敗の対処法を、初心者にも分かる言葉で丁寧に解説します。
最後まで読めば、あなたのガンプラに合ったスミ入れの道筋が見えてくるはずです。
スミ入れの種類と使い分け
スミ入れには大きく分けて三つの材料があり、それぞれに向く場面と注意点が存在します。エナメル系の魅力は、陰影のにじみと拡散を活かしたリアルさで、細いラインを丁寧に描くのに向いています。塗料を溶かす溶剤が強いため、拭き取りのタイミングを間違えると濃くなりすぎることがあります。慣れれば、細部の凸凹やモールドの陰影を劇的に際立たせる力を持っています。
次に水性系アクリル系は取り扱いが比較的安全で、初心者にも扱いやすいのが特徴です。すぐ乾くので短時間での作業が進み、ガンダムマーカーのような筆触タイプや液状タイプを選べます。色の深さはエナメルより控えめになることがありますが、重ね塗りで陰影を自然に作ることができます。
最後にラッカー系は、耐久性と透明感のバランスが良く、クリアコート後の仕上がりが美しく映える傾向があります。ただし匂いが強く、換気と作業環境の整備が必須です。扱いを誤ると塗膜の密着が悪くなることもあるため、事前のテストと適切な薄さのコントロールが大切です。これら三つの材料を理解することで、作品ごとに適切な方法を選べるようになります。
使い分けのコツは、作品のイメージと作業環境を意識することです。薄く、何度も重ねることで陰影は自然になり、強すぎない陰影が長く美しく保たれます。パーツごとに質感や色味の違いを考慮して選択を分けると、完成度が高まります。クリアコートの有無や仕上げの光沢感も、陰影の見え方を左右する重要な要素です。この記事の後半では、具体的な手順とコツを詳しく紹介します。
友達とガンプラの陰影の話をしていて、エナメル系の話題になったんだ。最初は匂いが強くて扱いが難しそうだと思っていたけれど、実際には細いラインを丁寧に描けるという大きな長所があると気づいた。薄く薄く塗って、溝に沿って流すと陰影が自然に現れて、パーツの形が立体的に見える。拭き取りのタイミングを見極める練習を積めば、余分な色が残らず、元の色と陰影のバランスが良くなる。エナメル系は慣れると、複雑なモールドの陰影もきれいに出せるので、挑戦する価値があると感じた。とはいえ、初めは失敗もつきもの。焦らず、薄く重ねることを繰り返すと、だんだんコツがつかめてくる。





















