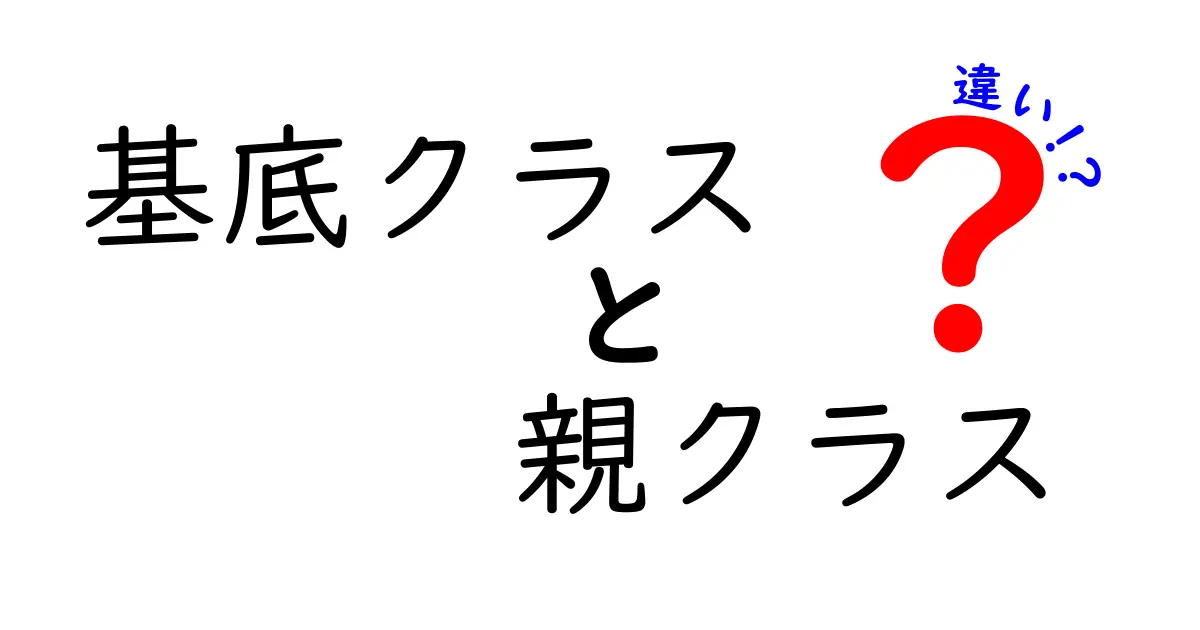

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
基底クラスと親クラスの違いを徹底解説しよう 101のポイントと実務での使い分け方を中学生にもわかるように丁寧に解説する導入部
基底クラスと親クラスは オブジェクト指向プログラミングの中核をなす考え方です。
この二つを正しく理解しておくと クラス設計の土台が安定します。
この記事ではまず用語の背景を整理し、次に実務での使い分け方を具体例と表で比較します。
難しく感じる人も多いですが、心配はいりません。中学生でも理解できるよう、身近なイメージで順を追って説明します。
ポイントは用語の違いよりも「どの階層を指すか」という点です。これを押さえると設計の発想が変わります。
1 基底クラスとは何か
基底クラスとは 継承の土台となるクラス です。派生クラスが共通の機能を引き継ぐ基盤となり、共通の属性やメソッドをここに集約します。
この整理がうまくいくと コードの重複を減らせ、修正の影響範囲も狭められます。
実務で基底クラスを適切に設計するコツは 「最小限の責任範囲」と「再利用性の両立」 を意識することです。例えば動物の共通機能を基底クラスへ集約し、猫や犬などの派生クラスはそれを継承して個別の特徴を追加します。
2 親クラスとは何か
親クラスとは 直近の上位クラス を指す言葉です。派生クラスが上位の機能を受け継ぎつつ、さらなる機能を追加することで新しいクラスを作る流れを説明します。
複数の階層がある場合には 親クラスは常に一つ上の階層です。
この考え方を把握しておくと 後の階層構造の理解が楽になります。Java なら super キーワードの挙動を思い出すとイメージしやすいでしょう。
3 実際のコード例と表で比較
下の例は日本語風の説明コードです 実際の言語の構文とは異なる場合がありますが 概念の理解には十分です。
この表から分かるとおり 基底クラスと親クラスは密接に関係します が 目的は異なります。基底クラスは土台であり 親クラスは直近の上位を指すことが多いのが実務の感覚です。
理解を深めるには自分で具体例を作ってみるのが一番です。
きのうの放課後 学校の廊下で友だちと雑談していたとき基底クラスと親クラスの混同について話題になった。私たちは実務と授業の違いを具体的な例で整理し、基底クラスは土台となる機能の集約、親クラスは直上の上位クラスを指すことが多いと結論づけた。言い換えると基底は“全体の設計図”、親は“今この派生がどの上位から機能を受け継ぐか”という視点。こうした認識のズレを減らす工夫が大切だと感じた。





















