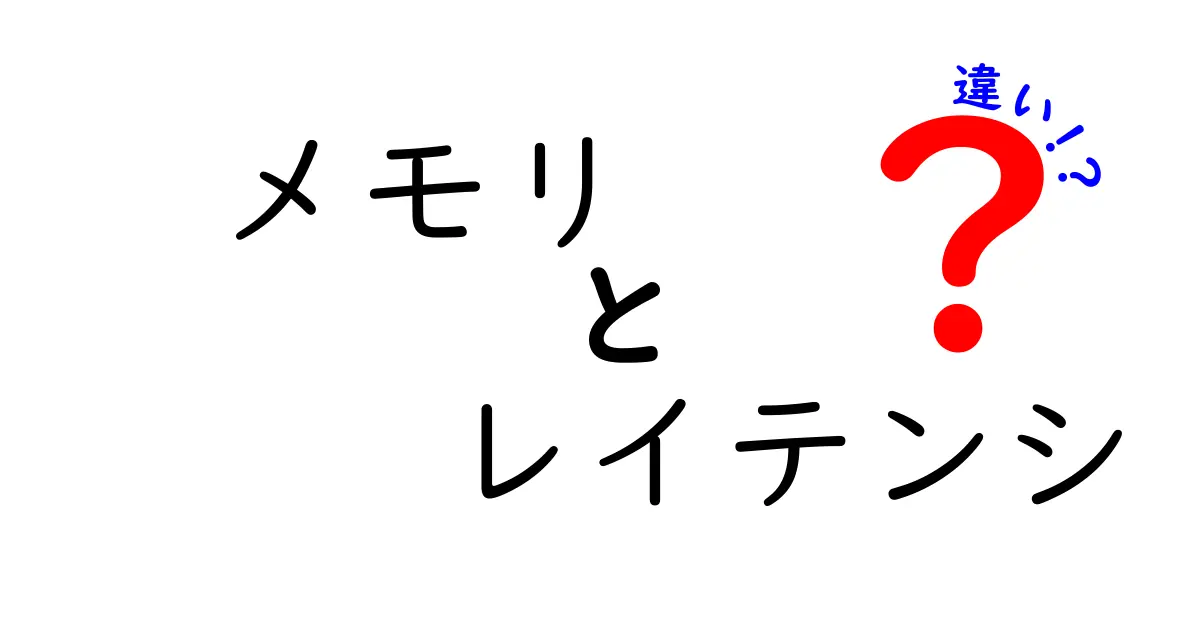

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
メモリとレイテンシの基本概念を整理
まずはメモリとは何かを理解しましょう。メモリはCPUが作業中に使うデータを一時的に置く場所です。映画を見ながらノートを開くとき、机の上に資料を広げておく感じに似ています。データを取り出すときには必ず待ち時間が発生します。この待ち時間が「レイテンシ」です。
つまりメモリは容量と速度の両方が重要です。
メモリには主記憶と呼ばれる“大きな机”と、CPUの手元にある“入る箱”のようなキャッシュがあり、それぞれ役割と距離が違います。
例えるなら、大きな机はたくさんの本を置けるが机までの距離があるため取り出すのに少し時間がかかり、手元の小さな引き出しはすぐ取り出せるが容量は小さい、という感じです。
レイテンシは数値で表され、単位は主にナノ秒(ns)で表されます。同じ容量でもDDR4とDDR5では設計が違い、読み出しの待ち時間が変わります。
ねらいは、データを必要とするタイミングに対して、できるだけ待ち時間を短くすることです。これがゲームの起動やアプリの立ち上がり、写真の読み込み速度にも影響します。
このセクションの要点をまとめると次のとおりです。
- メモリはデータを一時的に置く場所で、容量と速度の両方が重要です。
- レイテンシはデータを要求してから実際に返ってくるまでの時間を表します。
- 高性能なパソコンでは、低いレイテンシと高い帯域幅(データを一度に運べる量)の両方を狙います。
実際のパソコンでの体感と測定のしかた
現実の世界では、メモリのレイテンシはゲームの体感やアプリの起動時間に現れます。例えば、ゲームでロード画面の待ち時間やマップの読み込み時間が短いと、ストレスが減ります。
また、写真を編集するアプリを開くときにも、背景で多くのデータを読み込む必要があるため、レイテンシが低いと作業がスムーズになります。
現代のパソコンでは、メモリの速度はDDRの世代と周波数で表され、レイテンシはCAS Latency(CL)などの「何クロックで返ってくるか」を示します。
例えば同じ容量でも、DDR4でCLが低いタイプとDDR5でCLが高いタイプだと体感が異なることがあります。実測値を知るにはベンチマークソフトやOSの統計情報を見ます。
ベンチマークは「読み出し」「書き込み」「ランダムアクセス」といった指標を表示します。
以下は基本的な参考表です。
この表は実機やCPUの構成、メモリの実装により数値は変わります。
装置を選ぶときには、以下の3点を意識すると分かりやすいです。
実務でのコツは「同じセットのメモリを揃える」「多くのコアが同時アクセスしても安定する帯域を確保する」ことです。
母集団が大きいほど、実際の遅延は分散され、体感も安定します。
日常生活での最適化のヒント
ここでは、日常的にできる「レイテンシを下げる工夫」を紹介します。
まず、CPU側とメモリ側の組み合わせを揃えること。
マザーボードの規格に合わせて適切な周波数のメモリを選び、XMP設定を有効にすると、メーカーが想定する性能を引き出しやすくなります。
次に、メモリを増やす・高速なメモリを選ぶ・デュアルチャネル(2枚差し)で運用すると、読み出しの同時アクセスが増え、全体のレイテンシを見かけ上は低く感じられます。
さらに、背景で動くアプリを減らすことも効果的です。ウイルス対策ソフトの影響や不要なスタートアップを止めると、実質的な空きリソースとバンド幅が増え、待ち時間が短くなります。
最後にストレージの選択も影響します。頻繁にデータを読み込む場面ではSSDの速度が大きな違いを生み、RAMのレイテンシを補完してくれます。
まとめると、レイテンシを下げるには“速いメモリを選ぶ”“同じ性能のメモリを揃える”“不要な処理を減らす”という三つのコツが基本です。この三つさえ守れば、日常の作業やゲームで体感する快適さは大きく向上します。
ある日の放課後、友だちとスマホゲームの話をしていたとき、友達が『なんで同じゲームでも机の上が広いと速いんだろう?』と尋ねてきました。そのとき私は、メモリのレイテンシと呼ばれる“待ち時間の長さ”が鍵だと説明しました。レイテンシが短いほどデータの取り出しが速く、画面の切り替えや敵の反応がすぐに感じられます。私たちは、買い物のときに容量だけを見るのではなく“遅さの原因にもなる要素”をチェックする習慣をつけるべきだと話しました。話はさらに広がり、キャッシュの仕組みやデュアルチャネルの効果、XMPの設定といった話題へ。結局、速さは数値だけで決まるわけではなく、データがどれだけすぐに使えるかというタイミングの工夫の総和だと気づくことができました。
次の記事: プランクとホバーの違いを徹底解説!初心者でも分かる使い分けのコツ »





















