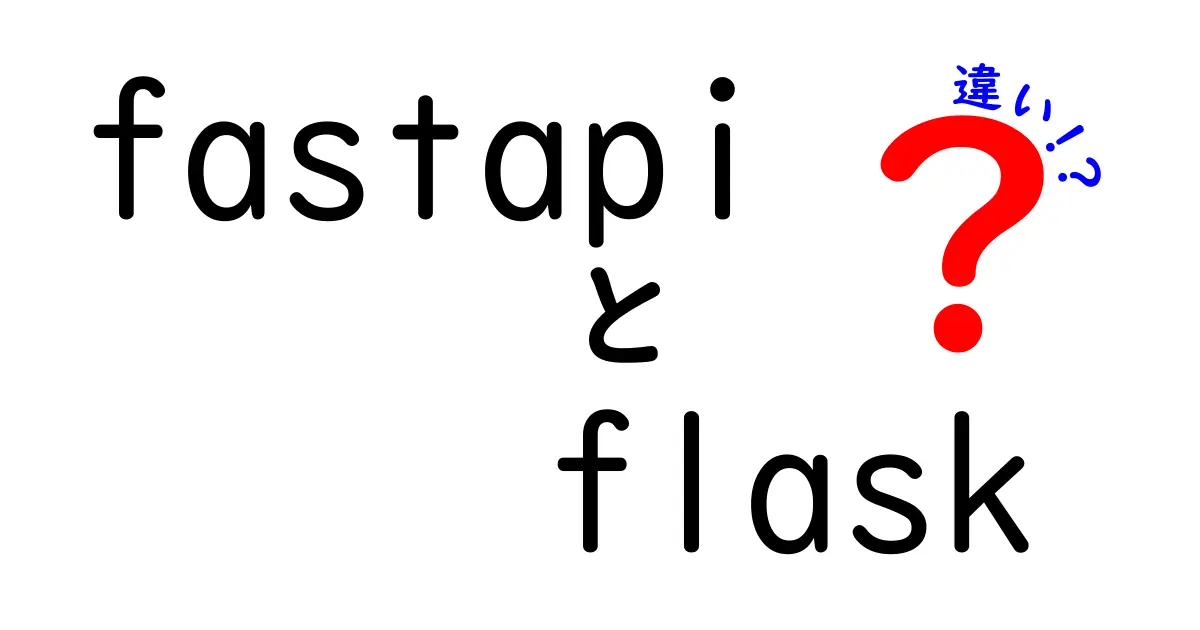

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:なぜ fastapi と flask の違いを学ぶのか
Web API を作る時、どのフレームワークを選ぶかは実務の成果に大きく影響します。flask は長い歴史を持つ安定した土台で、学習コストが低く、拡張性のあるエコシステムが魅力です。対して fastapi は最近の登場ですが、型ヒントを活かした自動検証、OpenAPI による自動ドキュメント生成、非同期処理のサポートを前提に作られており、パフォーマンスの面で有利になるケースが多いです。
この違いを理解すると、あなたが作りたいアプリケーションに最適な選択が自然と見えてきます。例えば、学習を早く終わらせたい場合は flask の方が入りやすいことが多く、API が外部と頻繁に連携する大規模なシステムを作るなら fastapi の方が合うことがあります。
また、開発チームのスキルセットや既存のコードベース、納期、デプロイ環境も影響します。初心者には「まずは小さな API から始める」体験が重要ですが、将来的に型安全性と自動ドキュメントの恩恵を受けたい場合は fastapi への移行を視野に入れるのも手です。
この記事では、初学者にもつまづきにくい言葉で、具体的な例を交えつつ、fastapi と flask の違いを整理します。これを読めば「今すぐに導入するべきか」「もう少し待って flask から始めるべきか」が分かるようになります。
fastapi の特徴と使い道
fastapi の特徴と使い道は大きく三つに分けられます。まず第一に速度と型安全です。fastapi は Python の型ヒントを利用して入力データの検証やエラーレスポンスを自動で作ります。これにより、実務でのバグを減らし、API の信頼性を高めることができます。次に ドキュメントの自動生成です。OpenAPI 仕様に基づくUI が自動で作られるため、開発者だけでなくフロントエンドや運用担当者にも理解しやすい API を提供できます。試験的なデータを送るデモや、外部サービスとの連携を相手に説明する時にも便利です。三つ目は 非同期処理のサポートです。ネイティブに async/await が組み込まれており、I/Oが多い処理(データベースやネットワーク通信など)を efficiently 處理できます。学習コストは flask より少し高く感じることがありますが、公式ドキュメントと例が充実しており、実務での成果につながりやすい設計になっています。
さらに エコシステムと将来性も魅力です。Pydantic や FastAPI 自体の進化に合わせて、デプロイや認証、データ検証の周辺ツールが急速に整備されています。小規模なAPI から大規模なマイクロサービスへとスケールさせる際の移行がスムーズで、クラウド環境でのパフォーマンスを活かしやすい点も魅力です。
結論として、もし「速く作りたい」「型の安全性を確保したい」「自動 DOCS が欲しい」という希望があるなら fastapi は非常に有力な選択肢です。
flask の特徴と使い道
flask の特徴と使い道は、シンプルさと 拡張性にあります。flask は最小限の核と豊富な拡張ライブラリで、用途に合わせて自由に組み合わせられます。新しい機能を追加する時には、必要なモジュールを自分で選び、ルーティングやテンプレート、データベース接続などを段階的に構築していきます。初心者には学習コストが低く、公式チュートリアルも分かりやすい点が魅力です。
また、モノリス型のアプリからマイクロサービス型の設計まで対応可能で、初期のプロトタイプを短時間で作ってから機能を拡張する「イテレーティブな開発」に向いています。
一方で、自動的な入力検証やドキュメント生成が標準機能としては弱いため、別途ライブラリを選ぶ必要があります。大規模な API や複雑なデータ検証が多い現場では、開発担当者が信頼できるライブラリを組み合わせて整備する作業が多くなる点を覚えておくと良いでしょう。
総じて、すぐに使い始められる気軽さと、必要に応じて拡張できる自由度が flask の最大の魅力です。小規模なサービスから初めて、徐々に機能を積み上げたい場合には特に向いています。
どう選ぶべき?ケース別の判断基準
選択の判断は、用途・規模・学習時間・既存のスキルセットで変わります。小規模で学習を最優先なら flask が入り口として安定しています。シンプルな API やウェブアプリのデモ、社内ツールなど、すぐに動くものを作る場合に向いています。
ただし、将来性を考えて「型安全」「自動ドキュメント」が欲しい場合は fastapi への移行コストを計算しておくと良いです。
規模が大きく、非同期 I/O が多いシステム、複数のマイクロサービスを連携させる場合には fastapi が力を発揮します。
また、組織のスキルセットがPython の型ヒントに慣れているなら fastapi へ寄せる判断は自然です。
最終的には、プロジェクトの納期、デプロイ先、運用の自動化、セキュリティ基盤、開発チームの学習コストを総合して判断します。具体的には以下のポイントを押さえると良いです。
要件の難易度、データ検証の重要性、自動ドキュメントの必要性、将来の拡張性、チームのスキル、デプロイ環境、既存コードベースなどです。
また、現場での実践を想定して、まずは Flask で簡単な API を作ってみて、次に FastAPI で同じ機能を再現してみると、違いが見えやすくおすすめです。
この表を見て、自分のプロジェクトに合うのはどちらかを判断してみてください。もし「型安全と自動ドキュメントを重視したい」「非同期 I/O を活かしたい」なら fastapi が適しています。逆に「とにかく早く小さな API から始めたい」「学習を押さえつつ確実に動くものを作りたい」場合は flask が良い選択になりやすいです。最終的にはチームのスキルや納期、運用体制を総合して deciding してください。なお、実務では両方を使うプロジェクトもあります。プロトタイプを flask で作り、後で fastapi に移行するという手法も有効です。
非同期処理について語るとき、友達とカフェで話しているような雑談風に説明すると理解が深まります。例えるなら、学校の文化祭の準備を想像してみてください。前日までに準備が終わらず、みんなが順番待ちをしている状況を考えると、待つ間に他の作業を同時に回せると全体の進捗が速くなることに気づきます。非同期処理はまさにその「待ち時間を有効活用する仕組み」です。FastAPI はこの考え方を最初から設計に組み込んでいるので、複数の作業を同時に進めるのが得意です。一方、Flask は「順番に丁寧に作る」タイプの設計で、待ち時間を別の作業に変える工夫は自分で取り入れる必要があります。つまり、非同期処理のメリットを最大化したいなら、FastAPI の方が自然に感じられるはず。とはいえ、急いで小さなものを作る場面では Flask の方がストレスなく開発を始められることも多い。要は、待つ時間をどう使うかという発想の違いなのです。





















