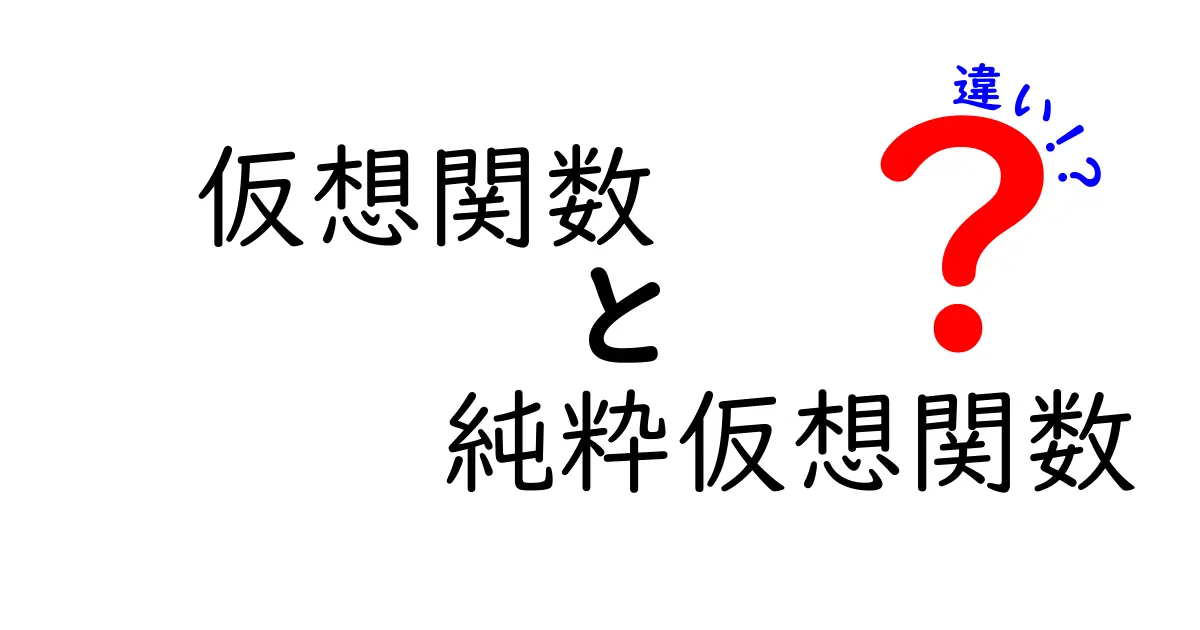

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
仮想関数と純粋仮想関数の違いをわかりやすく解説
プログラミングの世界には「仮想関数」と「純粋仮想関数」という言葉があり、初めて見ると混乱しがちです。ここでは中学生にも理解できるよう、生活の例に例えて噛み砕いて説明します。
まず、仮想関数とは「基底クラスに用意された関数で、派生クラスが呼び出すと実装が派生クラスのものに切り替わる」仕組みのことです。動的ディスパッチと呼ばれる仕組みを使って、実際に呼び出される関数はオブジェクトの型に応じて決まります。
つまり、同じ名前の関数を使っても、どのクラスのオブジェクトを操作しているかで結果が変わるのです。たとえば「動物」という基底クラスが鳴くという仮想関数を持っておくと、犬はワンワン、猫はニャーといった違う鳴き声を出すようにできます。これが仮想関数の強みで、コードの再利用性や拡張性を高めます。派生クラスでの振る舞いを柔軟に変えられる点が魅力です。
一方、純粋仮想関数は「この関数は基底クラスで具体的な実装を持たない」という宣言です。基底クラスはあくまで契約書の役割を果たし、派生クラスが必ず実装することを強制します。基底クラスを抽象クラスとして扱い、直接インスタンス化できない点も特徴です。抽象クラスを使えば、派生クラス間の共通する設計意図を保ちながら、個々の派生クラスに個性を持たせることができます。
下の表はこの違いを一目で比べられるようにした簡易バージョンです。なお、実務では表だけで判断せず、コードと設計のバランスを見ながら使い分けます。表の各行は大事なポイントを押さえるためのものなので、ひとつずつ読んで理解するのがおすすめです。
この表を見てもまだ分からない人のために、最後にもう少し現実的な話をします。仮想関数は「コードを書き換えずに挙動を変えたい」とき、純粋仮想関数は「最低限の機能を定義して、派生クラスに責任を持たせたい」ときに使います。
実際の使いどころの感覚をつかむコツ
・仮想関数の活用例としては、共通の手順を基底で用意しつつ、個別の手順だけ派生クラスで変える設計。
・純粋仮想関数を使う場面は、派生クラスを増やしていく開発や、外部からの部品を組み合わせるときの「インターフェース設計」。
・抽象クラスは後から機能を追加しても安全に拡張できる土台になります。
純粋仮想関数は、設計の橋渡し役です。基底クラスをインターフェースとして使い、派生クラスが各自の具体的動作を実装します。私の経験では、純粋仮想関数を理解すると、現実のチーム作業でも「誰が何を作るのか」をはっきり決められるようになりました。基底クラスを抽象化しておくと、後から新しい派生クラスを追加しても既存のコードへの影響を最小限に抑えられます。ただし、多すぎる純粋仮想関数は設計を硬直化させることがあるので、機能の粒度と責任の分担を慎重に考えることが大切です。設計意図を名前やコメントで明示することも忘れずに。





















