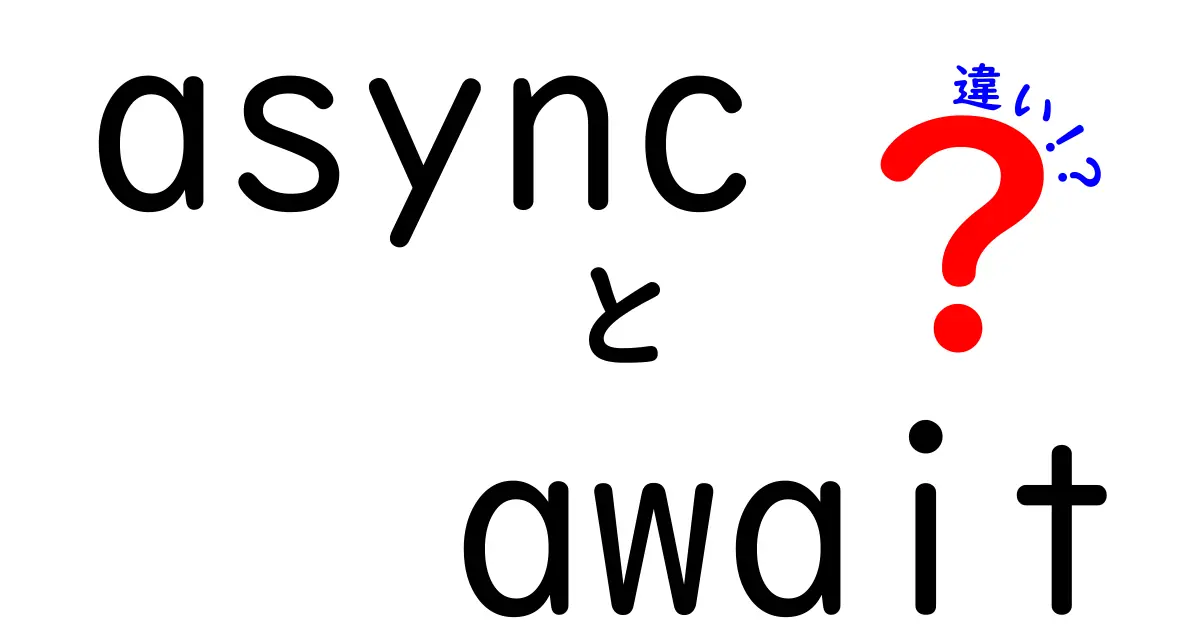

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
初心者でもつまずかない!asyncとawaitの違いを徹底解説
プログラミングでの「非同期」は、時間の使い方を変える大事な考え方です。オンラインゲームや動画サイト、SNSなど私たちの生活には“待つ”時間がたくさんあります。だけど待つのをそのままウェブページやアプリの動作に組み込むと、待機中に画面が固まってしまったり、操作が遅く感じられることがあります。そこで「非同期処理」という技術が登場します。非同期処理は、同時に複数の作業を進められるように、時間の使い方を工夫する方法です。私たちは普段、物語の場面転換のように、待つべきときと待たなくていいときを使い分けます。プログラムの中でも同じで、データをネットから取ってくる、ファイルを読み込む、長い計算をバックグラウンドで走らせる――こうした作業を、別の処理と同時に進めることで、全体の動作を速く感じさせることができます。
この章の核心は「async」と「await」の関係を正しく理解することです。まず、戻り値が「Promise」という約束で返ってくる関数を作るときに、関数の前に「async」を付けると、その関数は必ず Promise を返すようになります。次に、呼び出す側でその Promise が解決するのを待つには「await」を使います。await を使うと、結果が返ってくるまでその場の実行を一時停止し、次の処理へ進むタイミングを揃えやすくします。これを使えば、データを取る処理の連鎖や待ち時間の調整を、読みやすい形のコードで書けるようになるのです。
ただし注意点もあります。await は必ず「async 関数の内部」でだけ使えること、待ち時間が長い処理を sequential に実行してしまうと、全体の遅さを招くことがある点です。また、複数の処理を同時に走らせたい場合には「Promise.all」など別の手段を使う必要があります。さらにエラーハンドリングは、try/catch を使って行うと、エラーを見つけやすく、デバッグもしやすくなります。今回の解説では、これらのポイントを、まずはイメージとしてつかむことを目標にしています。今後の章で具体的なコード例と共に、手を動かしながら理解を深めていきましょう。
1. 何が非同期なのか?asyncとawaitの役割を分解
「非同期」とは、プログラムの流れを止めずに別の仕事を進めることを意味します。文字だけ読むと難しく感じますが、日常の例で考えると分かりやすいです。例えば友だちと話しているとき、あなたが返信を待っている間に別のことを片づけるイメージです。Webページを表示しているとき、サーバーからデータを取ってくる間、画面をフリーズさせずに他の操作を可能にするのが非同期の考え方です。async は「この関数は非同期ですよ」というマークのようなもので、await は「この Promise が解決するまで待ってね」という指示です。これを理解すると、コードがどう進むかを頭の中で描きやすくなります。
実際には、async 関数の中には必ずといっていいほど「Promise」が付きまといます。簡単に言えば、async で定義した関数を呼ぶと、その結果はいつか終わる約束(Promise)として返されます。次に、await を使ってその約束の成否を待ち、結果を変数に受け取ります。これを使えば、コールバックの嵐や長い then の連鎖を避けられ、コードの流れが自然になります。
しかし、await の使い方を誤ると、思わぬ順序待ちになって全体が遅くなることもあります。例えばデータを3つ順番に待つとき、それぞれの待ち時間が合計されてしまい、並列に処理できる場面を逃してしまうかもしれません。だから「並列処理」と「直列処理」の違いを意識し、必要に応じて Promise.all などで同時に走らせる工夫が大切です。これを覚えておくと、実務でのミスも減ります。
2. コードの読みやすさとエラーハンドリングの違い
読みやすさは、コードの可読性を高める大切な要素です。従来のコールバックや長い then の連鎖は、何が起きているのかを理解するのに時間がかかります。async/await は、自然な順序で結果を待つように見えるため、誰が読んでも処理の流れが追いやすくなります。例えるなら、映画の脚本のように、次に何が起こるのかを前提を示して追える感覚です。この仕組みを上手に使うと、エラー処理もシンプルになります。try/catch を使えば、エラーが発生した場所と伝え方を統一しやすく、デバッグが楽になります。
ただし、async/await を使うときは「待ち方」の設計にも気をつけなければなりません。Promise が返ってくる場所を変に待ってしまうと、他の処理が止まってしまうことがあります。適切な場所に await を置く、あるいは parallel execution を plan するなど、設計の選択肢を増やすことが大切です。特にエラーハンドリングの観点では、単純に一つの await の中で try/catch するより、複数個の非同期処理をまとめて管理する方法(例: Promise.allの組み合わせ)を知っておくと強力です。
この記事では、実務でよく見るパターンを取り上げ、何をいつ await するべきか、どのような場合に Promise.all を使うべきかを、具体的な考え方としてまとめています。最終的には、 async/await を使いながらも、コードの美しさと安全性を両立できる道筋を見つけることを目標にしています。
3. 実際の使い分けとパターン
使い分けの基本は“何を待つべきか”と“待つときの順序”を決めることです。もしデータを3つの非同期処理で同時に取りに行い、全てが揃ってから次の処理へ進みたいなら、まずはこれらを並列実行させてから結果を受け取るのが効率的です。例えば Promise.all([p1, p2, p3]) は、3つの処理を同時に走らせ、最後に全てが終わったときに結果を配列として返します。これにより待つ時間を短縮できます。
一方、データが順番に必要な場面では、1つ目が終わってから2つ目、という直列実行が適しています。この時は await を適切な場所に配置して、前の処理が完了してから次の処理へ進むようにします。エラーハンドリングは try/catch で包み、どの処理で失敗したのかを特定できるようにします。パターンを覚えたら、コードの設計図を描くように、まずは“何を待つのか”を決めてから実装を始めると良いです。
下の表は、3つの使い方の違いを整理したものです。
最後に、現実のコードではログを出す、タイムアウトを設定する、キャンセルを検討するなどの工夫が必要です。こうした実務的なポイントを押さえると、async/await は強力な武器になります。
友達とカフェで雑談しているみたいに話すと、await は“待つ”こと自体を、悪いことではなく“次に進むための道具”だと気づかせてくれます。async は君の関数を“非同期対応”にしてくれる設計図のようなもの。だから待つべき時と待たない時の判断を学べば、コードは自然と読みやすく、メンテもしやすくなります。私は、初心者の人にはまず並列処理と直列処理の違いを意識させ、必要な場面で Promise.all の使い方を覚えることをおすすめします。





















