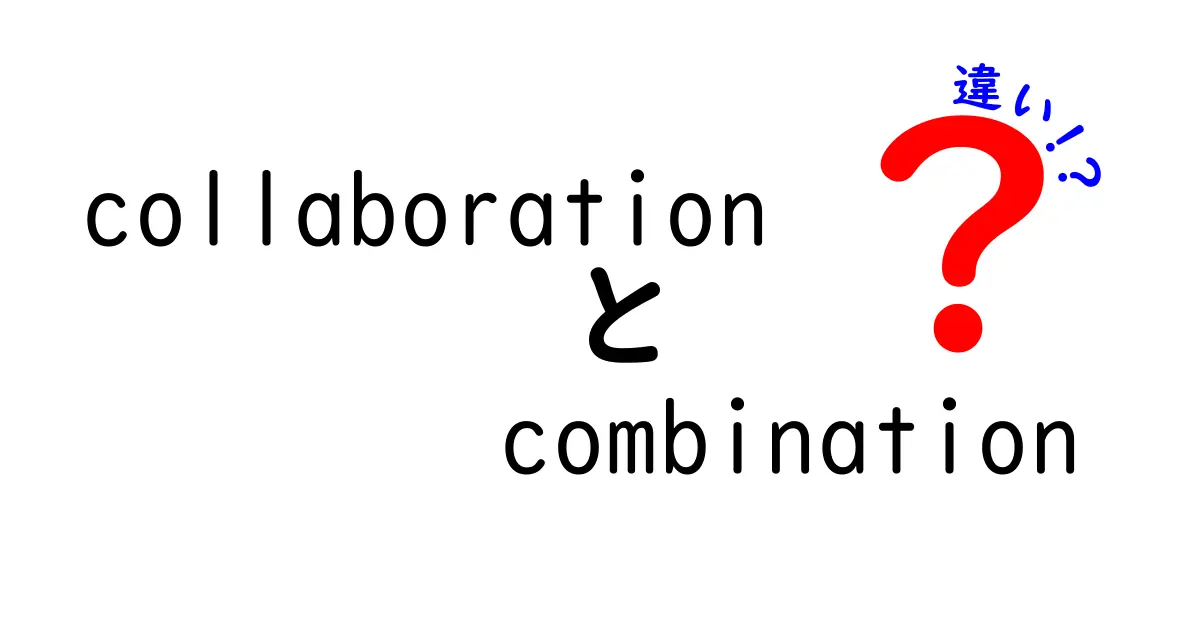

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
collaborationとcombinationの基本を押さえる
この二つの英語は発音や意味が似ていて紛らわしいこともありますが、使い方には大きな違いがあります。まずcollaborationは人と人が協力して一つの成果を作り上げるときに使います。相手と役割を分担し、情報を共有し、問題を一緒に解決するという行為を指す言葉です。対してcombinationは複数の要素を組み合わせて新しいものを作る力学を指します。人間関係に重点を置くのか、それとも要素の集合体をつくるのかの違いがポイントです。
日常の場面に置き換えると、協力して成果を出す場面にはcollaborationがよく使われます。学校の研究プロジェクト、部活の合宿、職場のチームミーティングなどで「みんなで協力していいものをつくろう」という意味合いです。一方で別々の材料やアイデアを組み合わせて一つの新しい形をつくる場合にはcombinationが適していることが多いです。料理のレシピのように“いくつかの要素をどの順番でどう組み合わせるか”が焦点になる場合にこの語が使われます。
以下の例を見てみましょう。
例1: グループで新しいアプリをつくるときには collaboration がぴったり。役割分担と情報共有を前提に、デザイナーとエンジニアが常にコミュニケーションを取りながら進めます。
例2: 新しい味を生み出す料理では combination が核心。異なる香辛料や食材をどう組み合わせるかを試行錯誤します。
場面別の使い分けと具体例
この section では、さらに具体的な場面ごとの使い分け方を詳しく見ていきます。まずは使い分けの基本ルールとして、人物関係と要素の関係を分けて考えると理解が楽になります。もし主語が人であり、誰かと一緒に作業を進める場面なら collaboration、主語が物事の組み合わせや創造的な新しい形を指す場合は combination を使うのが自然です。
この表から分かるように、collaboration は共創の過程そのものに焦点を当て、combination は要素の結合による結果や新しい組み合わせに焦点を当てます。実務ではこの二つを同時に使う場面も多いですが、基本の出発点を間違えないようにすることが大切です。
つまり「誰と何をどう作るのか」を最初に決めれば、どちらの語を使うべきかすぐ判断できます。仲間と協力して新しい成果を生むのが collaboration であり、別々の要素を組み合わせて新しい形をつくるのが combination です。
友達と文化祭の準備をしていたとき、collaborationの本当の意味を体感しました。役割を分担し、互いの意見を尊重し合うだけでなく、進捗を共有して小さな困難を一緒に乗り越える。その結果、私たちは一人ひとりの力を合わせて初めて出せたアイデアがあり、これがまさに協同作業の力だと実感しました。さらに、コミュニケーションの頻度と透明性が成功の鍵だということも学びました。相手の視点を受け止め、柔軟に方針を変える勇気も大切だと気づきました。





















