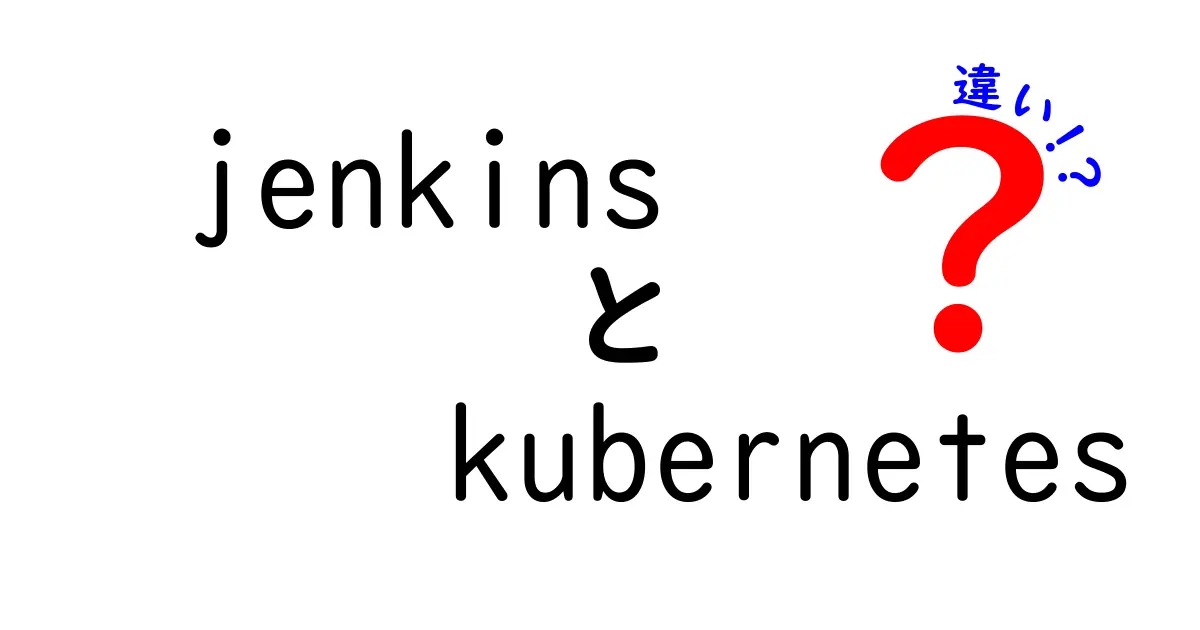

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:JenkinsとKubernetesの違いを知る理由
現代のソフトウェア開発では、アプリを作るだけでなく、それを「作ってから動かす」までの流れを自動化することが重要になっています。そんな時に登場するのが Jenkins と Kubernetes です。どちらも人気のあるツールですが、役割がぜんぜん違います。Jenkins は“継続的インテグレーションとデリバリー”を支える自動化サーバーであり、Kubernetes は“コンテナを大量に動かすための仕組み”です。この二つを混同すると、何をどのツールに任せるべきか迷ってしまいます。ここでは初心者にも分かるように、両者の違いをはっきりさせ、現場での使い分け方のヒントを紹介します。さらに実務でどう連携させるかのイメージもお見せします。
この話題を理解する第一歩は「目的の違い」を見抜くことです。
Jenkins はコードを動かすための“プログラムの実行環境”を提供しますが、Kubernetes は動く仕組みを提供します。
つまり、Jenkins は「作る人の作業を自動化する道具」、Kubernetes は「動く物を管理する道具」です。
Jenkinsとは何か
Jenkins はオープンソースの自動化サーバーです。開発者がコードをビルドしてテストし、リリースするまでの作業を自動化します。プラグインが豊富で、パイプラインと呼ばれる処理の連鎖を作ることができます。Jenkins はCI/CDの自動化ツールとして広く使われており、多くの開発現場で標準的な選択肢として利用されています。クラウド環境にも対応しており、Kubernetes 上のエージェントを動かすことでスケールアウトを容易にします。
ただし「Jenkins はCI/CDのためのツールであり、クラスタ全体の運用を管理するのが Kubernetes ではない」という基本を忘れないことが大切です。
この点を押さえると、CI パイプラインの設計とクラスタ運用の設計を混同せずに済みます。
Kubernetesとは何か
Kubernetes は分散アプリケーションを動かすためのオープンソースのプラットフォームです。多数のコンテナを自動的に配置・スケール・回復させる機能を持ち、クラスタと呼ばれるグループで動作します。日常的には Docker などのコンテナと組み合わせて利用され、アプリの信頼性と可用性を高める役割を果たします。Kubernetes は「どう動かすか」を管理する道具であり、個々のビルドやテストを自動化する機能は Jenkins の領域です。協調して使うことで、コードを作る人と動かす人の両方を助けることができます。
Kubernetes の基本は、コンテナの配置、ネットワーク、ストレージ、障害時の自己修復などを自動化する点です。これにより、開発者は「何を作るか」に集中し、運用担当者は「どのように安定して動かすか」という観点で効率化を図れます。
用途が違う点と使い分けのコツ
ここが最も混同されやすいポイントです。以下の点を意識すると、使い分けがぐっと明確になります。
・目的の違い:Jenkins はコードのビルド・テスト・デプロイの自動化を担う“実行環境”。Kubernetes はアプリを動かすための“動かす仕組み”そのものです。
・対象の範囲:Jenkins は単一プロジェクトや複数プロジェクトのパイプラインを横断して自動化します。Kubernetes は複数のマイクロサービスを同時に、信頼性高く動かすことを目指します。
・失敗時の挙動:Jenkins がビルドやテストの失敗を検知して作業を停止・通知します。一方Kubernetes は pod の再起動やスケール調整など、クラスタ全体の状態を保つ仕組みを提供します。
実務では、Jenkins で継続的インテグレーションを回しつつ、Kubernetes でデプロイ先の環境を安定運用する、という分業が基本形です。
この,使い分けのコツは「責務の切り分け」を徹底することです。コードの品質を高めたい → Jenkins。アプリを安定して動かしたい → Kubernetes。両者を別々の段階で適切に組み合わせましょう。
実務での連携イメージ
現場での連携をイメージしやすくするために、具体的な流れを要約します。まず Jenkins がコードをビルドしてテストを実行し、成果物(artifact)を作成します。次に Kubernetes がその成果物を含む新しいリリースを受け取り、クラスタ内のポッドを適切な数だけ動かしてデプロイします。ここで重要なのは、Jenkins が「誰が何をいつ実行するか」を決める中心的なオーケストレーターであり、Kubernetes が「その成果物を実際に運用環境で動かす実行エンジン」である点です。以下の表はその役割分担を短く整理したものです。要素 役割 例 Jenkins CI/CDの自動化 コードのビルド・テスト・アーティファクト作成 Kubernetes コンテナの運用・スケール クラスタ内のポッド管理・自動回復 連携 成果物をクラスタへデプロイ 新しいリリースの適用
この連携イメージを元に、現場では、CI/CD と運用の境界を明確に設計することが成功の鍵になります。続く実務例を参考にすると、より具体的な導入プランが描けるでしょう。
koneta: 最近友人と Kubernetes の話をしていて、彼は「難しくてよくわからない」と言っていました。私は雑談の中でこう返しました。『Kubernetesは大量の箱を賢く動かす仕組み。箱とはコンテナのこと。難しく見えるけれど、要は「動く仕組みを整えること」が目的ってだけなんだ。だから、最初は小さなクラスタから始めて、失敗しても自動で直してくれる仕組みを作ればいいんだよ』と。すると友人は少し安心して、最初の一歩としてローカルでミニクラスタを立ててみようと決心してくれました。
この会話からわかるのは、難しく見える概念でも、実際は“動かす仕組みを整える”というシンプルな考え方に集約できるということです。Kubernetes の世界は奥が深いですが、身近な目標を設定すれば、日々の学習も前進します。
次の記事: 【徹底解説】acsとサロモンの違いをわかりやすく見分ける方法 »





















