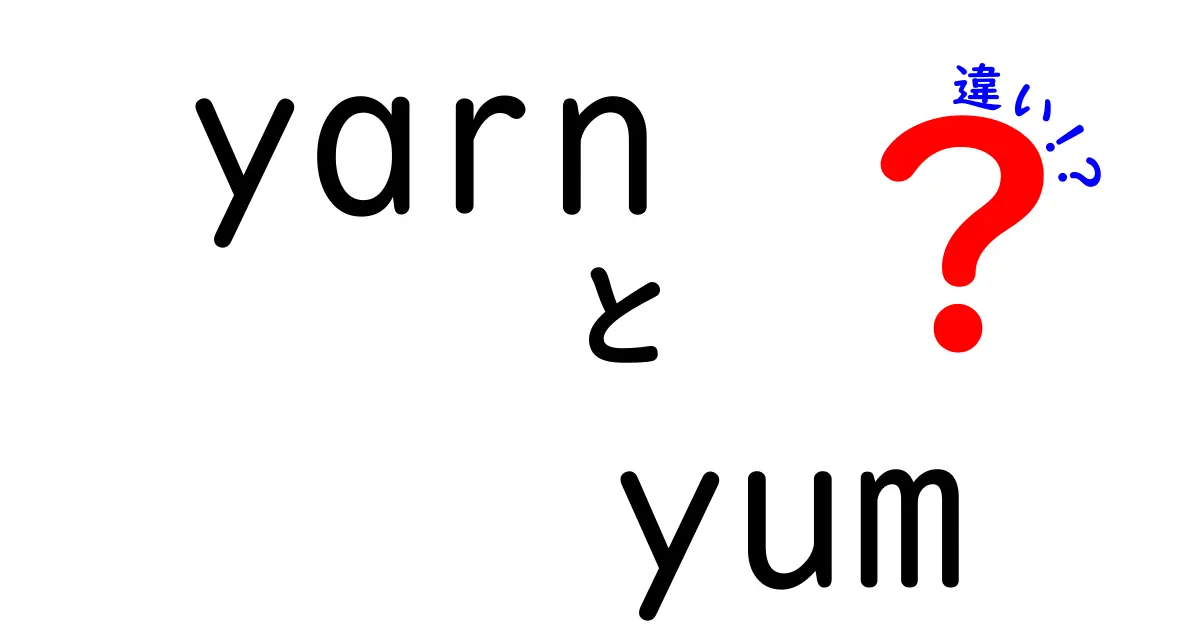

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
総論:yarnと yum の違いをひとまとめ
この二つのツールは「何かを管理する道具」という点は共通していますが、実際に担当する仕事はかなり違います。yarn は Node.js の開発現場で使うパッケージマネージャーで、主にアプリを作るときに必要な部品(依存関係)を管理します。yum は Linux のOSレベルのソフトウェアを扱う道具で、システムを成り立たせるプログラムを導入・更新します。つまり yarn はアプリの作り手寄り、yum はOSの運用寄りの存在だと覚えると混乱が減ります。
もう少し詳しく言えば、yarn は「どのパッケージをどのバージョンで使うか」を決める役割を持ち、パッケージのダウンロード元は npm レジストリなどの公開リポジトリが中心です。対して yum は「OS に必要なツールを今ある環境に足す/置き換える」仕事で、リポジトリと呼ばれる信頼できるソースからソフトウェアを取得します。
難しい言い方をすると、yarn はアプリ開発の再現性と移植性を高めるための道具、yum はセキュリティと安定性を保つための道具です。これを押さえておくと、次の質問にすぐ答えられます。
使い分けの基本原則は「何を管理したいのか」という観点です。開発中のアプリの依存関係を安定させたいなら yarn、サーバー上のソフトウェアを最新の状態に保ちたいなら yum です。これだけを覚えておくと、現場での混乱がぐんと減ります。
1章 役割の違いと基本思想
yarn は Node.js の開発現場で使うパッケージマネージャーで、基盤となる依存関係を管理するための仕組みを提供します。プロジェクト内には package.json があり、そこに依存パッケージの名前とバージョンが記載され、yarn install または yarn install --frozen-lockfile で正確な組み合わせを再現します。yarn.lock ファイルは、チーム全体で同じ依存構成を再現する鍵です。yarn は npm レジストリを主なソースとして利用し、キャッシュ機能によりインストールを速くします。Monorepo 対応、Workspaces、プラグイン形式の機能拡張などの先進的な機能も取り入れられました。最近の動向としては Yarn 2 以降の Berry 系が導入され、可搬性とパフォーマンスを重視した設計になっていますが、基本的な使い方は従来と大きくは変わっていません。
一方 yum は Linux 系統のOS管理ツールで、システムを動かすソフトウェアを安全に配布・更新する役割を担います。リポジトリという信頼できるソースからパッケージを探し出し、sudo yum install 名前 で追加します。更新は sudo yum update 名前、削除は sudo yum remove 名前 のように、権限を持つユーザーが行います。yum は長年の実績を持つ安定志向のツールであり、セキュリティ対策として署名付きパッケージの検証や依存関係の自動解決を組み込んでいます。これにより、OS の安定性とセキュリティが保たれます。
要するに、yarn はアプリ開発の“部品箱”であり、yum はOSの“部品箱”です。それぞれが大切な役割を果たしますが、混同すると依存関係の破損やOSの不具合につながる可能性があります。将来的にどちらを使うべきかは、取り組んでいる対象がアプリケーションかOSかで判断すると簡単です。
2章 使い方とコマンドの基本
yarn の基本コマンドは次のような流れです。まず新しいプロジェクトを作るときは yarn init、既存のプロジェクトの依存関係をインストールするには yarn install、特定のパッケージを追加するには yarn add パッケージ名、削除には yarn remove パッケージ名、アップデートには yarn upgrade パッケージ名 を使います。これらの操作は package.json と yarn.lock によって再現性を保ちます。yarn install は yarn.lock を読み込み、同じファイルがある端末で同じバージョンの依存関係がインストールされることを保証します。OS の yum では、コマンドは主に sudo をつけて実行します。基本は sudo yum install 名前、sudo yum update 名前、sudo yum remove 名前 の組み合わせです。OS のバージョンやディストリビューションによっては dnf へ移行している場合もあり、環境に合わせて使い分けることが大切です。
この違いを理解しておくと、開発と運用での作業手順が混ざらず、トラブルを減らせます。yarn は開発用のツールとしての動作を前提にしており、yum は運用用のツールとしての安定性を重視します。現場では、開発チームと運用チームで役割を分けて作業する場面が多く、コミュニケーションのコツとして、どちらのツールを使っているかを明確に共有することが重要です。
3章 セキュリティと信頼性の考え方
yarn には npm レジストリ由来のパッケージに対する整合性チェックがあり、yarn.lock による再現性でサプライチェーンリスクを低減します。署名ファイルや checksum の検証が組み込まれており、意図しない依存関係が入るのを防ぎます。一方 yum は OS の署名付きパッケージを検証し、信頼できるリポジトリからのダウンロードを担保します。セキュリティの観点では、OS レベルの更新は定期的に実施すべきで、サードパーティのリポジトリを追加する場合はその信頼性を確認します。日常の話として、開発者は公開パッケージの脆弱性情報を監視し、必要に応じてバージョンを固定します。OS 管理者は yum の設定を慎重に行い、署名検証を有効にし、失敗時にはエラーハンドリングを整えます。これらは小さな選択の連続ですが、長い目で見るとシステムの安全性と開発の安定性を大きく左右します。
4章 現場での使い分けのコツ
実務上は「何を目的にしているか」で判断します。アプリの開発に関わる場合は yarn の方が効率的です。サーバーの運用やOSの管理を任されている場合は yum の方が適しています。また、チームでの作業ではロックファイルや署名ポリシーを共有することで、同じ環境を再現しやすくなります。導入前には、プロジェクトの要件とセキュリティポリシーを確認し、適切なリポジトリの設定、適切な権限レベル、バックアップの計画を組み込みます。実務では、日常の作業の中で小さな改善を積み重ねることが最終的な安定性につながるのです。
ある日の放課後、友人が yarn の話題を持ち出しました。彼は npm からの乗り換えを検討しており、なぜ Yarn が選ばれるのかを私に尋ねました。私はこう答えました。yarn には依存関係のロックファイル yarn.lock があり、みんなが同じパッケージ構成で動く保証を生み出します。これがプロジェクトの再現性を高め、部署が違っても同じ環境を再現できる大きな理由です。これにより、同じチームでも場所が違って開発していても、互いの環境差を気にせず作業を進められます。もう一つの魅力はキャッシュの活用で、同じパッケージを再度インストールする時の時間を短縮できる点です。正直なところ npm も進歩していますが、安定性と速度のバランスをとりたい時には Yarn が有力な選択肢になるのです。
次の記事: expoとフェアの違いを徹底解説!初心者にも伝わる使い分けガイド »





















