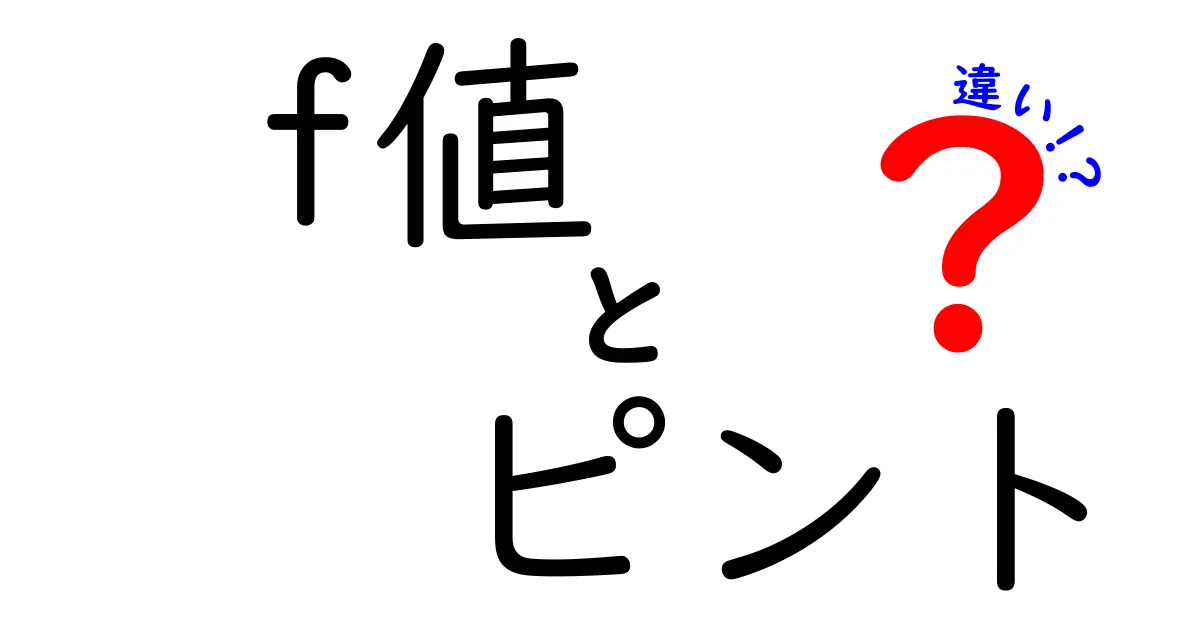

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
f値とピントの違いを正しく理解するための基礎知識
写真を撮るとき、カメラの世界にはいくつかの似ているようで違う仕組みが混ざっています。とくに「f値(エフち)」と「ピント」という言葉は、似た場面で混乱しやすいポイントです。まずは基本をそろえましょう。
f値はレンズの開口の大きさを表す数字であり、光の量を決める鍵です。数字が小さいほど開口が大きくなり、たくさんの光を取り込めます。反対に数字が大きいほど開口は小さくなり、室内の暗い場所ではシャッタースピードを遅くしてしまい、手ブレの原因になることがあります。
さらにf値は被写界深度、つまり写真の前景と背景がどれくらいピントが合って見えるかにも影響します。つまりf値は「光の量」と「ピントが届く範囲」の両方に関係してくる重要な数字です。
ここで混乱しやすいのがピントの意味です。ピントは“被写体がシャープに見える位置”を指しますが、それはカメラのレンズが対象物をどの距離で焦点を合わせるかを決める操作です。つまりf値がどうであっても、ピントを変えれば前後の被写体の見え方は変わります。ただし、f値を大きくしても被写界深度は深くなる一方、ピント自体を変えるわけではありません。
本稿では、f値とピントの違いを分かりやすく整理し、撮影現場での使い分けを紹介します。以下の項目はすべて、中学生にも伝わる言葉で説明しますので、学校の授業の合間にでも読んでください。写真は技術だけでなく「観察する力」と「試してみる勇気」が大切です。
まずは焦点の位置と光の量の両方を同時に意識する癖をつけることから始めましょう。
f値とは何か?ピント合わせの仕組みと関連性
f値とは、レンズの開口部の大きさを示す数字です。分母の焦点距離で分数のように表現され、数字が小さいほど開口が大きく、より多くの光を取り込みます。写真の明るさはこの光の量で大きく変わり、夜景や室内の撮影ではf値を小さくすることでシャッターを速くして手ブレを減らせます。
しかしf値が小さいと“被写界深度が浅く”なるため、背景が大きくボケやすくなります。逆に大きいf値は光量を少なくしつつ、背景も前景もできるだけシャープに写るようにします。
ここで重要な点は、f値は“ピントの位置そのもの”を決めるものではない」ということです。ピントを合わせる位置は、別の操作で決定します。
ピントを合わせる方法は大きく分けて二つ。オートフォーカス(AF)とマニュアルフォーカス(MF)です。AFはカメラが被写体を自動的に見つけて焦点を合わします。動く被写体にはAF-CやAF追従モードなどが用意され、設定次第で使い勝手が変わります。MFは自分の手で直接ピントリングを回して合う位置を探す方法で、微妙な距離を慎重に合わせたいときに役立ちます。
結局、f値とピントは別々の調整要素であり、現場では両方を組み合わせて写真を作っていくことが多いのです。
実践で使える違いの見極め方と写真編成のコツ
では、実際の撮影でどう使い分ければ良いのでしょう。まずは「何を主役にしたいか」を決めます。主役を際立たせたいときは背景をぼかして主役を強調するためにf値を小さくします。逆に、周囲の要素も大事なときはf値を大きくして全体をシャープに保ちます。次にピントの置き方です。被写体が近い場合は近距離のピントを正確に合わせ、背景まで含めたいときは被写界深度の広い設定を使いましょう。
実戦のコツとしては、Hyperfocal distance(ハイパーフォーカル距離)を意識すると良いです。これは、焦点距離とf値に応じて前景・中景・背景まである程度の距離で全体がシャープになるような距離のことです。風景写真や街のスナップで活躍します。
また、動く被写体を撮るときはAFの追従性能を活かし、必要に応じてシャッタースピードを調整します。シャッター速度と光量のバランスを崩さないことが大切です。
写真は科学と芸術の両方が混ざった活動です。
理屈を知るだけでなく、実際に場面ごとに試してみると、感覚が磨かれていきます。
次の章では、身近なシーン別の具体的な設定例をいくつか紹介します。
昨日、友だちと写真の話をしていて、f値とピントの違いについて深掘りしてみたんだ。友だちは『f値を下げると写真が明るくなるのは知ってるけど、ピントとどう関係してるの?』と聞いた。私はこう答えた。『f値はレンズの開口の大きさを決めて、光の入りやすさと被写界深度を同時に左右する。ピントはその光の中で“どの位置をシャープに見せたいか”の調整。つまり、背景をぼかすのか、全体をくっきりさせるのかは別々の判断だ。』と。話は続き、手ブレを防ぐコツや、夜の街での撮影テクニック、そして友人が撮った写真での失敗例を挙げてくれた。私は『失敗は学びの宝石』と笑い、次は自分のスマホにも取り入れて練習する約束をした。





















