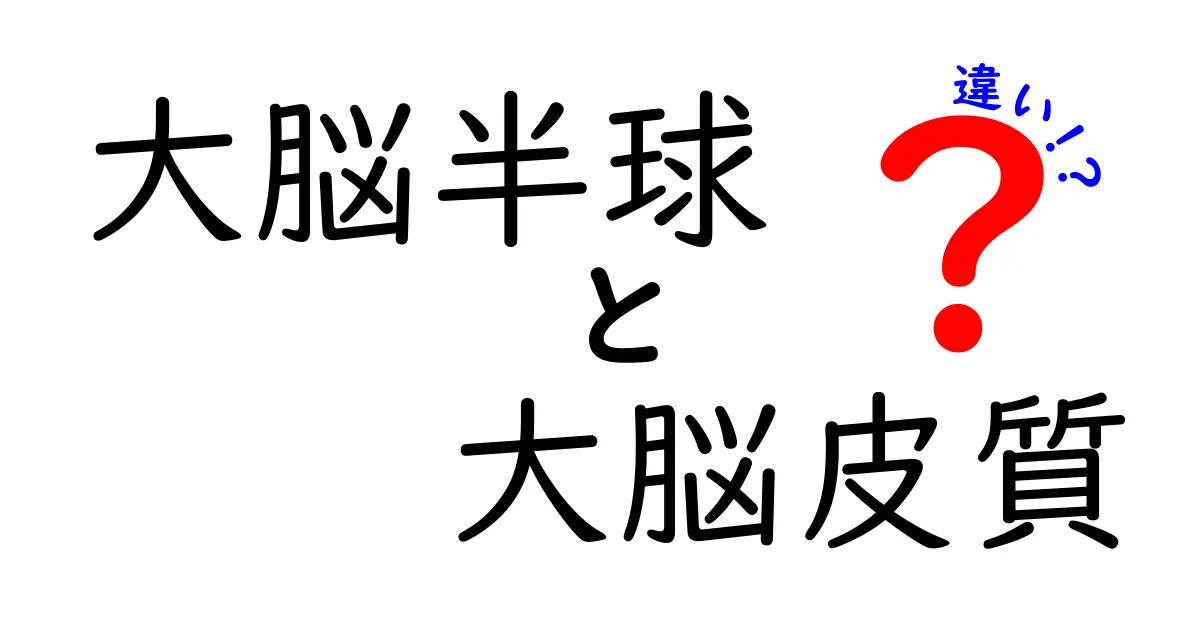

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
大脳半球と大脳皮質の違いを理解する
まず「大脳半球」とは何かを押さえましょう。大脳半球は脳の大きな左右二つの塊で、左半球と右半球に分かれています。日常生活で私たちが感じる思考や動作の多くは、これらの半球が協力して動く結果です。左右の半球は脳梁(のうりょう)と呼ばれる太い神経の束で結ばれており、情報を行き来します。
この「行き来」がうまくいかないと、言葉や手の動き、記憶の呼び出しなどがうまくいかなくなります。
大脳皮質はこの大脳半球の外側を覆う薄い灰色の層で、脳全体の機能の「処理部隊」と言われます。皮質は幾重にも折りたたまれ、表面積を広げることで、より複雑な情報処理が可能になります。
一方で大脳半球は一枚の地図のような役割を持つわけではなく、半球ごとに得意な分野を持ちながら、必要に応じて互いに協力します。左半球は言語や論理、数の処理などの「順序立てた作業」を担当することが多く、右半球は空間の認識や創造的な作業、音楽的な感覚などを補完します。ただしこの分業は絶対ではなく、状況や学習により半球間の協同は大きく変化します。実際には両方の半球が多くの場面で同時に働いており、私たちが話す言葉や描く絵、体を動かすときには、それぞれの部位が役割を分担しながら連携しています。
大脳半球と大脳皮質の役割と日常のイメージ
日常の中で「脳」が働く場面を思い浮かべると、まず視覚や聴覚などの感覚が皮質で処理される点が見えてきます。例えば、道を歩いていて信号が赤と青を交互に変えるのを「色の情報」として視覚皮質が受け取り、それを元に次にどの街路を渡るか決めるのは前頭前野を含む皮質の役割です。部位ごとに特殊な領域があり、それぞれの領域が連携して私たちの行動を成立させます。
これらの作業は視覚皮質、聴覚皮質、体性感覚皮質など、部位ごとに分かれつつも、情報を総合して意味づけすることで日常の行動を生み出します。
大脳皮質は情報の「処理工場」のような存在で、受け取った刺激を分類・解釈・判断・記憶へとつなげます。
一方、半球の役割分業についても触れておきましょう。左半球は言語の組み立てや論理的な思考を支える場として機能することが多く、右半球は空間認識や直感、ニュアンスの理解に強いとされています。もちろん、実際には両半球が互いを補い合い、話す、書く、計算する、描く、歌うなどの多様な作業を一つの脳で実現します。つまり、学習の過程では、皮質の部位が発達し、半球間の協調性が高まることによって、より複雑な思考や運動が可能になるのです。
日常の例としては、スポーツをする時の反応速度、音楽を聴くときのリズム感、友達と会話するときの言葉選び、宿題を計画的に進めるときの段取りなど、すべてが脳のさまざまな部位の協調で成り立っています。新しいことを覚えるときには、皮質の回路が網目のように広がって強化され、その結果、私たちは少しずつ難しいことも覚えられるようになります。学習のコツは、視覚・聴覚・体感といった感覚情報を、脳がうまく結びつけて意味づけを行う「繰り返しと結びつけ」を意識することです。
ねえ、最近授業で脳の話をしていたね。大脳半球と大脳皮質って、左右の場所と外側の層って意味で覚えやすいんだけど、実際はどう違うの?と友だちに聞かれて、私はこう答えた。大脳半球は脳の左右の“くに”みたいなもので、それぞれが得意なことを分担している。左は言葉の組み立てや計算、右は空間感覚や創造性を支える。皮質はその“外皮”にあたる薄い層で、受け取った情報を処理する工場のような役割。つまり、脳全体を動かすための道具箱が、半球と皮質の組み合わせで働いているんだ。昨日の授業のノートを読み返しながら、整理すると、脳は私たちの体験を意味ある知識に変える魔法の装置みたいと感じた。





















