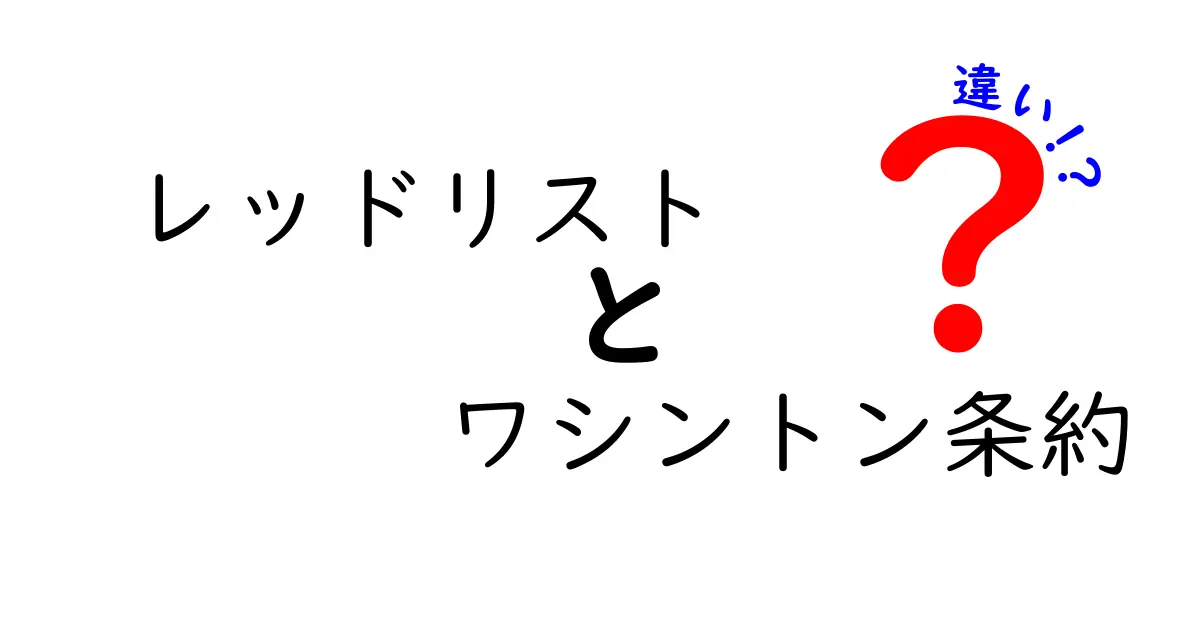

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
レッドリストとワシントン条約の違いを徹底解説
この章では、世界の生物を守る仕組みのうち、レッドリストと ワシントン条約がどう異なるのかを、専門用語をできるだけ使わず、日常の例えで解説します。まず大事な点は、「どんな生物が保護の対象になるのか」という視点の違いです。
レッドリストは科学者が作る「絶滅の危機度合い」を示す評価リストで、世界規模で公開されます。
これによって、研究者や自治体がどの種に注意すべきかを知る手がかりになります。
一方、ワシントン条約は国と国の間で結ばれた法的な約束で、どの動物や植物が「国際的に売買していいか」を制限します。
この違いを理解すると、ニュースで「絶滅危機」と「国際取引規制」という言葉が出てきたときの意味がすぐつかめます。
以下では、それぞれの目的、対象、運用の仕方、そして実際の影響がどう変わるのかを、例を交えて詳しく見ていきましょう。
レッドリストの基本と仕組み
レッドリストは国際的な評価リストで、生物の絶滅リスクを階層的に分類します。分類にはCR、EN、VU、NT、LC、DD、EW、EXなどがあり、各カテゴリには厳密な基準があり、人口の大きさ、減少傾向、地理的分布、データの充足度などが組み合わさって決まります。
このリストはどの政府の法的拘束力を持つものではありませんが、研究者や資源管理担当者にとって重要な手がかりになります。
つまり、レッドリストに載ると「この種は事前に保護を検討すべき」という信号になります。
ただし、全てのレッドリスト掲載種が直ちに保護法の対象になるわけではない点に注意が必要です。実際には国ごとに保護の法制度が異なり、リストの情報を踏まえて国内法がどう適用されるかが決まります。
また、データの不確実性を示す Data Deficient というカテゴリもあり、情報が不足している種については今後の研究が重要です。
ワシントン条約の基本と仕組み(CITES)
ワシントン条約は国際的な取り引きの規制を目的とする条約で、CITESとして知られます。
主な仕組みは、動物や植物をAppendix I, II, III の三つの追加表に分類し、それぞれ「商取引を全面禁止」「商取引を管理」「加盟国間の協力関係の維持」というように異なる規制を設定します。
この規制は加盟国内で法的拘束力を持ち、輸出入には許可証が必要です。違反すれば罰則が科され、取引の透明性を高めることで違法取引を抑止します。
つまり、ワシントン条約は「国際的な商取引の安全性を守る」ための仕組みであり、レッドリストが示す危機度とは別の情報を提供します。
実務的には、企業や研究機関が製品や研究材料を取引する際に、どの種が対象かを速やかに判断できるよう、各国の公的機関がデータベースと通商ルールを連携させています。
このように、レッドリストとワシントン条約は別々の仕組みですが、実際の保護活動では両方の情報を組み合わせて活用します。レッドリストが示す「生物が直面している危機の度合い」を把握し、ワシントン条約の「取引を抑制する法的な枠組み」でその危機を回避する道を作ることが多いのです。環境政策は単純なシステムではなく、科学データと法規制が互いに補完し合って動く点が、保護の現場ではとても大切です。
読者のみなさんがニュースで「絶滅危惧種」や「輸出入規制」という言葉を目にしたとき、これらがどのように日常生活とつながっているのかを思い出せるとよいでしょう。
友だちと下校中の雑談で、レッドリストとワシントン条約の話題になった。彼は『数字だけ見ても難しいんだけど、結局は“絶滅の危機”と“国際取引の制限”を別物として考えるべきだよね』とつぶやく。私は『その通り。レッドリストは科学者が危機レベルを評価するリストで、地域ごとの保護方針のヒントになる。一方、ワシントン条約は取引をコントロールする法的な枠組み。両方を知れば、ニュースの見出しが意味する大切さが分かる』と返した。雑談の中で、データの不足の話や、 Appendixの適用され方の違い、国内法との関係まで話が広がっていった。





















