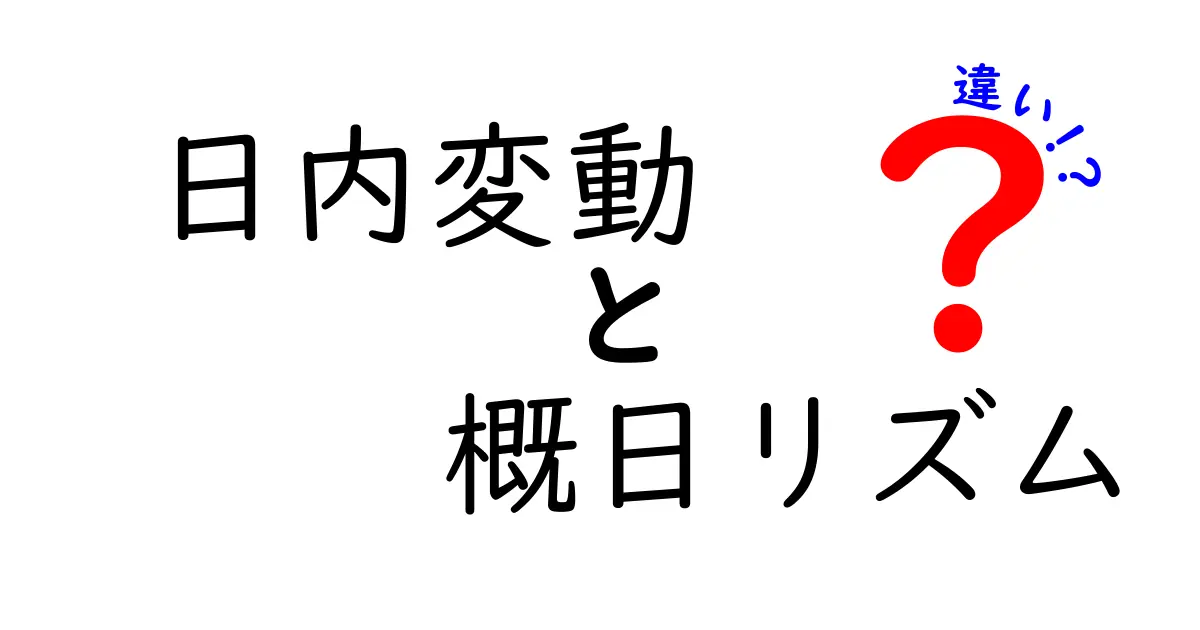

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
日内変動と概日リズムの違いをわかりやすく理解するためのガイド
日内変動は私たちの体や心の状態が日々、刻々と変わっていく現象を指します。朝起きたときの眠気、午前中の集中力、午後の活動量、夜の眠気など、時間が進むにつれて現れる変化はほぼ毎日見られるものです。これらは私たちの生活の中の環境や行動の影響を強く受け、数分から数時間のスケールで変化します。例えば、授業が始まるときの気分は眠気と覚醒のバランスに左右され、運動をした後は体温と心拍数が一時的に上がることがあります。要するに、日内変動は「その瞬間の状態の変化」を、外部刺激や活動の影響を受けて生じる短いスパンの変化として捉える考え方です。
これに対して概日リズムは体内にある長い周期の時計のようなもので、24時間を軸に私たちの眠気、覚醒、ホルモン分泌、体温などのリズムを整えます。これは外界の光や食事のリズムに合わせて時計が進むことで、私たちが意識的にコントロールできなくても日々同じリズムを保とうとする性質があります。概日リズムが乱れると、眠くなる時間が遅くなったり、眠れない夜が続いたり、朝の目覚めがつらくなったりします。朝起きると眠気が強く薄れ、日中はだるさや集中力の低下を感じることがあるのは、身体の時計が外部の光と結びつく速度と合っていないサインです。
概日リズムは遺伝的な要因も関わりますが、現代の生活ではスマホやパソコンの強い光、夜更かし、食事の時間帯など外部の刺激によって乱れやすい性質があります。概日リズムが乱れると、朝の起きづらさ、日中の集中力低下、睡眠の質の低下、体温の変動の不規則さなど、健康全体に影響が表れやすくなります。ですから、睡眠時間を一定にする、朝に軽い運動を取り入れる、朝日を浴びる時間を作る、夜は強い光を避けるなど、生活習慣を整えることが重要です。あなたが学校の初め、午後の部活、夜の勉強といった一日の流れを組むとき、日内変動と概日リズムの二つを意識すると、無理なくエネルギーをうまく使えるようになるはずです。
日内変動とは
日内変動は、体温、血圧、ホルモン、脳の覚醒状態など、日中の短い時間スケールで起こる変化のまとまりを指します。これらの変化は環境や生活習慣の影響を受けて、通常は数分から数時間の間に見られます。たとえば朝の通勤前に感じる眠気、授業の合間の眠気・集中の波、運動後の体温の上昇、食後の眠気などが日内変動の例です。また、ストレスを感じたときの心拍数の増加や呼吸の速さ、歌を歌うときの声の響き方など、身体の状態がすぐに変わる場面はすべて日内変動の範疇に入ります。これらは外部の刺激や活動レベル、睡眠直後の覚醒度など、私たちが自分で完全にはコントロールできない要因にも影響を受けるため、同じ日でも日によって感じ方が少しずつ違うのです。
日内変動の理解は、健康的な生活の基礎にもなります。授業のスケジュールや部活動の練習、勉強の計画を立てるとき、今この瞬間の自分のパフォーマンスを過大評価したり過小評価したりしないために、日内変動を意識することが役に立ちます。たとえば、眠気が強い時間帯には無理をせず休憩を入れ、体調が良いときには積極的に学習や運動を取り入れると、効率が上がることが多いです。また、睡眠の質を高める基本として、光のリセット、一定の就寝・起床時刻、適度な運動、夕方以降の刺激の抑制などが挙げられ、これらはすべて日内変動を落ち着かせ、日中のパフォーマンスを安定させる助けになります。
概日リズムとは
概日リズムは、体内にある長い周期の時計のようなもので、24時間を軸に私たちの眠気、覚醒、ホルモン分泌、体温などのリズムを整えます。これは外界の光や食事のリズムに合わせて時計が進むことで、私たちが意識的にコントロールできなくても日々同じリズムを保とうとする性質があります。概日リズムが乱れると、眠くなる時間が遅くなったり、眠れない夜が続いたり、朝の目覚めがつらくなったりします。朝起きると眠気が強く薄れ、日中はだるさや集中力の低下を感じることがあるのは、身体の時計が外部の光と結びつく速度と合っていないサインです。
概日リズムは遺伝的な要因も関わりますが、現代の生活ではスマホやパソコンの強い光、夜更かし、食事の時間帯など外部の刺激によって乱れやすい性質があります。概日リズムが乱れると、朝の起きづらさ、日中の集中力低下、睡眠の質の低下、体温の変動の不規則さなど、健康全体に影響が表れやすくなります。ですから、睡眠時間を一定にする、朝に軽い運動を取り入れる、朝日を浴びる時間を作る、夜は強い光を避けるなど、生活習慣を整えることが重要です。あなたが学校の初め、午後の部活、夜の勉強といった一日の流れを組むとき、日内変動と概日リズムの二つを意識すると、無理なくエネルギーをうまく使えるようになるはずです。
ねえ、日内変動と概日リズムの話、友だちと遊ぶ計画に置き換えると楽になるよ。日内変動は今の気分の揺れのこと、授業中に眠くなるかどうか、運動をした直後の体温の変化みたいに、すぐそこにある“今この瞬間の自分の状態”を表します。一方で概日リズムは体の時計で、24時間をひとつのリズムとして組み立てているもの。例えば朝日を浴びると眠気が薄れて姿勢がシャキッと立つのはこの時計のおかげ。時々この時計がずれると、朝が早くても眠いままだったり、夜眠れなくなることがある。
前の記事: « 概日リズムと生体リズムの違いを徹底解説 中学生にもわかる基礎講座





















