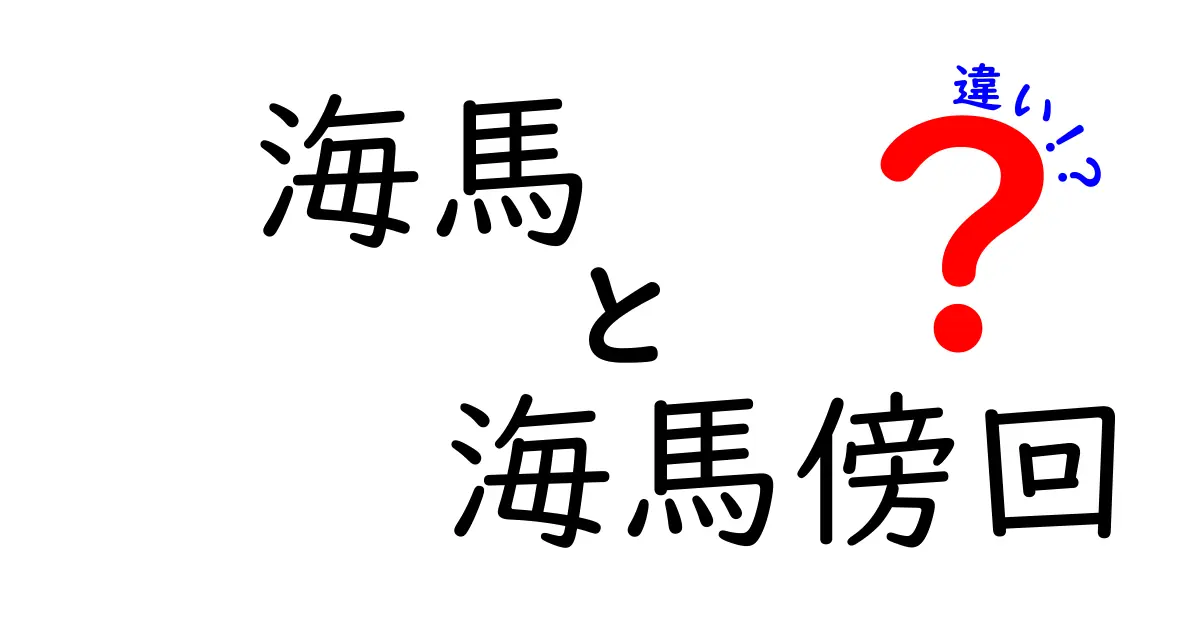

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
海馬と海馬傍回の違いを徹底解説!記憶を守る脳の二つの部分をわかりやすく比較
このページでは、海馬と 海馬傍回の違いを、脳の仕組みが苦手な人にも伝わるようにやさしく解説します。
「海馬」は記憶を作る中心的な部位のひとつで、日常の出来事を順番に並べて覚える助けをします。
一方、海馬傍回は海馬の周りの脳の皮質部分で、記憶をどの場面で使うか、どこへ結びつけるかといった整理作業を担当します。
つまり、海馬が新しい記憶を“箱”にしまう役目だとしたら、海馬傍回はその箱の整理整頓と、思い出を取り出す準備をする“仕分け人”のような役割です。
この違いを知ると、脳がどのように物を覚え、思い出をよみがえらせるのかが見えてきます。
これからの解説では、二つの部位の場所、主な役割、そして私たちの生活にどう関係しているかを丁寧に比べていきます。
最後には、二つの部位の違いをまとめた簡単な表も付けておきますので、復習に使ってください。
海馬の基本と位置
海馬は側頭葉の内側深部にあり、名前の由来は海の馬の形をしていることから来ています。
体は細長く曲がっており、記憶を作るときに出入りする情報の入口と出口の役割をもちます。
ここでの重要なポイントは、覚えたことを長く保持する作業を開始する場所だという点です。
例えば、初めて会った友達の名前を覚えたり、昨日の授業で習った新しい言葉を思い出そうとするとき、 海馬が働き始めます。
もし海馬がうまく働かないと、新しい記憶を作るのが難しくなることがあります。
だからこそ、健康な生活習慣や睡眠、適度な運動は海馬を助けます。
海馬は周囲の海馬傍回や扁桃体、前頭葉などのほかの脳の部位と連携して働き、私たちが体験したことをどう記憶として残すかを決める重要な連携網の中心にもなっています。
海馬傍回の基本と役割
次に海馬傍回の話です。海馬傍回は海馬を取り囲むように位置する脳の皮質領域の総称で、海馬の周囲に広がっています。
名前の通り海馬の隣にあり、海馬と協力して働きます。
主な役割は記憶の「取り出し準備」と空間情報の処理です。
実際には、物事を覚えるときに、どの場面でその情報を使うかを考える作業を手伝います。
例えば、学校で道順を思い出すとき、海馬傍回は場所の記憶を整理して、脳の他の部分が正しい道や状況を思い出すのを助けます。
また、場面記憶や場面を作るのにも関与し、どんな場面でどんな出来事があったかを結びつける手がかりを提供します。
もし海馬が覚えたことを“箱”にしまうとしたら、海馬傍回はその“箱のラベル”を作る人と考えるとわかりやすいかもしれません。
このように、海馬と海馬傍回は互いに補い合い、私たちの記憶の仕組みを成り立たせています。
昼休みの教室で友達と海馬の話をしていた。友達は海馬って何なのかを素朴に質問し、僕はこう答えた。海馬は記憶を作る“箱”のような部分で、海馬傍回はその箱の整理と取り出しの準備をする役目だよと。新しいことを覚えるとき、海馬が情報を取り込み、海馬傍回がどの場面でその情報を使うかを決める。眠ることや運動も、海馬が元気に働くための大事なサポートだ。授業中の細かい名前を思い出せないとき、海馬と海馬傍回が協力してくれるんだと実感した。次の日も実験の準備で頭を使うけれど、適度に休憩をとれば記憶の定着がスムーズになることを体感した。そんな小さな発見が、学習の自信につながるんだと感じた。





















