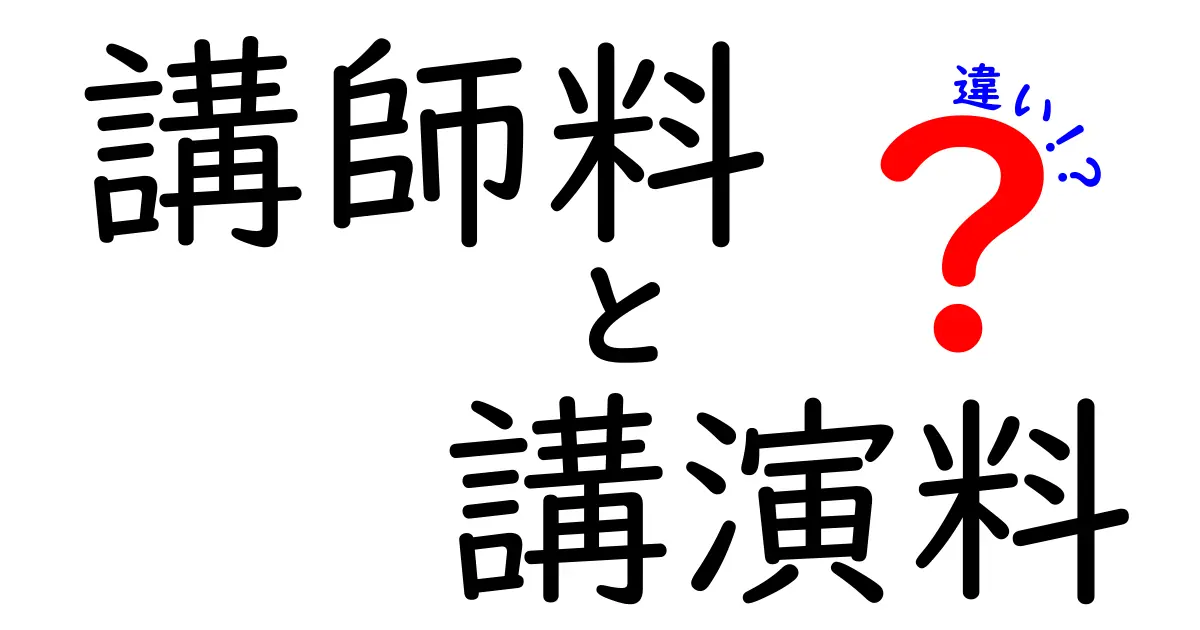

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
講師料と講演料の違いを理解するための基本
学校やイベントで「講師料」と「講演料」という言葉を耳にすることがあります。
この二つは似たような場面で使われることも多いのですが、意味や計算の仕方、支払いの流れが違います。
読者の皆さんが混乱しないよう、まずは違いの根本を押さえましょう。
ここでは、「講師料」と「講演料」の違いを、発生する場面、誰がどこへ支払うのか、契約上のポイント、そして実務でどう使い分けるかを、日常的な例や図解風の説明を交えながら解説します。
たとえば、小学校・中学校・大学の講義に関わる場合は講師料が発生するケースが多く、講演料は学会やセミナーの講演そのものの対価として支払われることが一般的です。
このように費用の性質と契約の枠組みを分けて考えると理解が進みます。
なお、同じイベントでも「講師としての指導活動」と「講演そのもの」の二つの要素が混ざることがあり、その場合は両方の費用が別々に発生するケースもあります。
結論としては、講師料は「教育・指導の提供」を対価とし、講演料は「講演そのものの提供」を対価とします。これを意識して契約書を読むと、費用の計算と支払いの流れがずっと分かりやすくなります。
以下の表や例を通じて、実務での区別をさらに明確にします。
この段階ではまだ混乱していても大丈夫。後の章で実際の契約文面の読み方や、支払い時のチェックリストを紹介します。
実務のポイントをまとめると、意味の違い、発生場面、支払先、計算方法、契約の時点での確認事項の五つが核心です。以下の表は、これらを一目で比較するためのものです。
この表を見れば、同じ「費用の支払い」でも、どの場面でどの名前が使われるかがよく分かります。
ポイントは、契約書に「講師料」か「講演料」かのどちらが明記され、支払いの対象・金額・タイミングがどう定義されているかを確認することです。
もし、イベント運営者と講師側で認識が食い違えば、後でトラブルの原因になります。
そのため、最初の段階で双方の合意を文書化しておくのが安全です。
ここまでの理解を踏まえたうえで、実務では契約文書の細かな条項を読み解く力が求められます。
次の章では、実際の契約書に現れる表現の読み替え方と、よくある誤解を防ぐチェックリストを紹介します。
ある日、イベントの打ち合わせをしていた私と先輩。講師料と講演料の話題になり、私はどちらがどの場面の対価かを上手く説明できませんでした。先輩は笑ってこう答えました。『講師料は教育・指導を提供する対価、講演料は講演そのものの対価だ。依頼の目的が継続的な指導なのか、一回限りの講演なのかで呼び方が変わるんだよ。さらに契約書には、支払時期・成果物・録音権・キャンセルポリシーなどを明記しておくことが大事だ。』その後、私たちは実際の案件表を作成して、講師料と講演料の違いを一目で判断できるようにしました。





















