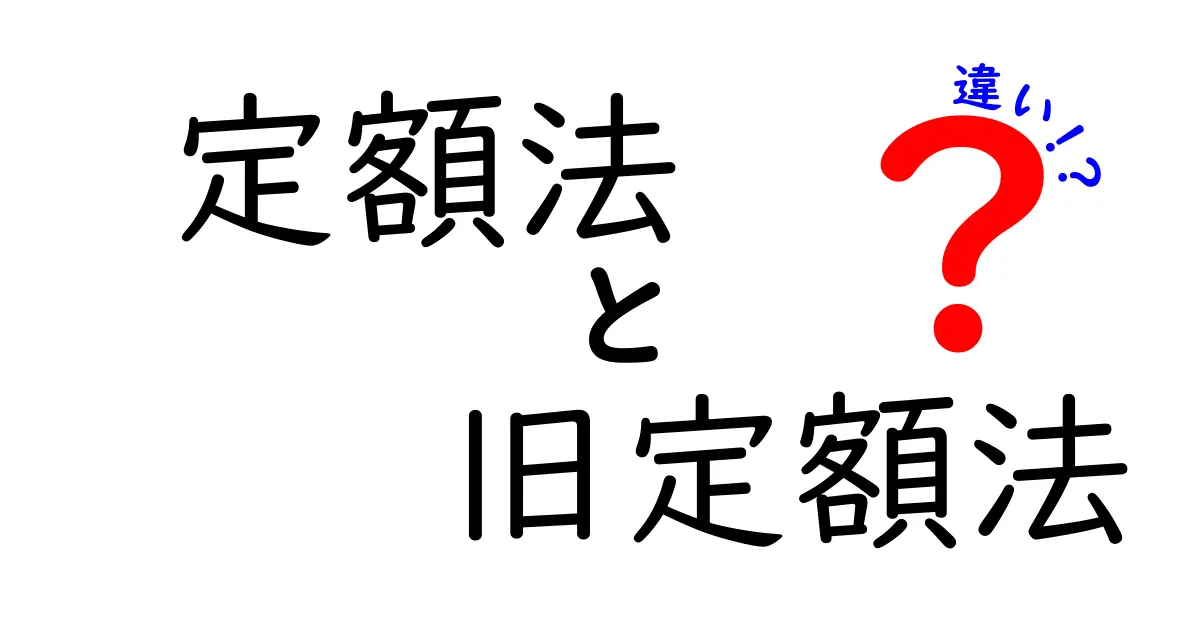

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
定額法と旧定額法とは何?基本的な違いをわかりやすく解説
減価償却とは、設備や機械、建物などの高額な資産を購入した際、その価値を一定期間に分けて費用として計上する会計の方法の一つです。
定額法は、毎年同じ金額を償却費として計上する方法で、資産の耐用年数にわたり均等に費用を割り振ります。
一方、旧定額法は、2007年(平成19年)の税法改正前に使われていた定額法で、現在の定額法とは少し償却費の計算方法が異なっています。
大きな違いは計算に使う耐用年数や償却率にあります。旧定額法では法定耐用年数を基にした一定の償却率を使い計算していましたが、新しい定額法ではより実態に即した見直しが行われています。
これにより、資産の減価償却費が少しずつ変わってきています。初心者の方でも、減価償却の基本と旧定額法との違いを押さえておくことで、会計や経理の理解がぐっと深まります。
定額法と旧定額法の計算方法の違いを比較表で解説
まずは、実際の計算方法を比較してみましょう。下の表は具体例を使って、どのように毎年の償却費が計算されるかをまとめたものです。
| 項目 | 定額法(現行) | 旧定額法(改正前) |
|---|---|---|
| 耐用年数の考え方 | 実態に即した耐用年数を使用(法定耐用年数を見直し) | 法定耐用年数のみを使用 |
| 償却率の算出 | 定額の率を見直し、より正確に計算 | 法定償却率を単純に適用 |
| 年間の減価償却費 | 取得価額 × 償却率 | (取得価額−残存価額) ÷ 耐用年数 |
| 特徴 | より現実的な費用配分が可能 | 単純計算でわかりやすい |
この比較表からわかるように、旧定額法は単純化された計算方法である反面、実際の資産の価値低下を正確に反映しにくい点があります。一方で、新しい定額法は税法改正により耐用年数などがより合理的になり、減価償却費がより実態に合わせやすくなっています。
この違いは、特に高額資産の減価償却を行う際に利益計算や税金計算に影響を与えるため、しっかり理解しておくことが重要です。
なぜ定額法は見直されたの?税制改正の背景と影響
定額法の見直しは主に2007年の税制改正によって行われました。この改正は、資産の実態により合った耐用年数の設定や償却率の見直しを目的としています。
旧定額法は簡単で分かりやすいものの、時代や技術の進歩により資産の劣化や使い勝手が変わり、減価償却の計算が実態とずれやすくなっていました。そのため、耐用年数の延長や短縮、償却率の調整などを行い、より現実的な費用配分ができるよう改正されたのです。
この改正は企業の利益計算に影響を与え、適切な利益計上や税負担の公平性が向上しました。
特に中小企業や会計初心者は、旧定額法のイメージのまま会計処理を続けると、計算ミスや税務上のトラブルにつながる恐れがあります。
だからこそ、定額法の改正内容と違いをしっかり理解し、新しい方法を正しく適用することが大切です。
「定額法」という言葉を聞くと、毎年一定の金額を減価償却するシンプルな方法と思いがちですが、実は2007年の税制改正前は「旧定額法」という少し異なる計算方法が使われていました。旧定額法は取得価額から残存価額を引いて耐用年数で割るといったシンプルな計算。けれど資産の実態を正確に反映しにくく、新しい定額法は計算の精度を高めるために耐用年数や償却率を見直しています。これにより、今の会計ではより現実に近い費用配分が可能になっているんですよ。





















