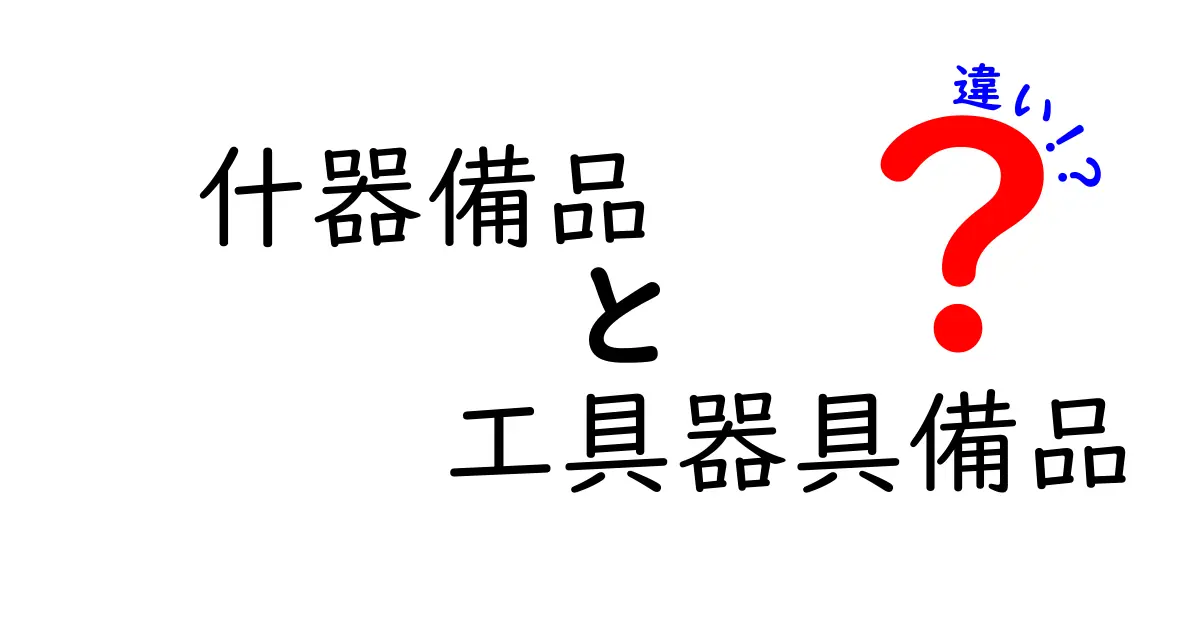

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
什器備品と工具器具備品の違いを理解しよう
ビジネスや会社の経理でよく聞く言葉に、什器備品と工具器具備品があります。どちらも会社が使うものですが、違いがわかりにくいですよね。今回はこの二つの違いをわかりやすく解説していきます。
まず、什器備品とは主にオフィスや店舗で使われる、机や椅子、棚、照明などの機器や備品のことです。一方、工具器具備品は作業現場や工場で使われる工具や機械、測定器具などを指します。
このように使う場所や目的によって名前がわかれているのです。2つとも会社の資産として計上されますが、分類が異なりますので見分けることが大切です。
什器備品の特徴と具体例
什器備品は主に事務所や店舗で使う設備や家具のことを指します。例えば、デスクや椅子、キャビネット、書類棚などが含まれます。照明器具やパーテーション、展示用の棚も什器備品に分類されます。
これらは業務をスムーズに行うための環境作りに欠かせません。形や大きさはさまざまで、耐用年数は一般的に5年から10年程度です。経理上で減価償却資産として扱われることが多いです。
例えば、ある会社がオフィスの机と椅子をまとめて購入した場合、それらは什器備品として固定資産に計上されます。購入価格が小額の場合は消耗品費として扱うケースもあります。
工具器具備品の特徴と具体例
工具器具備品は主に生産や建設、修理の現場で使う道具や機械のことをいいます。例えば、ドライバーやハンマー、電動工具、測定器、計測器具が代表的です。
これらは製造活動や作業を支える重要な資産です。耐用年数は3年から10年で、什器備品よりも耐用期間が短いこともあります。こちらも減価償却の対象となりますが、用途や価格によっては消耗品扱いになることもあります。
例えば、建設会社で使うドリルやウインチなどは工具器具備品に該当します。日常的に使う小物工具から、機械設備の一部となる大型器具まで幅広いのが特徴です。
什器備品と工具器具備品の違いをわかりやすく表で比較
まとめ:違いを押さえて適切に扱おう
今回は什器備品と工具器具備品の違いについてお話ししました。どちらも会社の大切な資産ですが、使用場所や用途、耐用年数などで区別されます。
経理や会計、税務の処理においても正しい区別が必要です。誤って分類すると減価償却期間や費用処理で問題が起きることもあります。
会社での資産管理を正しく行い、さらには必要な時に安心して使えるようにするためにも、什器備品と工具器具備品の違いを覚えておくことが大切です。
これからもこのようなビジネス用語の違いや使い方をわかりやすく解説していきます!
工具器具備品という言葉は聞きなれないかもしれませんが、現場で働く人にとっては普段から使う道具のことを指します。普通の家具や照明とは違い、作業を直接助けるものが多いです。例えば、電動ドリルのような機械も含まれ、壊れやすいこともあるので、どのくらい使えるか(耐用年数)が重要です。経理ではこれらを正しく分類しないと費用の計算で間違いが起きやすいため、扱いが地味に大切なんですよ。意外と知っているようで知らない存在なんです。
前の記事: « 【図解付き】ソフトウェアと無形固定資産の違いをわかりやすく解説!
次の記事: 工具器具備品と建物附属設備の違いとは?中学生にもわかる簡単解説 »





















