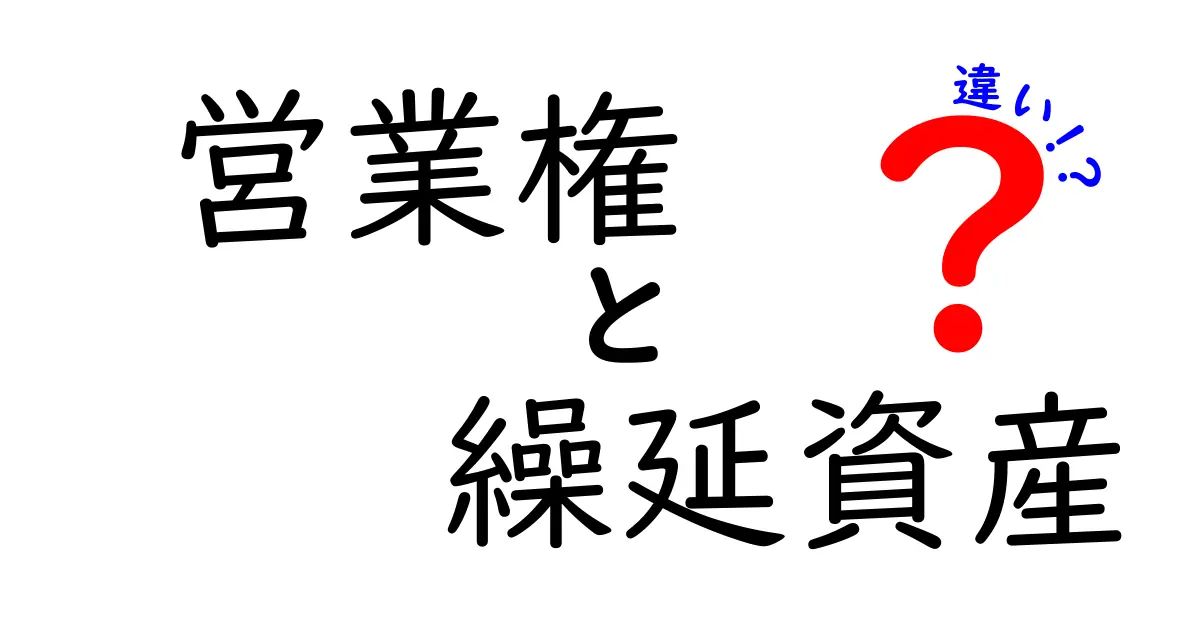

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
営業権とは何か?
営業権とは、会社が他の会社を買収したときに発生する「目に見えない価値」のことを指します。例えば、有名なブランドや優秀な社員、安定した顧客の関係などが該当します。
これらは数字ではすぐに表せないけれど、会社の価値を高める重要な要素です。営業権は無形資産の一つで、主に買収時に発生します。
会計上は企業が支払った買収価格が、買収した会社の純資産(資産から負債を引いた額)を超えるときに、その差額が営業権として計上されます。
繰延資産とは何か?
繰延資産は、費用を複数の会計期間にわたって分けて計上するための資産です。たとえば、新しい商品の宣伝費や開業費など、支払った費用が一気に消えるのではなく、時間をかけて費用化(減価償却、償却)するためのものです。
繰延資産は営業権と違い、発生する原因も使い道も異なります。繰延資産は会社自身が発生させた費用のうち、今後も効果が期待できるものを資産として計上する方法です。
営業権と繰延資産の違いまとめ
分かりやすく営業権と繰延資産の違いをまとめると以下の通りです。
| 項目 | 営業権 | 繰延資産 |
|---|---|---|
| 意味 | 買収時に発生する無形の価値 | 支払った費用で時間をかけて費用化する資産 |
| 発生原因 | 他社の買収 | 会社の自己費用(宣伝、開業など) |
| 会計処理 | 償却、減損テスト | 償却(数年にわたり費用計上) |
| 資産の種類 | 無形資産 | 繰延資産(特殊な資産の区分) |
営業権は買収という特別な場面にしか発生しませんが、繰延資産は企業が通常の経営活動の中で使う費用の処理方法の一つです。
この違いを理解すると、財務諸表や会計の仕組みがよく見えるようになります。
営業権って単なる買収のオマケみたいに思われがちですが、実は企業の“見えない強み”を数字にしたものなんです。たとえば、有名なブランドイメージや、長年築いてきた顧客関係など、単純な物やお金では表せない価値が営業権に含まれています。
それに、営業権は買収時にしか発生しないので、普通の経営活動の中ではあまり出てこないんですよ。だから会計の世界では「特別な存在」として扱われるんです。
次の記事: DCF法とインウッド式の違いとは?初心者にもわかりやすく解説! »





















