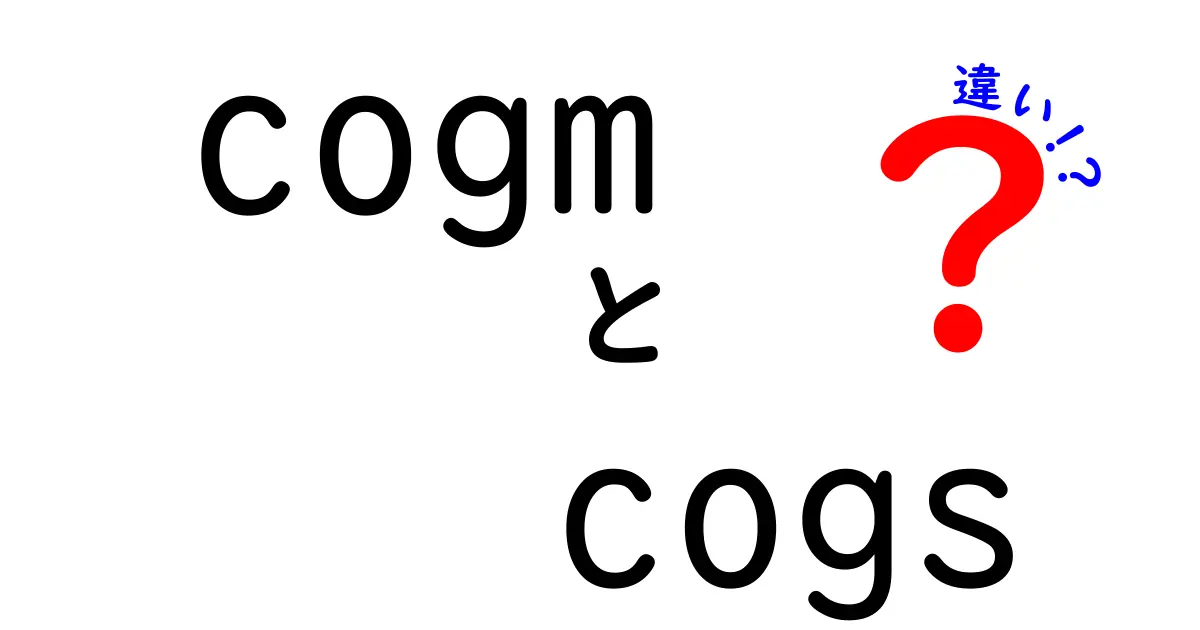

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:COGMとCOGSの基本を押さえよう
COGMとCOGSは会計の世界でよく出てくる用語です。略語の意味を覚えるだけでなく、実際の仕組みを理解すると経営の見方が変わります。COGM は Cost of Goods Manufactured の頭文字を取ったもので、日本語に直すと製造原価です。製造過程でどれだけのお金がかかったかを表します。COGS は Cost of Goods Sold の略で、日本語では販売原価と呼ばれます。これはすでに売れた商品の原価を指し、在庫が動くたびに変わる数値です。
これらの違いを正しく理解するには、原価の流れを追うのが一番近道です。材料が手元に入り、職人が作業を行い、工場で機械が動き、仕上がった製品が在庫として残り、やがてお客さんの元へ渡って売上が計上されます。この流れの中で、どの時点のコストを製造原価として計上するか、それをどのようにして在庫から売上原価へ移すのかが重要になります。
これらの違いを正しく理解するには、原価の流れを追うのが一番近道です。材料が手元に入り、職人が作業を行い、工場で機械が動き、仕上がった製品が在庫として残り、やがてお客さんの元へ渡って売上が計上されます。この流れの中で、どの時点のコストを製造原価として計上するか、それをどのようにして在庫から売上原価へ移すのかが重要になります。
ここでは見やすさを意識して、図解や実例を交えつつ、実務での使い分けがどう現場の判断につながるかを解説します。
COGMの意味と計算の基本
COGM は製造過程でかかったコストの総額を表します。具体的には直接材料費・直接労務費・製造間接費の三つを合計します。これに前期の開始在庫と当期の未完成分(WIP)を考慮して算出します。式としては、開始WIP に 当期直接材料費・当期直接労務費・当期製造間接費 を加え、終了WIP を引く形です。これが製造原価として集計される点が重要です。
この計算を理解すると、工場の生産性やコスト構造を把握しやすくなります。例えば、原材料の価格が上がれば直接材料費が増え、効率が落ちれば製造間接費が増えることが多いです。そうした変化を見て、企業は価格をどう設定するか、どの工程を改善するかを判断します。教育現場でも、COGM の扱いを教えることで費用がどう流れるのかを目で見える形で理解させやすくなります。
COGSの意味と計算の基本
COGS は販売された商品の原価です。これは期首在庫と当期に仕入れた商品の合計から、期末在庫を引くことで求められます。式としては COGS は 期首在庫 + 当期仕入高 - 期末在庫高 となることが多いです。製造業だけでなく、卸売や小売でも使われる基本指標です。ここで注意したいのは、COGS が実際に売れた分の原価を指すため、在庫が増えた期間には COOGS が低めに出る可能性がある、という点です。
現場では、COGM と COGS は別々の用途で使われます。COGM は製造部門の価値を示し、製品がどれだけのコストで作られたかを把握するための基礎データです。これを使って製造原価の管理や原価計算表を作成します。COGS は販売時点の原価で、売上総利益(粗利益)の計算に直結します。決算時には COOGS が損益計算書に表示され、企業の利益状況を示す重要な数値になります。また、在庫評価が正確であることが、COGS の精度を保つ上で欠かせません。
表で見る違いとひとことまとめ
下の表は、COGM と COGS の主要な違いを一目で比較できるようにしたものです。日常業務での計算のヒントや覚え方も付けています。どちらも会計の基礎ですが、使い分けを理解すると、財務諸表の読み方がぐんと楽になります。
この知識は商業・工業の現場だけでなく、学校のビジネス授業でも必ず役に立つ基本です。理解を深めるために、実際の企業の決算短信を読んで、COGM と COGS の表現を探してみるのもおすすめです。
本日の小ネタ:教室の黒板には黒と白のコントラストだけがある。しかし、COGMとCOGSという色の違いを知ると、数字の森の中でどこを探せば良いのかが一目で分かります。製造過程を追うCOGMは、材料費や人件費がどれだけ積み上がったかを示す長い棒グラフのよう。対してCOGSは、売れた分だけのコストを切り取る鋭いハサミのようです。両方を使い分けると、企業の利益が見えてきます。





















