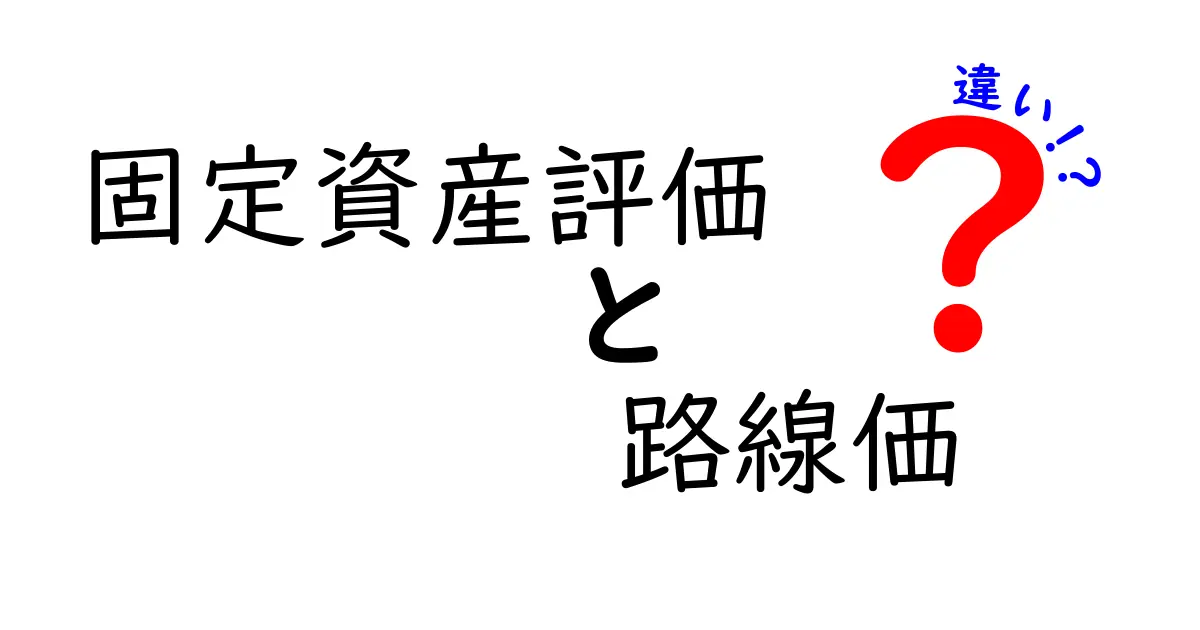

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
固定資産評価と路線価の基本とは?
みなさんは「固定資産評価」と「路線価」という言葉を聞いたことがありますか?どちらも土地や建物の価値を知るために使われますが、意味や使い方には違いがあります。
固定資産評価とは、市区町村が定める土地や建物の評価額のことです。この評価額は、毎年の固定資産税を決める基準になります。
一方、路線価は、国税庁が発表する土地1㎡あたりの標準的な価格のこと。主に相続税や贈与税を計算するときに使われます。
この2つの評価額は似ているようで、実は使う目的や計算方法が違うのです。これから詳しく見ていきましょう。
固定資産評価と路線価の違いを表で比較
まずは、どんな点で違うのかをわかりやすく表にまとめました。項目 固定資産評価 路線価 目的 固定資産税の算出のため 相続税・贈与税の算出のため 評価者 市区町村の役所 国税庁 評価時期 毎年1月1日時点 毎年1月1日時点 基準となる価格 実際の取引価格や土地の状況 路線ごとの標準価格 活用範囲 税金(固定資産税) 税金(相続税・贈与税)
このように、どちらも土地の価格を評価するものですが、使われる税金の種類や評価者が異なります。
また、評価方法も異なるため、同じ土地でも評価額が違うことがあります。
具体的な使い分けと注意点
では、実際にどう使い分けるのでしょうか?
固定資産評価は主に毎年支払う固定資産税の計算に使われ、土地や建物の価値を元に市町村が税額を決めます。例えば、家を持っている人はこの固定資産評価額に基づいて税金を払っているわけです。
一方、路線価は土地を相続したり、人に贈与したりするときに使われます。実際の市場価格より低めに設定されることも多いですが、税金を公平に計算するために国が毎年発表しています。
注意したいのは、路線価は都市部の主要道路沿いの評価が中心で、路線価が設定されていない地域は倍率方式という別の方法で評価されることです。
また、固定資産評価は地方ごとに基準が少し異なり、評価額が低くなることもあります。したがって、税金額が変わることを理解しておくことが大切です。
まとめ:固定資産評価と路線価の違いを知って賢く活用しよう
固定資産評価は毎年の固定資産税のため、路線価は相続税や贈与税のために使われる土地評価額です。
どちらも土地の価値を表しますが、評価者・評価基準・使われる目的が違うため金額に差が出ます。税金を正しく知るためには、それぞれの違いをしっかり理解しておくことが大切です。
これから家や土地を持つ、相続を考える際には、この違いを覚えておくと役に立ちますよ。
ぜひ参考にしてみてくださいね!
路線価の設定には国税庁が関わっていますが、特に面白いのは、路線価は"主要な道路沿いの土地"の価格を中心に設定されていることです。つまり、街の中でもどの道に面しているかによって価格が違うんですね。住宅地であっても、主要通りに近ければ価格が高く設定されるので、路線価はまるで街の"価値マップ"のような役割を持っているんです。これが相続税の計算に使われるため、どの道に面しているかで税金も変わることがあります。この仕組みを知ると、普段歩く街の道路の価値がちょっと気になってきますよね。
前の記事: « DCF法とインウッド式の違いとは?初心者にもわかりやすく解説!





















