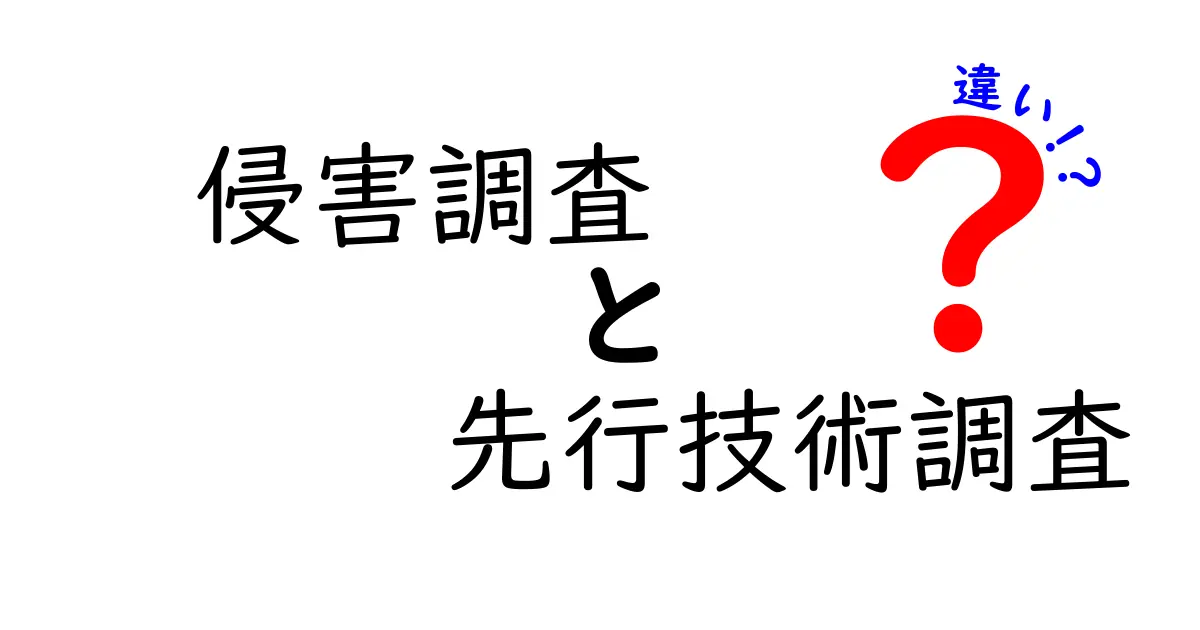

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
侵害調査と先行技術調査の違いって何?基本から学ぼう
みなさんは「侵害調査」と「先行技術調査」という言葉を聞いたことがありますか?この二つは特許などの知的財産の分野でよく使われる調査の種類ですが、目的や使い方がまったく異なります。
まずは簡単に言うと、「侵害調査」は特許や技術の侵害がないかを確認する調査、そして「先行技術調査」は新しい発明が本当に新しいものか、すでに似た技術がないかを調べる調査です。
つまり、侵害調査は他人の権利を侵害していないかを確認するため、先行技術調査は発明の新規性を判断するために行われるのです。
この違いを理解すると、特許の戦略やトラブル回避に役立ちます。
次の段落から、それぞれの調査の特徴や実際の使い方、違いについて詳しく見ていきましょう。
侵害調査とは?どういう時に行うのか
侵害調査は、特許や商標、意匠権などの知的財産権を侵害していないかを確認するための調査です。
たとえば、自分の製品を作ったけど、それが他の会社の特許を壊していないかな?
という不安を解消するためにこの調査が使われます。
侵害調査では、他人の特許権を一覧的にチェックし、特許権の範囲内に自分の技術が含まれていないか、法律的に問題がないかを判断します。
たとえば、その特許の、どの部分が守られているか(クレームと呼ばれます)を専門家が分析し、自社製品との関係を調べるのです。
その結果、侵害の可能性が高ければ製品の設計変更や使用許可の交渉などが必要になります。
つまり侵害調査は他社の権利を邪魔しないための防御的な調査といえます。
先行技術調査とは?新しい発明を守るためのチェック
先行技術調査は、新しく特許を取りたい技術が本当に新しいものかどうかを調べる調査です。
特許は「新規性」と「進歩性」が必要ですが、すでに似た技術が世の中にあれば特許が取れません。
先行技術調査では、過去の特許や論文、製品情報などを探し、自分の発明が既に知られているかどうかを入念にチェックします。
この調査によって、無駄な特許申請を避けたり、新しい発明のアイディアを深めたりすることが可能です。
発明者や企業にとってはとても重要で、特許出願前に必ず行うことが推奨されています。
また、先行技術が多く存在する分野では、調査が難しく時間もかかることがあります。
つまり先行技術調査は自分の発明の価値を守るための攻めの調査と言えます。
侵害調査と先行技術調査の違いを表でまとめてみよう
ここまでで大まかな違いは分かってきたと思います。
分かりやすく表でまとめてみましょう。
| ポイント | 侵害調査 | 先行技術調査 |
|---|---|---|
| 目的 | 他社の権利を侵害していないか確認 | 新しい技術がすでにあるか調査 |
| タイミング | 製品開発や販売前 | 特許出願前 |
| 調査対象 | 既に登録されている特許や権利 | 過去の特許、論文、商品情報など幅広く |
| 目的の性質 | 防御的(他権利の侵害回避) | 攻撃的(自分の発明価値保護) |
| 結果の活用 | 製品設計の変更や法的対策 | 特許出願の可否決定、発明のブラッシュアップ |
さいごに:どちらの調査も知的財産を守る大切な役割を持つ
今回は侵害調査と先行技術調査の違いについて説明しました。
両者は似ているようでかなり目的や調査方法が違います。
侵害調査は他社の知的財産権を侵害せず安全に事業を進めるため、
先行技術調査は自分の発明が本当に新しく価値があるか判断し、特許として守るための調査です。
知的財産はビジネスの武器となるため、どちらの調査も欠かせません。
大切なのは調査の目的を理解し、適切なタイミングで専門家の助けを借りることです。
あなたが発明や商品開発に携わるなら、この違いをしっかり押さえておきましょう!
ここまでご覧いただきありがとうございました。
先行技術調査についてちょっと面白い話をすると、この調査で見つける“先行技術”とは過去に存在した似た技術のことですが、その“似ている”判断が実はとても難しいんです。
似ている技術と完全に別物かの境界は明確には決まっていなくて、専門家の経験や国ごとのルールにも左右されます。だから先行技術調査は調査の質や深さで特許の結果が大きく変わることも。
この奥の深さが知的財産の世界の面白いところですね。





















