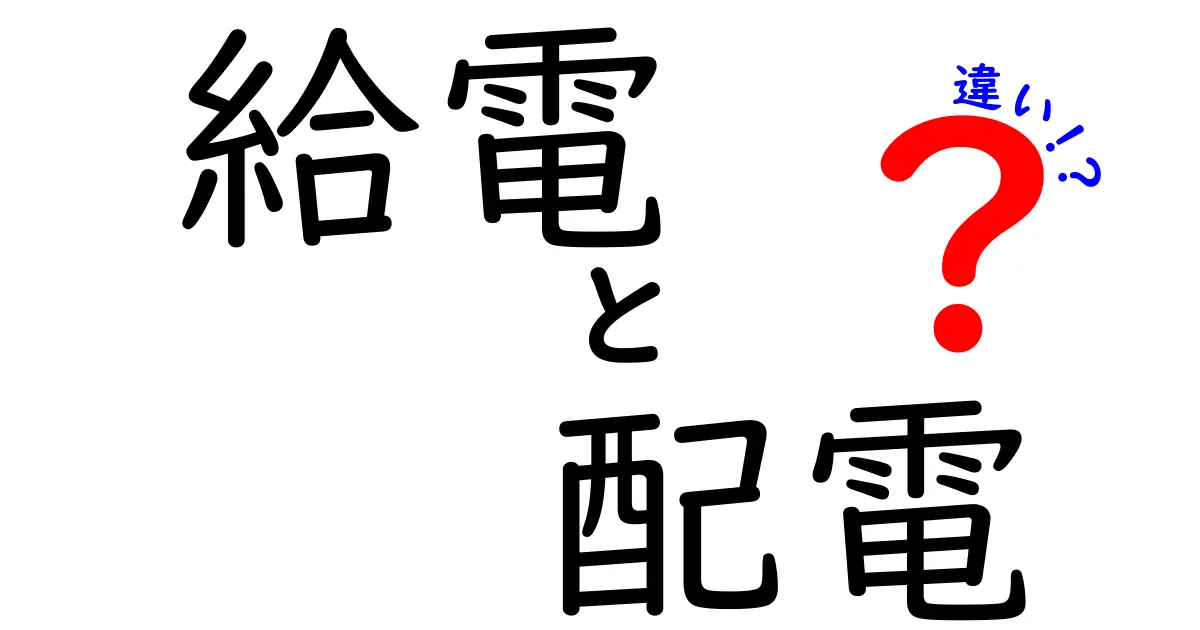

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
給電と配電の基本的な違いとは?
電気は私たちの生活に欠かせないエネルギーですが、その電気がどうやって家庭や学校、工場に届くのかを考えたことはありますか?
まず、給電(きゅうでん)とは、電気を生み出したり、発電所や電力会社から送ることを指します。発電所で作られた電気を高圧で送電線に乗せて、遠くの地域まで届ける役割です。
次に、配電(はいでん)は、その送られてきた電気を地域ごとに分けて、それぞれの家庭やビルなどに届けることをいいます。つまり、給電は大きな電気の流れを作り出す側の仕事で、配電は最後に電気を分けて送り届ける側の仕事と考えると分かりやすいでしょう。
給電と配電の違いをもっと詳しく見てみよう
これら二つは簡単に言うと、電気の“作り手”と“配り手”の違いです。
給電は発電所で電気を作り、その後、変電所を通じて送電線で遠くまで送ります。ここでは主に高電圧で送られ、ロスを減らすために工夫されています。
配電は、送電線で送られてきた電気を、より小さな電圧に下げて、それぞれの建物に届けます。配電設備は街の中に多く設置されていて、電柱や地下の配線を使いながら、みなさんの家まで安全に電気を届ける重要な役割を担っています。
給電と配電の役割比較表
| 項目 | 給電 | 配電 |
|---|---|---|
| 役割 | 発電所で電気を作り、高圧で送る | 送られてきた電気を地域や家庭に分けて届ける |
| 電圧 | 高電圧(数万ボルトから数十万ボルト) | 低電圧(数百ボルト程度) |
| 設備 | 発電所、送電線、変電所の一部 | 配電線、変電所、電柱、配電盤 |
| 対象 | 広域の地域や複数の配電エリア | 個別の住宅や建物 |
給電と配電がないとどうなる?
もし給電がなければ、電気はそもそも作られません。だから、電気が使えなくなります。
また、配電がなければ、せっかく作られた電気を家や学校、会社まで届けられません。家の電気が消えてしまい、照明やエアコン(関連記事:アマゾンでエアコン(工事費込み)を買ってみたリアルな感想)、スマホの充電などができなくなります。
給電と配電は一緒に働くことで、私たちの生活を支えている重要なシステムなのです。
「配電」という言葉は、単に電気を分けて配るという意味だけでなく、配電システムの設計が地域ごとに異なることが面白いポイントです。都市部では地下配線が多く使われる一方で、地方では電柱を多く使うため、配電設備の形も変わります。これにより停電が起きた時の復旧方法も違い、地域ごとの特性を理解すると配電の奥深さに驚くでしょう。こうした地域差も配電業界の大きなチャレンジの一つです。
次の記事: 【初心者向け】火力発電と石炭火力発電の違いを分かりやすく解説! »





















