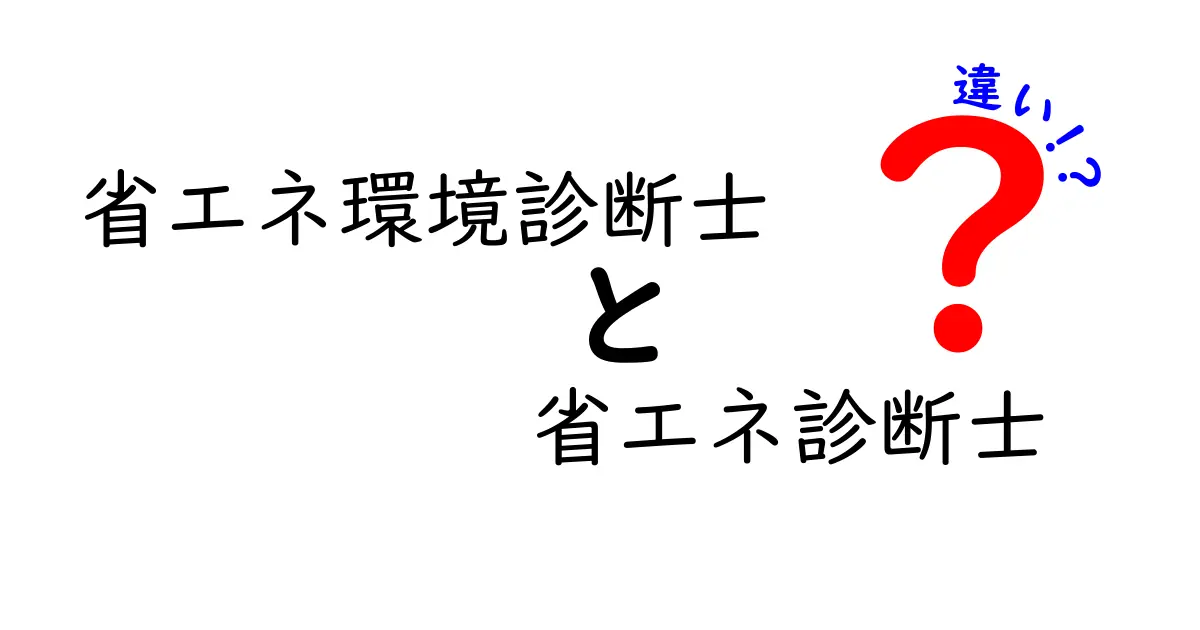

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
省エネ環境診断士と省エネ診断士、まずは資格の違いを知ろう
省エネに関する資格でよく聞く省エネ環境診断士と省エネ診断士は、名前が似ているため混同されやすいです。
しかし、この2つの資格は目的や対象としている範囲、そして試験内容や活躍の場が異なります。
省エネ診断士は、主に建物や設備のエネルギー使用状況を調べて省エネの提案を行う資格です。
一方、省エネ環境診断士は、省エネ診断の知識に加えて環境全般への配慮が必要な現場に対応できる資格で、環境保全も考えたアドバイスや診断ができます。
このように資格の名前だけでなく、役割や求められる知識の深さにも違いがあるため、自分が目指したい現場や仕事内容に合わせて選ぶことが大切です。
省エネ診断士とは?仕事内容と特徴
省エネ診断士は、企業や工場、オフィスビルなどの施設でエネルギーの使い方を詳細に調べます。
エアコン(関連記事:アマゾンでエアコン(工事費込み)を買ってみたリアルな感想)や照明、機械設備などエネルギーを使う場所を見て、無駄な消費がないかを細かくチェックします。
例えば、古い設備が多く使われている場合は、省エネ型の新しい設備の導入をおすすめしたり、運用方法の改善点を提案したりします。
資格取得のためには、省エネルギーに関する専門的な知識を身につける必要があり、試験もそれに合わせた内容になっています。
省エネ診断士は、実務においては即効性のあるエネルギー削減策を図る役割が強いのが特徴です。
省エネ環境診断士とは?環境面を踏まえた診断士の役割
一方、省エネ環境診断士は省エネ診断士が持つエネルギー削減の知識に加え、環境全体に影響を与える要素も考慮した診断が行えます。
例えば、省エネだけにとどまらず、温室効果ガスの削減や再生可能エネルギーの活用、廃棄物の減量といった幅広い環境対策も提案できるのです。
そのため、省エネ環境診断士の仕事はビジネスの場だけでなく、地域社会や行政でも求められることが多い資格です。
受験内容もエネルギー関係の知識に森林や水質、大気など環境科学の知識をプラスした幅広い内容になっています。
省エネ環境診断士と省エネ診断士の比較表
どちらの資格を目指すべき?ポイントと選び方
省エネだけを専門的に学び現場で活かしたい場合は、省エネ診断士が合っています。
一方で、環境保護にも力を入れたい、より幅広い分野で活躍したい場合は、省エネ環境診断士がおすすめです。
また、将来行政や地域の環境問題に取り組みたい人も省エネ環境診断士の方が適しています。
資格を取得するには学習内容や試験難易度も含めて検討し、自分のキャリアプランと照らし合わせることが大切です。
どちらの資格もエネルギーの有効利用と環境保全につながる社会的に意味のある資格なので、自分の興味や目標に合ったものを選んで挑戦しましょう。
省エネ診断士の資格取得には、省エネルギーの知識だけでなく現場での実践力も必要です。たとえば、実際に建物の設備を見て無駄なエネルギー使用を見つけ出すことは、ただ机上の勉強だけでは難しいもの。だから、資格取得を目指す人は座学と並行してインターンや現場見学でリアルな知識を積むことが大切です。
こうした実践的な経験が、省エネ診断士としての提案の説得力を高めるので、知らず知らずのうちにスキルが磨かれていきます。現場での努力と勉強の両輪が合わさることで、省エネ効果アップにつながるのですね。
前の記事: « ポンプと圧縮機の違いを徹底解説!わかりやすく理解しよう





















