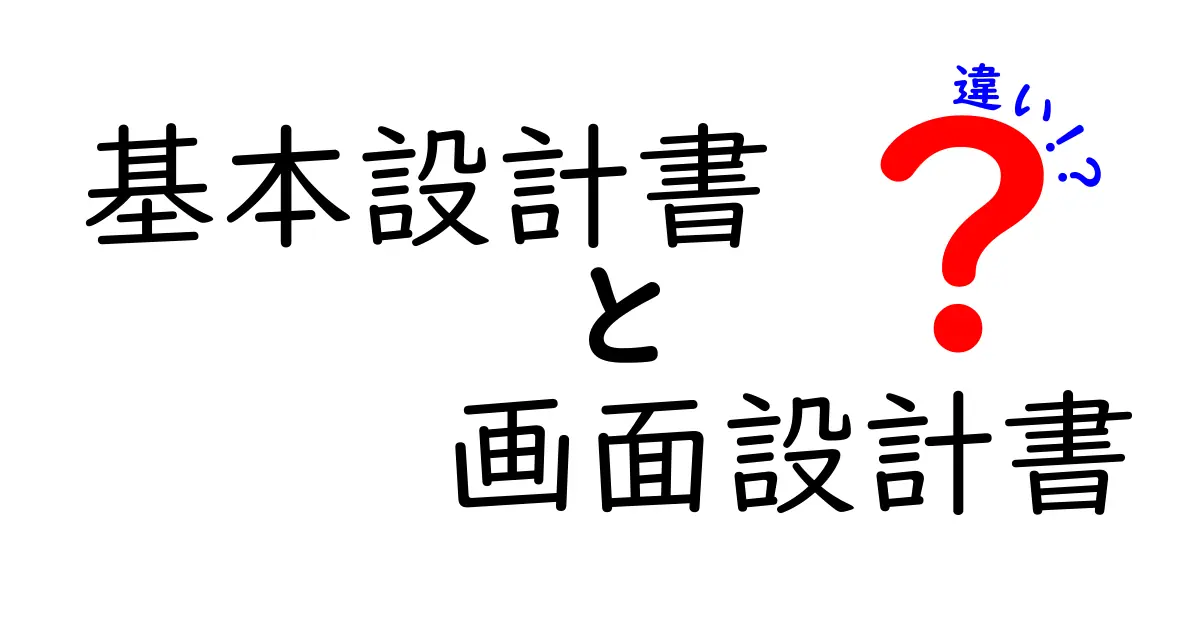

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
基本設計書とは何か?
システム開発の世界では、基本設計書はプロジェクトの土台となる重要なドキュメントです。これはシステム全体の構成や機能、動作の大まかな設計をまとめたもので、エンジニアや関係者がシステムの全体像を理解するために使われます。
基本設計書は、ユーザーの要望を基にシステムの機能をどのように実現するかを設計し、プログラムでどんな処理をするかを大まかに決めます。例えば「ユーザーは会員登録ができる」や「商品を検索できる」といった機能が含まれ、これらの機能がどのように連携するかを示します。
作成には時間がかかることもありますが、この段階がしっかりしていると後の開発やテストがスムーズに進みます。基本設計書は、プロジェクトの成功の鍵と言っても良いでしょう。
画面設計書とは何か?
一方、画面設計書は、その名の通りシステムの画面の設計を集めたドキュメントです。基本設計書がシステム全体の機能を大まかに設計するのに対して、画面設計書は具体的な「見た目」や「操作方法」を詳しく示します。
たとえば、会員登録画面のレイアウトやボタンの配置、入力項目の種類など、ユーザーが直接触れる部分について細かく設計します。カラーやフォント、エラーメッセージの内容なども含まれることがあります。
開発チームやデザイナー、ユーザー担当者が共有することで、完成後にイメージと異なることを防ぎ、使いやすい画面を作るために役立ちます。
基本設計書と画面設計書の主な違いを表で比較
ここで基本設計書と画面設計書の違いをまとめてみましょう。
| 項目 | 基本設計書 | 画面設計書 |
|---|---|---|
| 目的 | システムの全体的な機能設計 | ユーザーが操作する画面の具体設計 |
| 内容 | 機能や処理の流れ、構成要素 | 画面レイアウト、入力項目、操作方法 |
| 対象者 | エンジニア、プロジェクト管理者 | デザイナー、フロントエンド開発者、ユーザー |
| 詳細度 | 大まかな設計 | 具体的で詳細 |
| 役割 | システム全体の土台作り | ユーザビリティの確保 |
なぜ違いを理解することが大切なのか?
基本設計書と画面設計書はそれぞれ重要ですが、違いを理解しないで扱うと、開発の途中で仕様が変わったり、使い勝手が悪いシステムができてしまうリスクが高くなります。
たとえば、基本設計書に記載された機能を画面設計書で具体的に表現できていなければ、ユーザーは操作に迷い、システムの価値が下がるかもしれません。また、両方の設計書を連携させて作成することで、チーム内の認識のズレを減らし、スムーズに開発を進められます。
初心者の方には少し難しく感じるかもしれませんが、この違いを押さえておくと、将来自分でシステム開発に関わる際に非常に役立つ知識となります。
「画面設計書」という言葉を聞くと、画面の見た目だけを想像しがちですが、実はそれ以上にユーザーの操作性を考えた設計も重要です。たとえば、ボタンの配置一つで操作しやすさが大きく変わることがあります。画面設計書を通じて、ただ美しいだけでなく使いやすい画面を目指す努力がされているのです。だから、デザイナーとエンジニアの橋渡し役としても大切なドキュメントなんですね。
前の記事: « RFPと要件定義書の違いとは?初心者でもわかる基本ポイント解説
次の記事: 画面定義書と画面設計書の違いとは?初心者にもわかりやすく解説! »





















