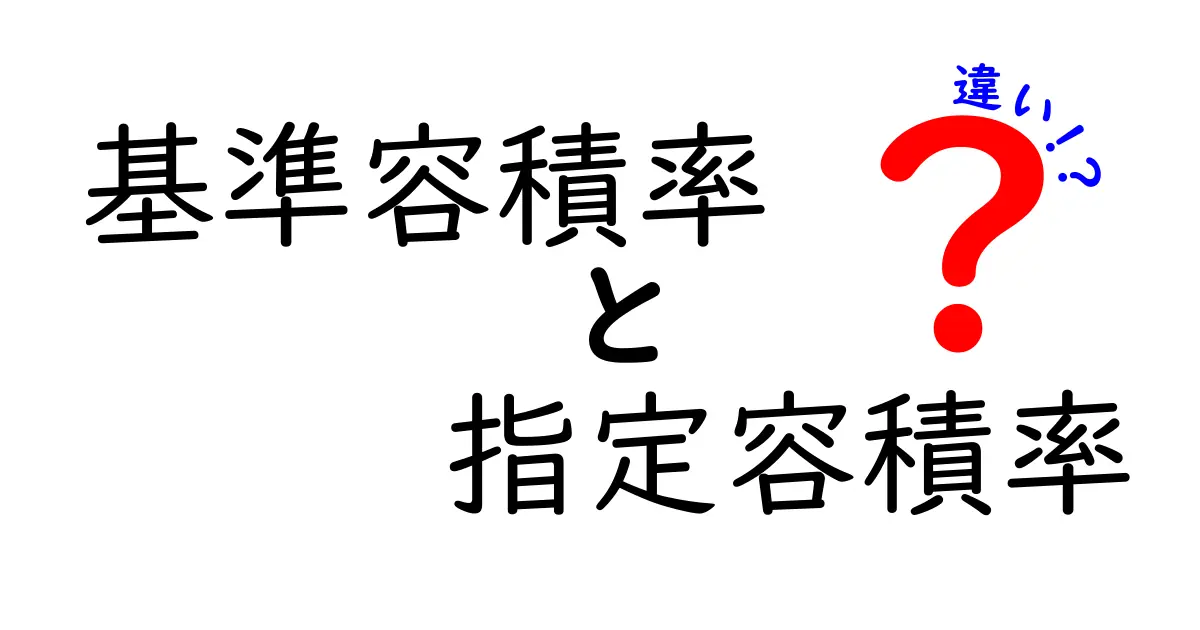

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
基準容積率と指定容積率とは?
建物を建てるときに重要な数字として「容積率」があります。
この容積率には「基準容積率」と「指定容積率」という2つの種類があり、どちらも土地に対してどれくらいの建物を建てられるかを示す基準です。
簡単に言うと、「容積率」は土地の面積に対して建物の延べ面積(床面積の合計)の割合を表し、例えば容積率が200%なら、100平方メートルの土地に200平方メートルの建物を建てられます。
しかし、なぜ基準容積率と指定容積率があるのか?それは地域によって建物の高さや大きさの制限が違うからです。
それぞれの容積率は違う意味を持っていて、その使い分けが分かると土地選びや建築計画がしやすくなります。
基準容積率とは?
基準容積率は、都市計画区域内で土地利用の基本として定められている標準的な容積率です。
これは地域ごとに国や自治体が決めたもので、建物の規模の目安になります。
基準容積率は例えば住宅地や商業地など用途地域ごとに法律で設定されていて、その土地で原則として守らなければならない建物の大きさの範囲を示します。
また、基準容積率は建築基準法や都市計画法などに基づいて定められています。
これにより、過度な建物の密集や日照不足を防ぎ、良好な住環境を保つ役割があります。
指定容積率とは?
一方、指定容積率は基準容積率をより細かく調整した容積率です。
これは都市計画の中で特定の地域や場所に対して、基準容積率よりも厳しく規制したり、場合によっては緩和したりするために指定されます。
例えば、交通の便が良い商業地区や公共施設周辺では、より高い容積率が指定されることがあり、逆に景観や周辺環境を守るために低く設定される地域もあります。
この指定容積率は地元自治体が地域の実態に合わせて細かく設定・変更できるため、より実用的な規制として機能しています。
基準容積率と指定容積率の違いまとめ
| 項目 | 基準容積率 | 指定容積率 |
|---|---|---|
| 制定主体 | 国や自治体の法律や都市計画 | 自治体の都市計画決定で地域ごとに調整 |
| 目的 | 基本的な建物の大きさの基準 | 基準容積率の調整(強化・緩和) |
| 適用範囲 | 広範囲の用途地域 | 特定の地区や土地 |
| 役割 | 建物の高さや密集を制御 | 地域の実状に合わせた容積率調整 |
つまり、基準容積率は広い地域での標準ルール、一方指定容積率はその標準ルールを土地や地区ごとに調整したものと考えると分かりやすいでしょう。
これを理解すると、土地の価値や建物の建築可能面積が見えてきて、より賢い不動産選びができるようになります。
まとめ
「基準容積率」と「指定容積率」は建築や土地利用を考えるときに欠かせない数字です。
基準容積率が基本的なルールを示し、指定容積率はそれを土地や地域ごとに調整したものです。
これらの違いをしっかり理解しておくことで、例えば新しい家を建てたり、土地を買ったりする際にトラブルを避けやすくなります。
建物の規模や土地の活用方法を決めるときは、この2つの容積率の意味と違いをしっかり知ることが大事です!
実は「指定容積率」は地域の特性や需要に応じて柔軟に変えられることが多いんです。
例えば駅に近い便利な場所では指定容積率が高めに設定されていることが多く、より大きな建物を建てやすくしています。これで不動産業者も商業施設を作りやすくなるわけですね。
逆に住宅の静かな街並みを守るため、指定容積率を低くすることで大きな建物の建設を抑制しています。
こうして地域の特色に合わせて「ちょうどいい」容積率を指定していることが多いので、土地の購入や開発時には指定容積率の確認が欠かせませんよ!





















