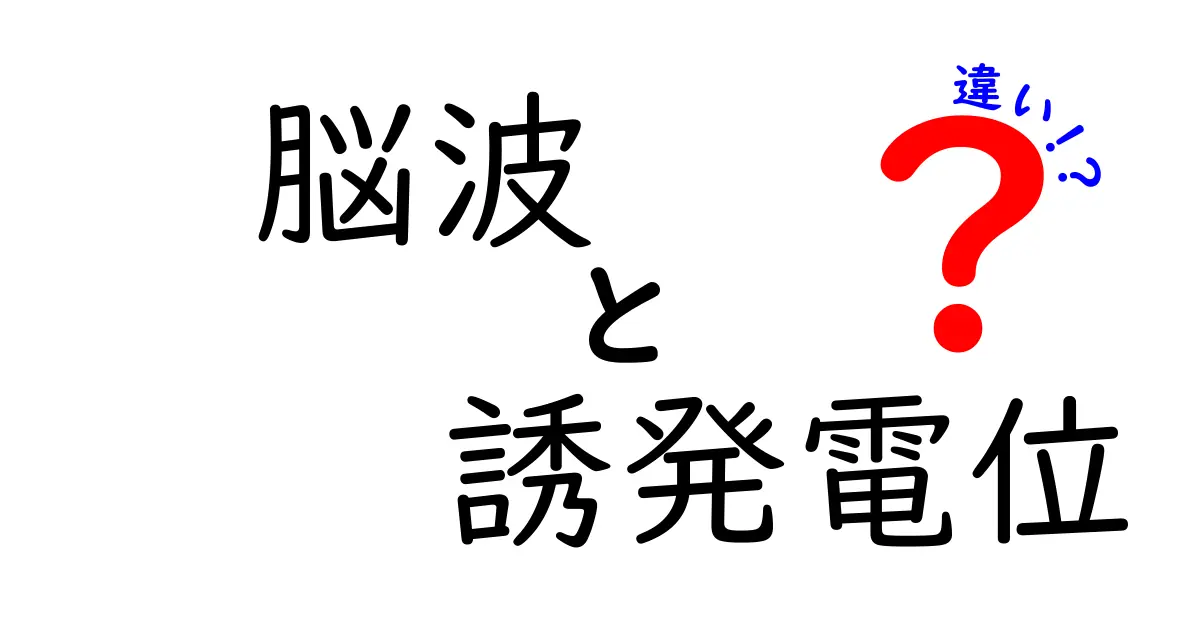

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
脳波と誘発電位って何?基本を理解しよう
私たちの脳の働きを調べる方法には、いろいろなものがあります。その中でよく使われるのが脳波と誘発電位です。
「脳波」とは、脳の活動によって生じる電気のリズムや強さを測るものです。これはリラックスしているときや集中しているときに変わる、この電気の波形を記録します。
一方、「誘発電位」とは外からの刺激(例えば光や音、触覚など)に対して脳が反応して生じる電気信号のことをいいます。つまり、ある刺激を与えた時に脳がどのような反応をするかを見るための方法です。
どちらも脳の電気活動を調べますが、使う目的や測り方に違いがあります。
脳波と誘発電位の違いを詳しく比較!目的や特徴を表で整理
脳波と誘発電位は似ているようで実は違う特徴を持っています。簡単にまとめると、脳波は 脳の自然な電気活動を測るもの、誘発電位は特定の刺激に対する脳の反応を測るものです。
以下の表で違いを確認してみましょう。
脳波と誘発電位、どんな場面で使われるの?実際の活用例
脳波は、病院でてんかんや脳の異常を調べるときによく使われます。
たとえば、患者さんがどんなときに発作が起きるのか、どの部分の脳が関わっているのかを調べるためです。
また、睡眠の質を調べる睡眠検査にも脳波は欠かせません。
一方で誘発電位は、聴覚や視覚など特定の感覚に関する神経の働きを調べる目的で使われます。
例えば、目や耳がちゃんと脳に情報を伝えているかどうかを調べるために誘発電位を測定します。
つまり、脳波は脳の全体的な状態を知るため、誘発電位は特定の刺激に対する反応をチェックするために使われると考えるとわかりやすいです。
まとめ:脳波と誘発電位はどう違う?
脳波は安静時の脳の自然な電気活動を記録し、誘発電位は刺激に対する脳の電気的反応を記録します。
測り方や目的、使われる場面が違うので、理解しておくと健康診断や病院での検査のときにも役立ちます。
どちらも脳の働きを知るための大切な手段で、病気の診断や研究に幅広く使われています。
覚えておくと、ニュースや医療の話題で出てきたときに理解しやすくなるでしょう。
「誘発電位」という言葉を聞くと、ちょっと難しく感じるかもしれません。でも実は、脳が外からの刺激に『反応』する電気信号というだけで、私たちの体のいろいろな感覚が実際にどう伝わっているかを調べるために使われているんです。
面白いのは、たとえば医者が耳や目の検査をするとき、この誘発電位を利用して音がちゃんと脳に届いているかや光を正しく感じているかを確認できます。
つまり、誘発電位は見えないけれど私たちが世界をどう感じているかを科学的に見る“窓”のような役割を果たしているんですね。すごいと思いませんか?
前の記事: « 浄土宗と禅宗の違いとは?初心者にもわかる仏教の基本ポイント解説





















