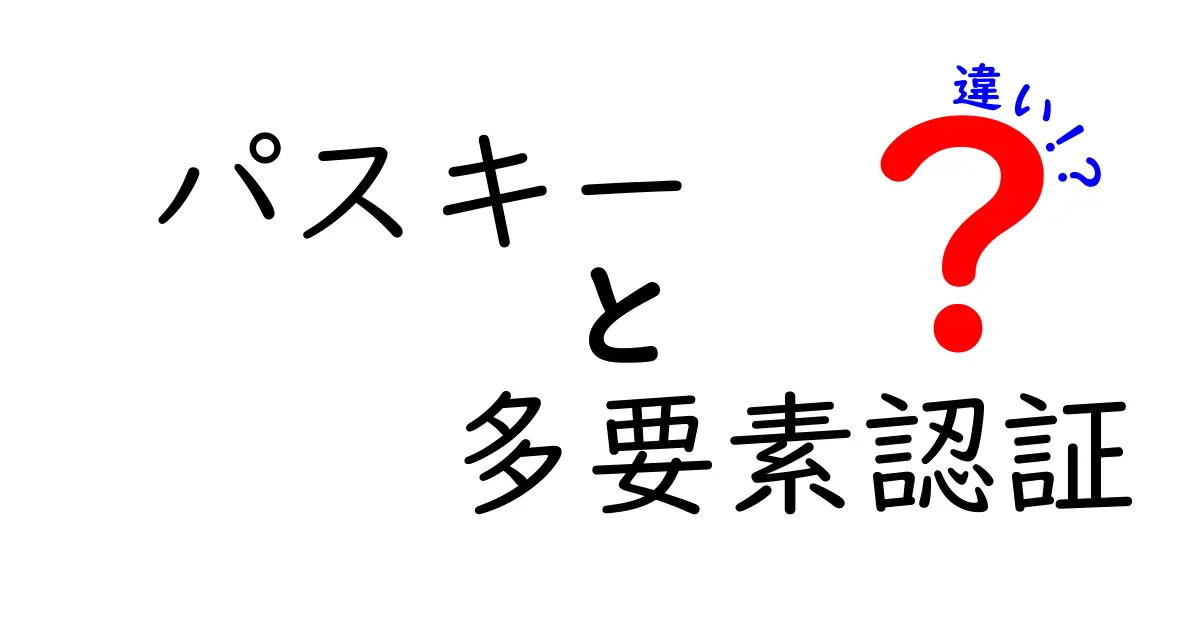

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
パスキーと多要素認証の基本的な違いを理解しよう
最近よく耳にするパスキーと多要素認証は、どちらもインターネットの安全を守るための技術ですが、その役割や使い方には違いがあります。
パスキーは、パスワードの代わりになる新しい認証方法で、簡単に言うと指紋や顔認証などの生体情報やスマホを使ってログインできる仕組みです。
一方、多要素認証(MFA)は、1つの情報だけではなく、複数の認証方法を組み合わせて安全性を高める方法です。例えば、パスワード+スマホに送られてくるコードの入力などが代表例です。
このように、パスキーは主に「認証情報の形態」で、多要素認証は「認証方法の数や組み合わせ」を示しています。
パスキーとは何か?その仕組みと特徴
パスキーとは、パスワードに代わる新しい認証技術で、暗号化された秘密鍵を利用し、ユーザーが安全にウェブサービスやアプリにログインできる手段です。
従来のパスワードは、人が覚えるため単純になりがちで、使い回しや漏洩の危険がありましたが、パスキーはデバイス内に保存されていて、第三者が盗み取ることがほぼ不可能です。
ログイン時には、生体認証やPINコードで本人確認ができ、パスキーが自動的に認証情報をやり取りします。
これにより、ユーザーはパスワードを入力する手間がなくなり、セキュリティが飛躍的に向上するのが特徴です。
多要素認証の仕組みと使われ方
多要素認証(MFA)は名前の通り、複数の異なる方法で本人確認を行うことで、不正アクセスを防止します。
大きく3つのカテゴリに分けられます。
- 知識要素(例:パスワードやPIN)
- 所有要素(例:スマートフォンやセキュリティトークン)
- 生体要素(例:指紋や顔認証)
このうち、2つ以上の要素を組み合わせて認証を行うのが多要素認証です。例えば、パスワード(知識要素)+スマホに届く確認コード(所有要素)、またはパスワード+指紋認証(生体要素)などがあります。
多要素認証により、一つの情報が漏れても、他の要素が守ってくれるので安全性が高まるという点が魅力です。
パスキーと多要素認証の違いを比較表でチェック!
| ポイント | パスキー | 多要素認証 |
|---|---|---|
| 認証方法 | 暗号化キー+生体認証やPIN | 複数の異なる認証要素の組み合わせ |
| 目的 | パスワードを不要にし、簡単安全にログイン | 不正アクセス防止のため複数証拠の確認 |
| 利用者の負担 | 操作は簡単、パスワードの入力不要 | 追加の認証操作が必要な場合が多い |
| 安全性 | 秘密鍵はデバイス内に安全保存 | 各要素の組み合わせで高い安全性 |
まとめとこれからのセキュリティ対策
パスキーと多要素認証はどちらも安全にログインするための技術ですが、パスキーはパスワードを使わずに強力な暗号技術+生体認証で個人認証を行う新しい方法です。
多要素認証はパスワードと追加の確認方法を組み合わせて安全を確保します。
今後はパスキーが普及することで、より簡単かつ安全にネットサービスを使えるようになるでしょう。
しかし従来の多要素認証もまだ広く使われており、両者を理解して適切に使いわけることが大切です。
パスキー、多要素認証の違いを知り、あなたのデジタルライフをしっかり守りましょう!
パスキーの最大の魅力は、端末内に秘匿された暗号鍵を使うことです。これによりパスワードのように外部に情報が漏れる心配が大幅に減ります。実は、この仕組みは「公開鍵暗号方式」というちょっと難しい技術を使っています。指紋や顔認証が成功すると、この暗号鍵が使われて自動でユーザーを認証してくれるのです。このおかげで、パスキーは簡単なのに非常に安全なログイン方法として注目されているんですよ。
次の記事: 防炎シートと防音シートの違いとは?用途と特徴を徹底解説! »





















